第8回 「死」の意味と「想起」と『わが町』と
2010年 12月 29日|水谷 八也
水曜ワイルダー約1000字劇場、美術担当の水谷です。
さて、先週の続きで、ワイルダーは好んで舞台に「死」を持ち込んでいましたが、それはなぜなのか。その答は『わが町』の第三幕の後半部分に集約されているので、みなさん、舞台で自分自身の《感覚》で体感してください。「想起」と言った方がワイルダー好みかもしれませんが。
ワイルダーのお芝居はその完成形が舞台の上じゃなく、舞台と想像力豊かな観客の中間にあるのではないかと、わたしは常々思ってます。舞台監督も言ってるように、死者たちの言葉の中には、聞いていて傷つくようなことも出てきますが、それがこの戯曲の完成形ではなく、それは観客の中に「想起」を起こすための要因なんじゃないでしょうか。じゃ、何を想起するのか。これはもう体感するしかないと思います(是非、体感しに来てください)。
『わが町』もそうですが、先週名前を出した一幕劇でも、ワイルダーが「死」を舞台に導き入れるとき、個別の死の過程が具体的に語られることはなく、逆にあっさりと、淡々と人は死んでいきます。あらゆる「生」を一瞬にして無に帰する死は、それ故に、個別の領域から普遍の領域へと観客を巻き込み、生の本質を鋭く浮かび上がらせます。そのような死が至るところで待ち受けていた日本の戦国時代やヨーロッパ中世の演劇に、死が大きな要因となって組み込まれていたのは必然かもしれません。そしてその時代、どちらの地域でも、演劇は宗教的でした。そもそも演劇の起源はどの国でも、まず宗教儀式にありますよね。人は演劇の中で、神、あるいは死を通した神、という絶対的存在の前に自らの「生」を対置させ、日常では見えなくなっている「生の意義」を見ていたと言えます。
先週は能のことを書きましたが、今週はイギリスの中世の演劇、道徳劇のことを少し。夢幻能と同じように、この道徳劇も大体パターンが決まっていて、「人類(Mankind)」とか「万人(Everyman)」という名前の登場人物が、様々な罠や誘惑に惑わされながらも、最後に自分の人生を悔い改めて、神の祝福を得る、というものです。『万人』では、文字通り「死(Death)」という人物も登場します。個々の物語は違いますが、生の移ろいやすさ、はかなさ、つまりは「無常感」を醸し出すことでは、能と同じかもしれません。おもしろいですね、洋の東西は異なっても、似たような感覚を持っていた時代が「近代」以前にあったというのは。どちらも現世の空しさを説き、人間を超えたもの(聖なる領域)の前に人間の小ささを見、その二つ、聖と俗の関係性の中で、わたしの生を認識する。ワイルダーのお芝居は、近代を飛び越した中世の芝居と本質的には同じだと言えるのではないでしょうか。
しかし、MankindとかEverymanという名前の登場人物を出すって、すごいですよね! 誰が見ても、「お、これはわたしの話だ」と思えてしまうんですから。『わが町』も、そうだといいのですが。(ミズタニさーん、字数オーヴァーでーす。)すみません・・・
(何字だと思ってんですか!)
ごめんなさ・・・
イテッ・・・何も叩かなくたって・・・
(ちょっと調子に乗ってんじゃないの、最近?)
・・・でも、言いたいことが
うまく
さ・・・。
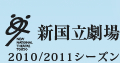







コメント
トラックバック