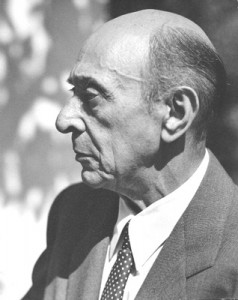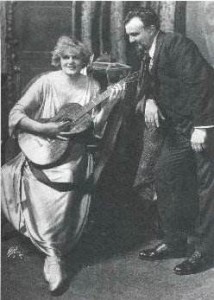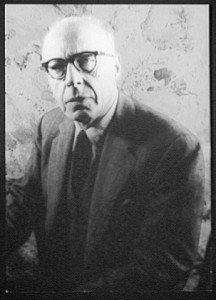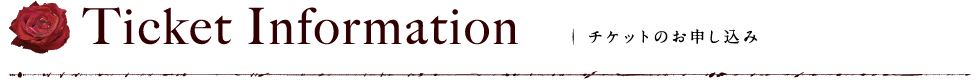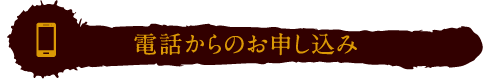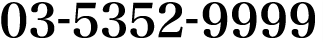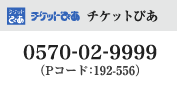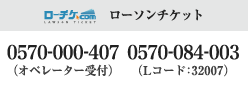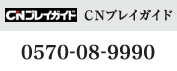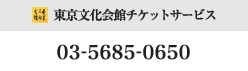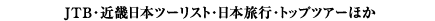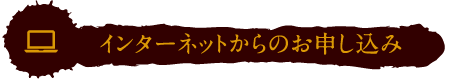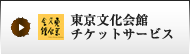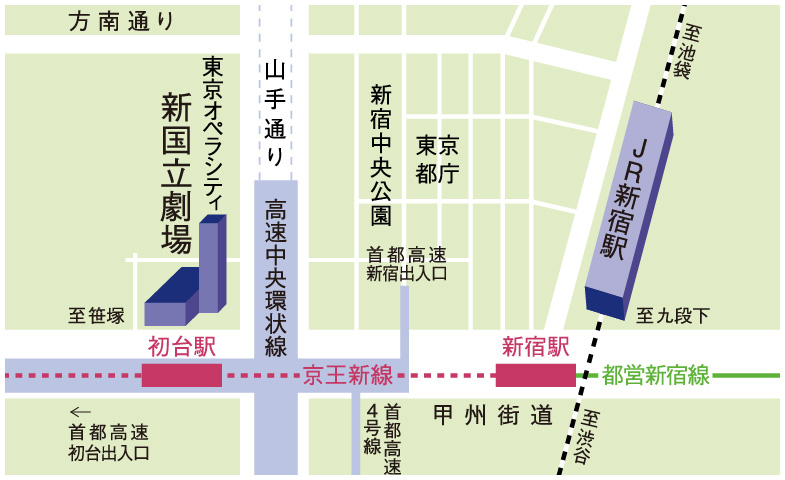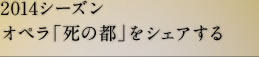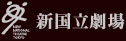2014年3月24日
プログラム訂正のお知らせ
下記の通り、「死の都」プログラムに誤植がありました。お詫びして訂正いたします。
15ページ 4段落目 4行目(ウィーン初演について)
誤 パウル役をリヒャルト・タウバーが歌った。
正 パウル役をカール・アーガルト・エストヴィヒが歌った。
2014年3月18日
マリー役(黙役)、エマ・ハワードの略歴
今回の「死の都」でマリーの黙役を演じているのは、イギリス出身のエマ・ハワード。お問い合わせの多い、彼女の略歴をご紹介します。
ロンドン生まれ。ロンドン・マウントビュー演劇学校で学び、ナショナル・シアターなどの舞台、テレビで活躍。その後日本に拠点を移し、映画「ジャッジ!」「ハゲタカ」、NHK「生きたい たすけたい」「負けて、勝つ」「英語であそぼ」など、テレビ、CM、映画、ナレーションと幅広い分野で活躍している。
2014年2月13日
2/23(日)開催「死の都」オペラトーク演奏曲目決定! USTREAM配信も行います。
今シーズンの大きな話題作「死の都」の上演がいよいよ迫ってきました。2月23日(日)開催予定のオペラトークにつきまして、チケットが完売しておりましたが、Ustreamでの配信を行うことになりました。「死の都」を鑑賞予定の方も、鑑賞を検討されている方もぜひご覧ください。
日時:
2月23日(日)11:30-13:00
出演:
広瀬大介(青山学院大学准教授、音楽評論)
ヤロスラフ・キズリンク(指揮)
歌唱予定楽曲:
第1幕より「マリエッタの歌」マリエッタ:増田のり子
第2幕より「ピエロの歌」フリッツ:萩原 潤
配信チャンネル
http://www.ustream.tv/channel/dietotestadt
※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
2014年2月10日
演出家カスパー・ホルテン インタビュー

新制作「死の都」を演出するのは、英国ロイヤルオペラのオペラ部門のディレクターであり、気鋭の演出家として世界各地で活躍するカスパー・ホルテン。
美しく幻想的な舞台に、ホルテン独自の解釈が光るプロダクションについて、そして自身のキャリアについて大いに語る。
「死の都」は20世紀のオペラの最高傑作のひとつ
――ホルテンさんとオペラ「死の都」との出会いについて教えてください。
ホルテン(以下H) 実のところ、フィンランド国立歌劇場から「死の都」の演出の話をいただくまで、このオペラについてはそれほど詳しく知らなかったのです。でも作品を聴いてみて、たちまち魅了されました。コルンゴルトの音楽は、リヒャルト・シュトラウスやワーグナーなどの後期ロマン派音楽と20世紀のハリウッド映画の間に位置し、とても親しみやすく、身振りの大きな表現をもち、初めて聴く方もすぐに引き込まれるに違いません。さらに聴けば聴くほど、見事なオーケストレーションなど、様々な発見があることでしょう。私自身は、20世紀のオペラの最高傑作のひとつだと考えています。
――今回のプロダクションは2010年にフィンランド国立歌劇場で上演されたものですが、演出にあたって何を出発点とされましたか?
H このオペラについて調べる中で、ひとつ気になった点がありました。主人公のパウルは妻を亡くし、そのことから立ち直れず、精神的に病んでしまっているわけですが、彼がオペラの中で妻のことをまだ生きているかのように延々と語るのを聞くとややうんざりしてしまうのではないか、という点です。その上、最後で「夢でした」と言われると、聴衆はパウルにあまり共感できないのではないか、と。そこでかなり早い段階から、私は外部の視点からパウルを見るのではなく、彼自身の視点から世の中を見る設定にしたいと思いました。すなわち、彼が精神を病んでいるのではなく、周りがおかしいのだと。そのため、この演出ではパウルの亡き妻マリーを舞台に登場させ、女優に演じてもらうことにしました。マリーはパウル(と聴衆)にしか見えず、他の登場人物には見えません。パウルの〈現実〉では、マリーはまだ生きていて、彼は彼女に話しかけ、笑いかけ、寝食を共にしているわけです。
たとえば新しい恋人のマリエッタが第1幕で歌う有名なアリアの場面でも、パウルとマリーは聴きながらそっと見つめ合うのです。でもマリエッタはその三角関係には気づきません。ようやく第3幕でマリエッタは、パウルにとってマリーはまだ死んでいないことに気づき、その時に2人の女性の間で対決が起きるのです。
――全幕を通して単一のセットですが、ブラインドや照明を巧みに使って、パウルの家と“死の都”と呼ばれるブルージュの街の両方を描き出していますね。
H 基本の舞台はパウルの家の中の、妻の遺品が所狭しと飾られている“思い出の部屋”です。セットは、ロンドン・オリンピックの開会式のセットも担当したエス・デヴリンによる壮麗なデザインです。さらに死の都ブルージュの街を反映させるべく、部屋の外に街をパノラマ風に浮かび上がらせました。ブルージュの街並みはグーグル・マップから発展させたものです。最新のデジタル・テクノロジーも取り入れているわけです(笑)。
窓のブラインドを開けると街が見えるようになっており、街が舞台の第2幕ではブラインドは完全に開けられ、街がパウルの部屋に侵入してくる形にしました。すなわち、自分の世界の中に引きこもろうとしても、完全にシャットアウトすることはできないということを表現したかったのです。
――照明もそうしたパウルの心理を浮かび上がらせているようで、印象的でした。
H はい、オペラ全体を通じてパウルの頭の中、彼の心理状態に光を当てようとしました。それこそがオペラの醍醐味だと思うんです。私はオペラとは、世界を表面からではなく内側から見た時にどう感じられるか、ということを表現できる芸術だと考えています。内側から見ることで世の中はもっと奥深く、複雑で、困難で、あるいは刺激的かということがわかり、オペラはそうしたことを表現する言語をわれわれに与えてくれるのです。
私の演出のなかで、もっとも誇りに思う作品です
――ホルテンさんは9歳で初めてオペラを見て以来、オペラの魅力にとりつかれたと聞いていますが、何に惹かれたのでしょうか。
H 私は銀行家一家に生まれ、両親は文化への関心はありましたが、音楽やオペラの専門的な知識はまったくありませんでした。テレビがない家庭に育ったことが大きかったのかもしれませんが、8歳の時に両親と初めて演劇を観にいった時に、物語をこんな形で舞台に実現できるということに強い衝撃を受けました。その後、オペラというものがあるらしいということを知り、両親にオペラに連れていってほしいと頼みました。それが9歳の時に観た「カルメン」です。
今思えば、9歳の自分がオペラのどこに惹かれたのかはっきりしませんが、あらゆる芸術形態――音楽、ドラマ、演劇、詩、美術など――が一体となっている点が強い魅力だったように思います。
――その後、どのような道を経て、オペラの演出家になったのでしょうか。
H 1990年代、デンマークでは小さなオペラ・カンパニーがたくさん活動していたのですが、国内で演出ができる人が少なかったので、早くからさまざまな機会を得ました。ちょうど20年前、20歳の時にマイケル・ナイマンのオペラを演出したのが私の演出家デビューでした。それと並行して、デンマーク王立歌劇場で多くのすぐれた演出家のアシスタントを務め、彼らがどのように仕事をしているかを実地で学びました。
23歳の時、オーフス・サマー・オペラのディレクターになった頃から、オペラ・カンパニーの運営にも興味を持つようになり、26歳でデンマーク王立歌劇場の芸術監督に就任しました。最初の仕事が新しい歌劇場の建設と〈リング・ツィクルス〉の演出で、忘れられない体験となりました。2011年からは英国ロイヤル・オペラのディレクター・オヴ・オペラを務め、また演出家としても活動を続けています。昨シーズンはロイヤル・オペラで「エフゲニー・オネーギン」、アン・デア・ウィーン劇場でベルリオーズの「ベアトリスとベネディクト」を新演出しました。
――最後に、今回「死の都」初めて観るオペラ・ファンにメッセージをお願いします。
H このオペラは少し前まではめったに上演されなかったのに、最近とみに人気が高まり、各地で取り上げられています。私がフィンランドで演出した時が「死の都」の同国初演で、ほとんどの人がこの作品を知らなかったんです。ところが上演してみたら、誰もがすっかり夢中になり、2013年秋には再演されることになりました。ですので、日本の皆さんもきっとその虜になると思います。特にリヒャルト・シュトラウスなど後期ロマン派の音楽がお好きな人は、魅了されること間違いなしです。
私はこれまで60作以上のオペラの演出をしていますが、この「死の都」の演出は私がもっとも誇りに思っている作品のひとつです。
――ホルテンさんの自信作とのことでますます期待が高まります。本日はありがとうございました。
インタビュアー:後藤菜穂子(音楽ライター)
<ジ・アトレ9月号より>
2014年1月15日
「死の都」の舞台 ブルージュ紀行
text by 後藤菜穂子(音楽ライター)
コルンゴルトのオペラ《死の都》の原作であるローデンバックの短編小説『死都ブルージュ Bruges-la-morte』(1892年刊)では、土地と物語がきわめて密接に展開していく。作者自身、前書きにおいて「ブルージュの街はまるで人間のようだ...街はそこに住むすべての人に強い影響を及ぼす」と述べており、読者にもこの街の持つ影響力を感じてもらおうと、初版ではブルージュの街並みの写真が文中に挿入された。まるで街自体も小説のキャラクターの一人であるかのようだ。
現在のブルージュはフランドル地方有数の風光明媚な観光地として生まれ変わっており、ローデンバックが描いたような、衰退をたどっていた19世紀のブルージュの寂寞とした暗さはない。それでも小説に登場する名所や街並の多くは今も往時の姿をとどめている。ここでは原作およびオペラの中で重要な役割を果たすブルージュの名所をたどってみよう。
1.運河とローゼンフッド河岸
ブルージュはしばしば〈北方のヴェニス〉とも呼ばれるように、運河の街として有名である。実はブルージュがもっとも繁栄した13~14世紀には街の北部に港があり、そことの間に運河が整備され、活発な交易が行われていた。しかし15世紀以降、港が徐々に沈泥でふさがれてしまい、運河も海から切り離されていき、ブルージュは貿易港としての地位を失って衰退していった。ローデンバックの描く「死都」とはそうしたブルージュなのだ。
小説の主人公ユーグ(オペラではパウル)が、妻マリーの死後、ブルージュに居を定めたのはそうした街の陰鬱な雰囲気が、自分の心の癒えない悲しみに合っていたからであった。彼は街の中心地のローゼンフッド河岸の邸宅に住み、夕暮れになると人気の少ない運河沿いを散策するのを日課としていた。そうした散策中のある日、亡き妻マリーに生き写しの女性ジェイン(オペラではマリエッタ)を初めて見かけ、たちまち彼女に夢中になるのである(オペラではマリエッタに出会った直後からストーリーが始まる)。
現在のローゼンフッド河岸はお店やレストランが並び、遊覧ボートの乗り場もあり、観光客でにぎわっているが、中心を少し離れた運河沿いの通りには、小説のままの静かな街並が残っている。
2.ブルージュの鐘
ブルージュの中心部には大きな教会がそびえ立ち、それらは小説の中にも登場する。たとえば散歩の途中に主人公ユーグが好んで立ち寄る聖母教会は13世紀から15世紀にかけて建てられ、高さ122メートルの尖塔が街並を見下ろす。またゴシック様式の救世主大聖堂はブルージュ最古の教会だが、高さ100メートルの塔は 19世紀に増築されたものである。ユーグはこうした塔から鐘が鳴り響くたびに、亡き妻マリーの葬式を思い出し、ますます鬱々とした気分にひたっていく。
コルンゴルトはこれらの鐘の音をオペラ《死の都》の中でも効果的に取り入れている。とりわけ印象的なのは、パウルにとって鐘の響きが亡き妻マリーを思い出させるものから、マリエッタに恋してしまった自分の罪をとがめる鐘へと変化していく場面だ。第2幕第1場のモノローグにおいて、パウルはマリエッタの家の前にたたずみながら、聴こえてくる鐘の音に、「妻を葬った時も 鐘はこんな風に泣いた/その響きがいまも この身を戒める/鐘よ わが罪の告白を赦し給え」と歌う。
3.〈聖血の行列〉
毎年5月のキリスト昇天祭の日に行なわれる〈聖血の行列〉はブルージュの伝統行事であり、12世紀の第二次十字軍遠征に参加したフランドル伯爵が持ち帰ったという聖血(キリストの血)に由来する。この聖血は通常、ブルグ広場にある聖血礼拝堂に奉納されているが、年に一回、聖遺物箱に入れられ街をパレードする。行列には聖職者を始め、十字軍の騎士など中世の装束に身を包んだ市民や子供たちが参加し、聖血礼拝堂を出発点とするルートを練り歩く。
そしてこの〈聖血の行列〉は小説およびオペラのクライマックス・シーンにおいて鮮やかな背景を形作っている。パウルの家で展開するオペラの第3幕はまさに昇天祭の日という設定で、マリエッタがマリーと対決する第1場でもパウルと口論になる第2場でも、外ではこの行列がにぎやかに繰り広げられている。最初は子供たちの行進、続いて中世の衣装をまとった人々、そして聖職者らが窓の外を行進する様子が合唱によって歌われる。
このように、コルンゴルトは原作において丹念に描きこまれているブルージュの風景をオペラでも見事に音楽化している。今回の演出全体におけるブルージュの描かれ方とともに、ぜひこうした音楽面での工夫にも注目しながら聴いていただければと思う。
2013年12月27日
第10回(最終回)
「忘れられた」コルンゴルトと再評価
text by 中村伸子
終戦の翌年。49歳になったコルンゴルトは、芸術音楽への完全な復帰を決意してワーナー・ブラザーズとの契約の更新を断り、ウィーンへ帰る準備を始めます。帰還に合わせて新しく《弦楽合奏のための交響的セレナーデ》Op.39(1948)を作曲し、これは、かのフルトヴェングラーの指揮でウィーン・フィルハーモニー管弦楽団により初演されることが決まります。他にも《カトリーン》のウィーン初演や《死の都》の再演が計画されました。
そして1949年、コルンゴルトはおよそ10年ぶりに故郷ウィーンの土を踏みます。ところが、彼の目に映ったのは、変わり果てた街の姿でした。彼の作品を上演し続けたウィーン国立歌劇場は瓦礫と化し、街全体も爆撃を受け、まさに「死の都」でした。さらに、フルトヴェングラーによる初演は、こともあろうに練習不足のため失敗に終わり、《カトリーン》の上演では客席の半分も埋まらず、《死の都》に至っては上演そのものがキャンセル、というありさまでした。彼の「時代遅れ」な作風と、「映画音楽作曲家」という肩書きが、ウィーンでは評価されなくなっていたのです。コルンゴルトは妻ルーツィに向かってつぶやきました。「ここにはコルンゴルトの劇場はない。私は忘れられたんだよ。」
彼は失意のうちにハリウッドに戻り、1957年11月29日、脳溢血のため亡くなりました。1962年に後を追った妻と共に、いまはハリウッド共同墓地に埋葬されています。
その後、コルンゴルトの作品は、細々とは演奏されましたが、かつてのような熱狂的な支持を受けることはありませんでした。しかし、コルンゴルトを再評価しようという動きは、1970年代からアメリカの映画音楽界を発端としてヨーロッパに波及し、次第に高まっていきます。《死の都》に関して挙げるだけでも、ニューヨーク・シティ・オペラによる復活上演(1975)、ルネ・コロらの歌とエーリヒ・ラインスドルフ指揮による録音(1975)、そしてゲッツ・フリードリヒの演出によるベルリン・ドイツ・オペラでの上演と映像収録(1983)、と続きます。ジャン・レイサム=ケーニック指揮によるストラスブールでの上演(2001、フランス初演)は、つい最近まで、日本語字幕付きで観ることのできる唯一のDVDでした。ここでパウル役を歌っているのが、他でもない、今回新国立劇場に登場するトルステン・ケールです。
マリエッタ(マリー)役のアンゲラ・デノケとのペアは、ザルツブルク音楽祭でのウィリー・デッカーの演出による上演(2004)の際にも演じています。このプロダクションはさらに、ウィーン(2004、2008、2009)、アムステルダム(2005、オランダ初演)、バルセロナ(2006)、サンフランシスコ(2008)、ロンドン(2009、イギリス舞台初演)、パリ(2009)、マドリッド(2010)、ビルバオ(2012)と、世界各地を回りました。2013年には、それぞれまったく異なる演出で、インスブルック、ホーフ、リューベック、そしてヘルシンキ(新国立劇場共同制作)で上演されており、いまや《死の都》は、一年のうちにはどこかで必ず出会えるスタンダードな演目となりつつあります。
日本でのコルンゴルト受容は、実は戦前からありました。明治~昭和期のレコード批評家である野村あらえびす(野村胡堂)の著作『名曲決定版』(1939)には、ハイフェッツの演奏によるコルンゴルトの《空騒ぎ》Op.11について記述されています。戦後しばらくは取り上げられにくい時期が続きましたが、1996年の井上道義指揮による演奏会形式での《死の都》日本初演など、少しずつプログラムに組み込まれるようになり、今に至ります。
そうした中での、満を持して、とも言うべき新国立劇場への《死の都》初登場。大きな期待を寄せずにはいられません。
2013年12月20日
舞台スタッフが一足早くご紹介!「死の都」舞台美術のここが凄い!
3月に上演するオペラ「死の都」のプロダクションは、フィンランド国立歌劇場で初演されたものです。去る11月フィンランド国立歌劇場で「死の都」の再演が行われ、新国立劇場の舞台スタッフが打ち合わせのためヘルシンキに行ってきました。そのスタッフが見てきた「死の都」舞台美術の注目ポイントをご紹介します!
1.ブルージュの街
「死の都」はベルギーの古都ブルージュのこと。舞台セットの奥の背景にもブルージュの街が登場します。これは街の写真の上に、立体型の建物をのせた作りとなっており、2Dと3Dがミックスされた非常に凝ったもの。オペラのもうひとつの主役であるブルージュの街が、照明効果もあわさって非常に効果的に描かれます。
主人公パウルの部屋には、亡き妻マリーの思い出の品々――額縁に入った写真や遺品の入ったミニチュアハウスが飾られています。その数なんと数百個!飾る位置はすべて決められており、番号で照らし合わせて並べられています。そのうちいくつかは照明が灯され、実に美しくノスタルジックな雰囲気を作り出します。
3.マリエッタのドレスの色
パウルが魅了される踊り子マリエッタが着ているドレスは、目に鮮やかな赤色。この赤ですが、舞台上で鮮やかに際立つシルクの赤色なのだそうです。官能、エロス、生の象徴であるマリエッタ。こだわりの赤で、それを見事に現しているといえるでしょう。
4.細部にまでこだわった衣裳
「死の都」では合唱は3幕前半にしか登場しないのですが、その行進の人々の衣裳にシルク・シャンタンという高級な生地が使われています。しかも同じように見える衣裳にも2種デザインがあるなど、細部にまで衣裳デザイナーのこだわりが見て取れます。
この「死の都」の美術、衣裳を手掛けたのは、世界的に売れっ子の英国の女性デザイナーたち。美術デザイナーのエス・デヴリンは、英国のオペラ、演劇、ウエストエンドなどで活躍するほか、レディー・ガガの2009/2010年コンサートツアーや、2012?年ロンドン・オリンピックの閉会式も手掛けています。衣裳デザイナーのカトリーナ・リンゼイも、英国、アメリカで活躍するトップクラスのデザイナーで、2008年にはトニー賞も受賞しています。
「死の都」は舞台美術にも注目です!
2013年12月12日
連載コラム第9回
ハリウッド映画音楽の祖コルンゴルト
text by 中村伸子
日本では最も有名なコルンゴルト作品のひとつであるヴァイオリン協奏曲Op.35(ハイフェッツにより初演)は、その壮大な旋律や楽器法から、「まるで映画音楽みたいな曲!」と言われることがままあります。しかしながら、実はこれは映画音楽みたいなのではなく、映画音楽そのものなのです。
というのも、終戦直後に完成されたこの協奏曲は、『放浪の王子』(1937)を始めとする4つのハリウッド映画のために彼自身が作った主題を、ふんだんに引用して書かれているからです。コルンゴルトはこれに限らず、弦楽四重奏曲第3番Op.34(1945)やチェロ協奏曲Op.37(1946)などのように、映画音楽のために書いた音楽を新しい自作品の中で積極的に「再利用」しました。現代のようにDVDやサウンド・トラックのCDが売られることのなかった時代ですから、映画音楽は公開を終えるとほとんど聴くことができなくなります。それを防ぐために、コルンゴルトは映画音楽をクラシック作品の中に取り込み、恒久的に残そうとしたのです。
では、コルンゴルトはどのような経緯で映画音楽に関わるようになったのでしょうか。鍵となる人物は、ドイツの演出家マックス・ラインハルトです。彼とコルンゴルトは、1920年代前半から、ウィーンやベルリンでシュトラウス一家のオペレッタなどを上演するときに、ラインハルトは演出、コルンゴルトは編曲、という形で、しばしば一緒に仕事をしていました。しかし、ラインハルトもユダヤ人で亡命を余儀なくされ、コルンゴルトよりも一足先にアメリカに渡って活動を続けます。そこで、ラインハルトがシェイクスピアの『夏の夜の夢』の映画化をするときに、メンデルスゾーンの音楽の編曲者と収録の指揮者として、コルンゴルトを呼び寄せた、というわけです。
コルンゴルトはオペラ作曲家としての経験と才能を惜しみなく発揮しました。全編143分中116分に音楽が流れており、《夏の夜の夢》だけではなく交響曲第3番《スコットランド》や第4番《イタリア》など、いくつものメンデルスゾーン作品のテーマが取り入れられました。彼はさらに撮影現場に立ち入り、自らの指揮に合わせて俳優に台詞を喋らせ、後日その台詞に合わせて音楽を収録する、という他に例のない方法を取りました。数々の工夫の成果が実り、映画の音楽と映像は見事なほどにシンクロしています。もともとの6週間という予定をゆうに超えた半年を費やして制作されたこの映画は、1935年にアメリカで公開され、大ヒットとなりました。
その後、1935年の『海賊ブラッド』以降、コルンゴルトはワーナー・ブラザーズのもとで、約20本の映画音楽を担当しました。『風雲児アドヴァース』(1936)と『ロビン・フッドの冒険』(1938)ではアカデミー音楽賞を受賞しています。彼がもたらした書法は、ジョン・ウィリアムズを始めとする後のハリウッドの映画音楽にいまも生きています。ごく一例にすぎませんが、映画『嵐の青春』(1941)のテーマの冒頭は、『スター・ウォーズ』(1977~)のテーマにそっくりです。
こうして、コルンゴルトが映画音楽に追随したのではなく、映画音楽がコルンゴルトに追随したのだということをお分かりいただけるでしょう。現在でも、彼の携わった映画はいくつも観ることができます。もととなった映画をご覧になってからヴァイオリン協奏曲をお聴きいただくと、より一層興味深く感じられることと思います。
2013年12月4日
連載コラム第8回
ナチスを逃れた音楽家たち
text by 中村伸子
《死の都》の作曲から、時は10年ほど進みます。コルンゴルトはルーツィ・フォン・ゾンネンタールと結婚して2人の息子に恵まれました。家庭を持った彼は、さらに仕事に励みます。しかしながら、彼を待ち受けていたのは大きな荒波でした。ユダヤ人迫害の問題です。
反ユダヤ主義は、それまで存在しなかったわけでは決してないのですが、1930年代から急激に進み、コルンゴルトもその影響を強く受けるようになります。当時彼は、ちょうど5作目のオペラを構想しているところでした。ユダヤ系の作家H.E.ヤーコプの小説を原作とした、ドイツ人の娘とフランス兵士の恋物語です。コルンゴルトは、それまで彼のほとんどの楽譜を世に出してきたショット社にこの出版を持ちかけたのですが、こともあろうに拒否されてしまいました。反ユダヤ感情が高まり、ユダヤ系の芸術家の活動が次々と妨げられている状況で、ユダヤ系作家の原作によるユダヤ系作曲家のオペラなど、出版できるはずがない、というのです。このオペラは《カトリーン》Op. 28というタイトルで1937年に完成されますが、ウィーンの舞台で日の目を見るのは、終戦後の1950年まで持ち越されてしまいました。
1933年1月ヒトラー率いるナチス・ドイツが政権をとり、3月には全権委任法が通過すると、コルンゴルト作品の大事な上演の場であったドイツは「第三帝国」となりました。さらに4月に「職業官吏再建法」が成立すると、ドイツで活動するユダヤ人は次々に職を追われ、音楽家も、歌劇場や音楽大学などの公的な役職を奪われました。さらにはユダヤ人作曲家による作品の演奏までも禁止され、コルンゴルトやマーラーどころではなくメンデルスゾーンの音楽まで、ドイツでは聴くことができなくなります。その勢力は留まることを知らず、1938年にナチスがオーストリアを併合すると、オーストリア国内もドイツと同じ状況になります。1934年以来すでにハリウッドとウィーンを数度行き来していたコルンゴルトは、併合以降ハリウッドに留まり、映画音楽作曲家として腰を据えることになるのです。
コルンゴルトと同じようにオーストリアやドイツからアメリカへ亡命したユダヤ系の音楽家は、実に数多くいました。アメリカ西海岸へ渡っただけでも、オットー・クレンペラー、ブルーノ・ワルター、マーラーの妻アルマ、シェーンベルク、ハンス・アイスラー、第一次大戦で右手を失ったピアニストのパウル・ヴィトゲンシュタインなどです。コルンゴルトとシェーンベルクは、その主義と作風の違いや、コルンゴルトの父ユリウスがシェーンベルクの音楽を嫌っていたことなどから、ウィーン時代はほとんど交流がありませんでしたが、ロサンゼルスでは互いの家を訪ね合う仲になります。このころのシェーンベルクの妻ゲルトルーデは、コルンゴルトの幼なじみでもありました。(余談ですが、シェーンベルクの最初の妻は、コルンゴルトの師ツェムリンスキーの妹でした。)コルンゴルトは、シェーンベルクの《6つのピアノ小品》Op.19(1911)を讃えて、本人を前に暗譜で弾いて聴かせたこともあったようです。
ウィーンにいる間は宗教曲をほとんど書かなかったコルンゴルトですが、ロサンゼルスではユダヤ教のための音楽を2曲だけ残しました。《過越の詩篇》Op.30と《祈り》Op.32です。どちらも、ロサンゼルスのユダヤ教のラビであったJ.ゾンダーリングに委嘱されました。彼の委嘱で書かれた作品は他に、シェーンベルクの《コル・ニドレー》Op.39などがあります。
2013年11月26日
連載コラム第7回
《死の都》を上演した音楽家たち
text by 中村伸子
1920年12月の初演から今日まで、《死の都》を上演した音楽家の中には、現在の私たちもよく知る名手がたくさんいます。今回は、コルンゴルトの生きた時代に《死の都》を歌ったり指揮をしたりした往年の音楽家たちを見ていきましょう。
<歌手>
マリエッタ(マリー)とパウルの二人の主役は舞台に上がり通しで、休む暇がほとんどありません。ワーグナーの長時間のオペラを余裕で歌いこなせるくらい、ともすればそれ以上の声帯、体力、そして音域の持ち主でなければ、歌い切るのは難しいようです。さらにマリエッタ役については、貞淑で上品な亡きマリーと奔放で野卑なマリエッタとを、一人二役で演じ分けるのも大変です。この役を演じた歌手でまず外すことができないのは、マリア・イェリッツァでしょう。彼女はロッテ・レーマンと並ぶ当時のウィーンの人気ソプラノで、コルンゴルトの前作の一幕オペラ《ヴィオランタ》の初演でタイトル・ロールを歌っていました。《死の都》ではウィーン初演で演じ、ウィーンでは「演技の面でも歌の面でも卓越している」などと絶賛されています。コルンゴルトは彼女を「ミッツィ」と呼んで慕いました。
《死の都》は、1921年11月にはニューヨークのメトロポリタン歌劇場(MET)にかかります。これは、イェリッツァが、自身のMETデビューのための演目として《死の都》を選んだためです。METでは、1917年以来、オペラを敵国ドイツの言葉で歌うことが禁止されていたことから、《死の都》は第一次大戦後にMETでドイツ語上演された最初のオペラとなりました。この公演は圧倒的な成功とまではいきませんでしたが、コルンゴルトの若き才能はニューヨークの音楽界にも深く印象付けられたことでしょう。イェリッツァもユダヤ系だったため、後にアメリカに亡命しました。コルンゴルトが1947年に完成させた彼最後の歌曲集《5つの歌》Op. 38は、「マリア・イェリッツァ=シアリ、かけがえのないヴィオランタとマリエッタに友情と尊敬を込めて」献呈されています。
ロッテ・レーマンもマリエッタ役を歌っています。彼女はコルンゴルトの次のオペラ《ヘリアーネの奇跡》(1927)でヘリアーネ役を初演しました。実は、コルンゴルトにとってはイェリッツァの声の方が好みで、ヘリアーネ役を書く際はイェリッツァを想定していたようです。とはいえ、彼とレーマンも後年まで良好な関係を築きます。
パウル役では、ハンブルク初演やウィーン初演で歌ったカール・アーガールト・エストヴィヒ以上に、リヒャルト・タウバーがその「悪魔のような音楽性」で観客を魅了しました。コルンゴルトは、オペラ《カトリーン》(1937)のフランス兵フランソワ役を、彼を念頭に置いて書いています。また、〈ピエロの歌〉が最大の見せ場であるフリッツ役では、リヒャルト・マイヤーが人気を博し、ウィーン初演の際には「小さな歌を一つ歌っただけだが、大いに魅了させた」と評されました。
<指揮者>
《死の都》はヨーロッパ各地の歌劇場で上演されたので、当然のことながら数多くの指揮者がこのオペラのタクトを取りました。現在の私たちにも耳馴染みのあるマエストロの名前を挙げると、オットー・クレンペラー、フランツ・シャルク、ハンス・クナッパーツブッシュ、ツェムリンスキー、ジョージ・セルと、実に錚々たる顔ぶれです。クレンペラーはケルンでの初演を指揮し、マリエッタを歌ったのは彼の妻ヨハンナでした。ところが、クレンペラーは作品を評価せず、カーテン・コールには姿を現さなかったそうです。コルンゴルトと同い年のセルは、1924年のベルリン初演後、ロッテ・レーマンとリヒャルト・タウバーと共に《死の都》のうち数曲を録音しています。コルンゴルト立ち会いのもとで録られたこの音源は、現在でも聴くことのできる貴重な資料の一つです。


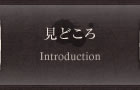
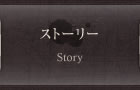



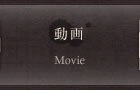
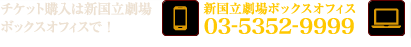
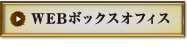








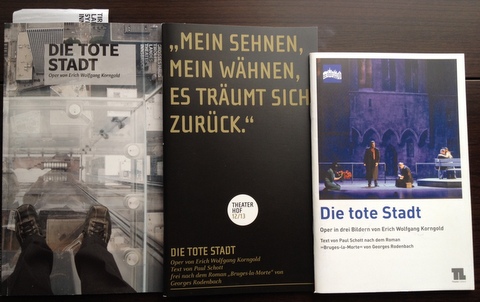



ポスター-195x300.jpg)
ポスター-186x300.jpg)
ポスター-200x300.jpg)