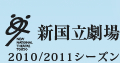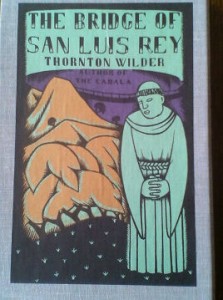第10回 三分間劇集『癒しの池、天使がさざ波立てるとき』 の序文
2011年 01月 12日|水谷 八也
水曜ワイルダー約1000字劇場、プロンプターの水谷です。もう今週が初日! ドキドキしてきますねぇ。
さて、ワイルダーは演劇をこの世界とそれを超える次元とを結ぶ回路だと考えていたようだ、ということを前回書きました。彼の演劇観は『三戯曲集』の序文(1957)に一番良く出ていますが、もうひとつ、彼の演劇観を知る上で重要なものが、今回、演劇講座でも紹介する「三分間劇」です。これは1925年、彼がオベリン大学の学生だった頃から、大学の文芸誌に投稿していたもので、登場人物が三人、上演時間(必ずしも上演を念頭に置いてないのですが)が三分という枠を自分に課していた時期のものです。ワイルダーはイェール大学進学後も、ローレンスヴィル高校のフランス語教員時代にも、この形式の戯曲を書き続け、1928年に初の戯曲集『癒しの池――天使がさざ波立てるとき』として出版しました。
この奇妙な戯曲集には16編の三分間劇が収められており、その大半が「死」や「宗教」を扱ったものです。この凝縮された個々の戯曲の内容も読み応えがあるのですが、冒頭に付された序文は注目に価します。
この序文の中で、ワイルダーは「偉大な宗教的テーマに見合うだけの精神を、それもお堅い教訓に陥ることのない精神を発見したかった」と書いています。彼は宗教を、(外から強制を加える)教訓としてではなく、内発的なものとしてとらえていて、「美」が唯一の説得力を持つものだ、と熱弁をふるってます。そして最後の部分で「宗教の復興は、ほとんどレトリックの問題だ。その作業は困難で、多分不可能だろう。しかしそれで思い起こすのは、神が聖書の中で《鳩のように柔和であるだけでなく、蛇のように賢くあれ》と勧めていることである」としめくくっています。
ワイルダーは最初の戯曲集で、20世紀という非・宗教的な時代に、あえて宗教的作家を目指すのだと、宣言しているわけです。ワイルダーが28年にこの文章を書いて以来、20世紀がどんな時代だったか、どれほど超・人間中心主義だったか、わたしたちはすでに知っています。
ワイルダーは明らかにその時代の流れに逆行しています。彼の初の小説『カバラ』や『サン・ルイス・レイの橋』でも、ワイルダーの姿勢は同じです。物語は人間世界のことを描いていますが、すでに見てきたように、こちら側の世界を描いて、向こう側の世界を、読者(観客)に想起させるのが彼の方法です。最終的に彼が内面に創出しようとしていたのは、こちらとむこうを結ぶ関係性でした。『サン・ルイス・レイの橋』の最後の部分は有名で、2001年9月11日のテロで亡くなったイギリス人を追悼する席で、当時のブレア首相もそこを引用しました。「存在するのは生きている者の国と死んでいる者の国だけであり、そこをつなぐ橋が愛なのだ、それこそが唯一生き残るものであり、唯一意味のあるものなのだ」という部分。ここだけ読むと陳腐な感じですが、通して最後にここを読むと、曰く言い難い空気に包まれます。それは『わが町』でも同じです。その空気を創出するのに、実験的な形式は不可欠な要素になっています。
ジャンルを問わずワイルダーの全作品に見られる形式への執拗な実験は、「蛇のような賢さ」で、非・宗教的な時代に「大いなるもの」を想起させるための方途でもあったのです。