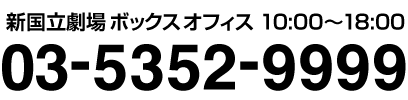タミーノ役:スティーヴ・ダヴィスリムTamino:Steve DAVISLIM

大野オペラ芸術監督による新体制がスタートする2018/2019シーズンのオペラは、世界各地で大好評のプロダクション、ケントリッジ演出『魔笛』で開幕する。タミーノを歌うのは、スティーヴ・ダヴィスリムだ。世界の名門歌劇場で活躍し、名指揮者たちと数多く共演しているダヴィスリムは、ケントリッジ演出『魔笛』もイタリアで経験済み。『魔笛』について、そして自身について語る。インタビュアー:後藤菜穂子(音楽ライター)
[ ジ・アトレ7月号より ]
ケントリッジ演出は現在の『魔笛』の中で
最高のプロダクション

© Elisabeth Carecchio - Festival d'Aix-en-Provence 2009
――今回、新国立劇場初登場になりますが、これまで日本にいらしたことはありますか?
ダヴィスリム(以下D)20年以上前に一度だけ訪れたことがあります。そのときは高松市でプライベートのコンサートに出演しました。かねてより日本の伝統文化に深い関心を持っているので、それ以来日本と縁がなくて残念に思っていたのですが、今回ケントリッジ演出の『魔笛』に出演できることになり、たいへん嬉しく楽しみにしています。
――ケントリッジ演出の『魔笛』にはヨーロッパですでにご出演されているそうですね。
Dええ、ナポリのサン・カルロ劇場(2006年)とミラノ・スカラ座(2011年)の2回出演しましたが、大好きなプロダクションです。彼はこの作品のもつさまざまな象徴性を理解していますし、ヴィジュアル面でもアイディア面でもきわめてインパクトの強い演出です。今上演されている『魔笛』のプロダクションの中でも最高のものではないでしょうか。
――南アフリカ出身のケントリッジらしく、この演出はコロニアリズム(植民地支配)がひとつのテーマとなっているそうですね。
Dたしかにケントリッジはこの作品を南アフリカとアパルトヘイトに結びつけていますが、それはほんの一面にすぎず、自身のドローイングや映像を巧みに使った多層的な演出です。たとえば、ザラストロが気高いアリア「この神聖な殿堂の中では」を歌う場面では、背景のスクリーンで象やサイを狩る人間の白黒の映像を流し、人間の偽善について問題提起するといった具合です。ただケントリッジの場合、彼はあくまでもアーティストであり政治的な活動家ではないので、自己主張のためではなく、人々に考えてもらうためにこうした演出をしているわけです。
――ダヴィスリムさんにとってタミーノはもっとも得意とされる役のひとつだと思うのですが、技術的にはどんな難しさがありますか。
Dモーツァルトの作品は本当にどれも難しいのです! モーツァルトを歌う場合、どこにも隠れるところがありません。声の調子が少しでもよくなかったらすぐに人々は気づきますし、声のコントロールが完璧でなかったらすぐにわかってしまいます。モーツァルトを歌う上では妥協はできません。でもうまく歌えたときには、自分と観客と音楽がまさに一体となれるのです。大作曲家はほかにもたくさんいますが、モーツァルトは私にとっての原点といえるでしょう。
――タミーノ以外にも、数々のモーツァルトの役を歌っていらっしゃいます。
Dモーツァルトのオペラのテノール役は、それぞれまったく違うんですよ。イドメネオはミュンヘンのテノール歌手アントン・ラーフのために書かれましたが、ラーフはすでに60代後半だったため音域が低く、また彼が得意としたコロラトゥーラが多用されています。一方、皇帝ティートはかなり高音域ですし、ミトリダーテはさらに高くハイCが出てきます。一方で、『コジ・ファン・トゥッテ』のフェルランドは第1幕では軽めのテノールですが、第2幕で恋人に裏切られたことを嘆くアリアはよりドラマティックな声が必要です。したがって役ごとに難しさが違うわけですが、それもモーツァルトの魅力のうちです。
熟成してきた声
今、最も良い状態を迎えています

© Elisabeth Carecchio - Festival d'Aix-en-Provence 2009
――ダヴィスリムさんはマレーシア生まれ、オーストラリア育ちだそうですが、子どもの頃から音楽に親しまれてきたのでしょうか。
Dええ、家族は音楽好きでした。アイルランド人の母方の祖母は1920年代にロンドンの王立音楽大学でオルガンを学んだという先駆的な女性で、オルガニストをしていました。また祖父はアマチュア演劇に携わっていました。そうした影響が私にきっと流れ込んだのでしょう。
歌うことは好きで学校や教会で歌っていましたが、8歳のときにホルンを始め、最初はホルン奏者になろうと思って音大に進みました。ただホルンのためのレパートリーをひと通りマスターしたときに、40歳になったら何をするんだろうと考えてしまって(笑)。そんなときに歌のレッスンを受けてみたらとアドバイスしてくれた友人がいて、やがて声楽に転向したのです。オペラにしても歌曲にしてもレパートリーは無尽蔵ですからね。
――その後渡欧され、チューリヒのオペラスタジオで研鑽を積まれました。
Dそうです。当初アテネでギリシャ人の先生についていたのですが、その縁でチューリヒのオペラスタジオのオーディションを受け、採用されました。その後、1994年より同歌劇場のアンサンブル・メンバーになりました。当時はフレーニやギャウロフが現役で舞台に立っていた時代で、こうした大歌手から多くのことを学びました。
――アーノンクールともずいぶん共演されましたね。
Dアーノンクールは私がまだ23、4歳のときに私をザルツブルク音楽祭に起用してくれました。たしかに早すぎた感はありますが、それを機に多くの指揮者が私をコンサート歌手として起用してくれたことは私のキャリアにとって幸いなことでした。さらに大きなブレイクとなったのは、1998年にロイヤル・アルバート・ホールでノリントン指揮BBC交響楽団と『ミサ・ソレムニス』を歌ったことでした。
ダヴィスリムさんは、ご自分をどのようなタイプのテノールだと思っていらっしゃいますか?
Dけっこうカメレオンなんですよ。私の声の特質については、指揮者によって違う面を評価していただいてきたので、どんなタイプと言われても困ってしまいます。現在では歌手のレパートリーの専門化が進んでいますが――特にバロック音楽の復興以降――1970年代、80年代までは歌手はバッハからシュトラウスまで幅広いレパートリーを歌っていました。私自身、今でもバッハも歌いますし、つい最近作曲された現代の音楽も歌うので、どちらかといえばそのタイプだと考えています。
――ご自身の声はどのように変化してきましたか? また今後歌いたい役などありますか?
Dプロとして歌い始めてから30年以上経ちますが、声も赤ワインのようなもので、徐々に熟成してきて、おそらく今ちょうどピークを迎えている気がします。多様な色彩が出せるようになりましたし、若い頃はもっと考えて歌わなければならなかったことがより容易にできるようになりました。
今後は実はオペラの演出やコンサートのプロデュースをやってみたいと思っています。私の両親は今マレーシアに住んでいるのですが、同地でオペラの演出を始めました。オペラ入門編として『魔笛』を上演したんですが、台詞の部分は英語に訳して(アリアはドイツ語)、大蛇の代わりに中国の竜を出したり、3人の侍女がパパゲーノに石を与えるところでは代わりにドリアンを与えたり(笑)と、地元ネタを入れて上演したところたいへん好評でした。それは18世紀のウィーンでシカネーダーがやっていたことであり、『魔笛』はまさに庶民のオペラなのです。
――最後に日本のみなさんにメッセージをお願いします。
D『魔笛』というオペラは、子どもや初心者も楽しめますし、一方で何度も観たオペラ・ファンにとってもさらに高いレヴェルで理解できる奥の深い作品です。とりわけケントリッジの演出は、この作品の示唆をさまざまな角度から掘り下げた独創的なプロダクションなので、ぜひ日本のみなさんにも体験していただきたいです。
BUY TICKETS
チケットの購入
お電話のお求め
- チケットぴあ
- 0570-02-9999(Pコード106-121)
- ローソンチケット
-
0570-000-407(オペレータ受付)
0570-084-003(Lコード38230)
JTB・近畿日本ツーリスト・日本旅行・東武トップツアーズほか
グループでのお申し込み
10名以上でご観劇の場合は新国立劇場営業部(TEL 03-5352-5745)までお問い合わせ下さい。