現代戯曲研究会
座談会 連続3回掲載その(1)
いま、同時代演劇とは?
小田島恒志 佐藤 康 新野守広 平川大作 鵜山 仁(進行)
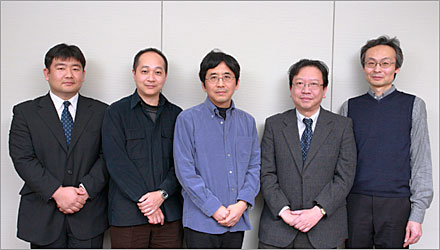
鵜山●「シリーズ・同時代【海外編】」の三作品連続上演の機会に、これまで「研究」を積み重ねてきた現代戯曲研究会のメンバーのみなさんと、“いま、同時代演劇とは?”というテーマをあらためて掲げ、議論してみようと思います。
大テーマですが、まず僕から問題提起として、現代演劇史という観点から、ドイツのブレヒト以降、フランスのベケット以降、イギリスの“アングリー・ヤングメン(怒れる若者たち)”以降の、現代演劇をどうとらえればいいのか、というあたりから始めたいのですが。
佐藤●演劇史というと戯曲以外も含まれてきますよね。戯曲研究会は戯曲にスポットをあてて検討しているので、現代戯曲史という考え方でいいですか?
鵜山●そうですね、さしあたっては戯曲に焦点を当てて話しましょう。
個人的な話で恐縮ですが、丁度1968年から70年にかけて、当時高校生だった僕の周囲には、文化祭でバーバラ・ガーソンの『マクバード!』とか、福田善之さんの『袴垂れはどこだ』、別役実さんの『マッチ売りの少女』を上演しようという先鋭的な先輩たちがいました。僕自身は第二前衛的にピランデルロの『ヘンリー四世』や、安部公房の『友達』なんて作品を、主演と演出を兼ねて上演していた。
その後71年に東京に出てきて、実際の舞台に接する機会がグンと増えた。アングラ前衛劇に限らず、出口典雄さんのシェイクスピア・シアターで、小田島雄志さん訳のシェイクスピア作品が次々に上演されていた。創作劇では、つかこうへいさんの時代ですね。客席の側から見ていると、日々、舞台の上で演劇言語が解放されているというスリルがあった。ところが、それ以降、現代演劇の新しい言語が、何故か衝撃力を失くしてしまったように思います。自分が芝居の現場にかかわっちゃったのが大きな原因だとは思いますが(笑)。70年代の演劇言語の解放というのが、かえってモラルハザードを引き起こしたと言うべきなのか、演劇ジャーナリズムも含めて、演劇にかかわるさまざまな言説が70年代の後半から、にわかに鮮度を失くしてしまったという印象があります。僕の実感としては、新劇の失速というものがかなり影響しているんじゃないかと思っている。それまで営々と積み重ねてきた現代演劇のエスタブリッシュメントがなぜ急に空洞化してしまったのか、僕にとっては大きな問題です。
とにかく創造現場では、作り手と観客と批評が三位一体、それぞれの独自性をもってぶつかりあわないとほんとうに新しいものは生まれてこない。テレビやネット上にあふれかえっている情報を、ただ切り貼りするだけの教育とか、年金や保険で生き延びるだけの人生とか、病院で死ぬ身体とか、圧倒的な「公共性」を前にして「私的」な身体のアイデンティティが薄れていく。一方で、政治・経済・文化・教育、いろいろな分野で、「あるべき姿」はどんどん崩れていって、僕らは「理想」と、そしてその対極の「敵」を見失った。その両極がぶつかるダイナミズムを忘れてしまったというのが「今」の現実なんじゃないかと思う。これは実は、いつの時代にも繰り返されてきた現象なのかもしれませんが、こういう時期だからこそ、劇場の役割、演劇の現場の役割、批評の役割について根本的な議論をする必要がある。そのあたりが、そもそも昨年からの、「シリーズ・同時代」の企画を立ち上げる問題意識だったわけです。そういう観点から、ドイツでは、フランスでは、イギリスでは、というお話をしていただければと思います。
