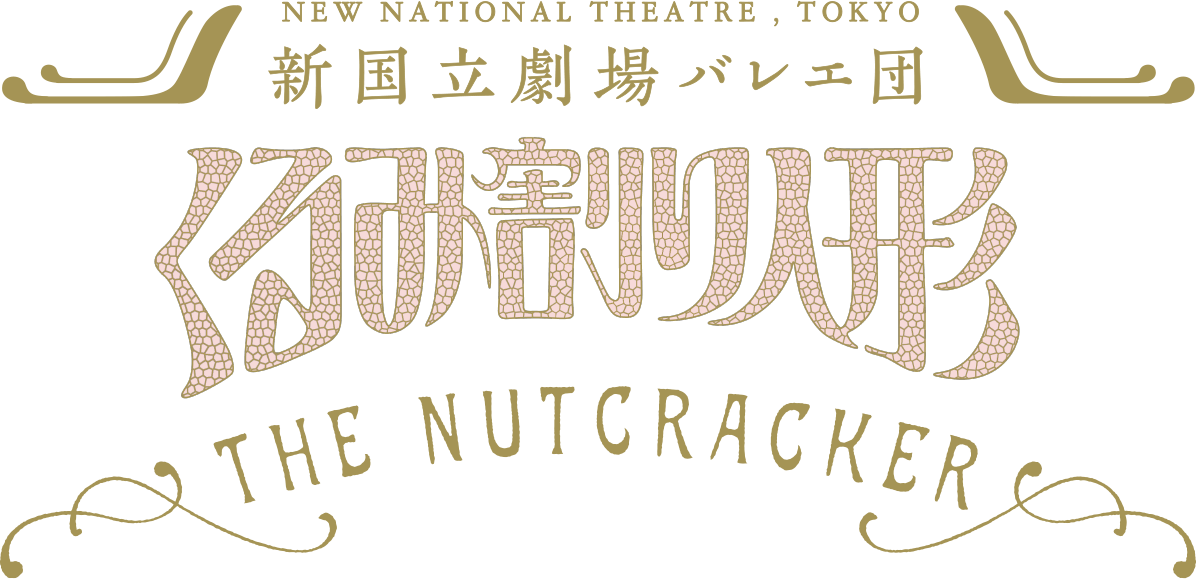コラム 〜その4〜
チャイコフスキーがかけた
『くるみ割り人形』の音の魔法

バレエ『くるみ割り人形』は、物語同様、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840~93)の音楽もファンタジーにあふれています。おとぎの世界を描き出すためにチャイコフスキーが書いた音は、『白鳥の湖』『眠れる森の美女』にはない新しさと工夫に満ちたもの。『くるみ割り人形』の響きのヒミツを、少し紐解いてみましょう。
新しい楽器・奏法による幻想的な響き
まずは、新しい楽器チェレスタの登場です。グロッケンシュピールのような音のするチェレスタは1886年にパリで開発された楽器で、チャイコフスキーは1891年にパリで見つけました。出版社に楽器購入を頼む際には、決して他人(特に作曲家リムスキー=コルサコフとグラズノフ)に知られないよう注意しており、誰も知らない音を最初に使おうとする興奮がうかがいしれます。チェレスタが使われるのはおとぎの国の場面の第2幕で、特に金平糖の精の踊りが有名ですが、ほかにも第2幕冒頭(第10曲)、金平糖の精の登場も印象的です。チェレスタにハープ2台が加わって輝きを増した響きは、まさに夢の世界。そこに笛の音のような旋律が聞こえますが、これはフルートではなく、ヴァイオリンとヴィオラによるフラジオレットという奏法の音なのでご注目を。
続いて、金平糖の精は4人の男性にエスコートされ(第11曲)、そこで「ヒュルルル」と風が吹くような音がします。これはフルートのフラッター・タンギングによる音です。当時はまだ新しい奏法で、チャイコフスキーは1891年、演奏旅行先のキエフで知り、この場面にさっそく使ったのです。チャイコフスキーもとても驚いたという音色を、ここではフルートを3本も使った充実の響きで、きらめく世界を描きます。
新しい楽器に対し、一番古い楽器とも言えるのが「声」です。第1幕、雪の精の場面(第9曲)では、なんとバレエ音楽に合唱が登場します。実は『くるみ割り人形』はオペラ『イオランタ』とのダブルビルとして計画された作品なので、合唱団が楽屋にいるから加えたのかもしれません。ヴォカリーズによる合唱は作品に斬新性をもたらし、新たな幻想性を生み出しています。子どもや人形の世界を描くためにおもちゃのラッパや太鼓などが登場するのも『くるみ割り人形』ならでは。とはいえ、『くるみ割り人形』の前に完成したオペラ『スペードの女王』でもおもちゃの楽器を使っていて、その経験を生かしたものなのでした。楽譜には"『スペードの女王』と同じ楽器を"と指示されているのも興味深い点です。
高音と低音が表すもの
『くるみ割り人形』は、音域ごとの描写も見事です。序曲で使用する楽器は、木管楽器、ホルン、トライアングル、ヴァイオリン、ヴィオラのみという、高音を意図した楽器編成です。序曲というと通常はフル編成の音楽をイメージしますが、ここでは低音を徹底的に省いて、かわいらしい音世界を作り出しているのです。逆に、ドロッセルマイヤーの登場(第4曲)はヴィオラ、トロンボーン、チューバ、それにホルンのゲシュトップ奏法(「ビーン」と鳴る音)という、低音の楽器編成で不気味に描きます。このようにチャイコフスキーは高音と低音の性格の違いを明確に使い分け、音で物語を鮮やかに表現しているのです。
繰り返す旋律から広がるイメージ
『くるみ割り人形』の旋律は、じっくり聴かせるというより、シンプルな短いフレーズを繰り返すものが多いのが特徴。
第1幕幕開けのプロローグ(第1曲)からそうで、第2幕、クララがおとぎの国に到着する音楽(第11曲)も簡単な音階を繰り返すだけ。この音階の繰り返しは金平糖の精と王子のパ・ド・ドゥの音楽へとつながります。
繰り返しの音楽の白眉は、第1幕クリスマス・ツリーが大きくなる場面です(第6曲の途中から)。何度も旋律を繰り返しながらクレッシェンドして作品中の最大音量 ffff に達します。単なる繰り返しにもかかわらず、巨大なツリーがありありと目に浮かぶ描写力に圧倒される音楽で、まさにチャイコフスキーの円熟の技と言えるでしょう。
ほかにも素敵な響きがたくさんある『くるみ割り人形』。公演ではぜひ音楽も楽しんでください。
ピョートル・チャイコフスキー作曲
くるみ割り人形 作品 71
| 序曲 | |
|---|---|
| 〈第1幕〉 | |
| 第1曲 | クリスマス・ツリーの情景 |
| 第2曲 | 行進曲 |
| 第3曲 | 子どもたちの小さなギャロップと 両親の登場 |
| 第4曲 | 踊りの情景 (ドロッセルマイヤーの登場) |
| 第5曲 | 情景とグロースファーターの踊り 第6曲 (招待客の帰宅〜真夜中の部屋) |
| 第7曲 | 情景 (兵隊人形とねずみの戦い) |
| 第8曲 | 情景(松林の踊り) |
| 第9曲 | 雪片のワルツ |
| 〈第2幕〉 | |
|---|---|
| 第10曲 | 情景(お菓子の国) |
| 第11曲 | 情景(クララと王子の登場) |
| 第12曲 | ディヴェルティスマン a チョコレート(スペインの踊り) b コーヒー(アラビアの踊り) c お茶(中国の踊り) dトレパック(ロシアの踊り) e 葦笛:ミルリトン(葦笛の踊り) f ジゴーニュおばさんとその子どもたち |
| 第13曲 | 花のワルツ |
| 第14曲 | 金平糖の精と王子のパ・ド・ドゥ アダージョ 王子のヴァリエーション 金平糖の精のヴァリエーション コーダ |
| 第15曲 | 終幕のワルツとアポテオース |
文章:榊原律子 Sakakibara Ritsuko
バレエをこよなく愛する音楽ライター。慶應義塾大学大学院文学研究科 修士課程修了(音楽学)。新国立劇場友の会情報誌「ジ・アトレ」をはじめ各 地の劇場・音楽ホール会報誌の執筆・編集、演奏会の曲目解説執筆などで 活動中。共著書に『新国立劇場名作オペラ50鑑賞入門』(世界文化社)など。
(2013年当公演プログラムより)
-
コラム 〜その1〜
-
コラム 〜その2〜
-
コラム 〜その3〜
-
コラム 〜その4〜