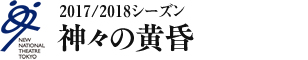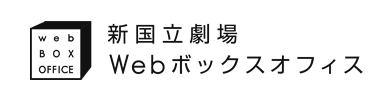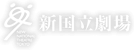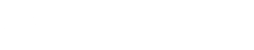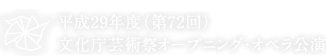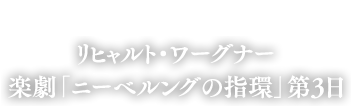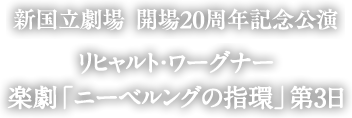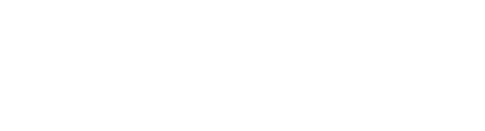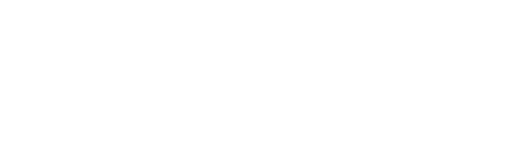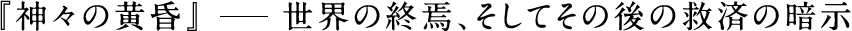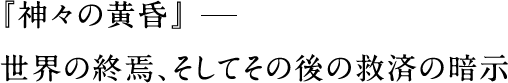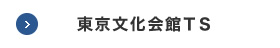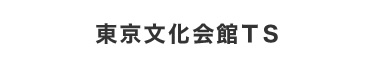- 2017.10.03 初日公演の動画を公開しました。
- 2017.10.01 「神々の黄昏」が初日を迎えました。
- 2017.09.29 「神々の黄昏」メディア掲載情報
- 2017.09.14 「飯守泰次郎の『神々の黄昏』音楽講座」を掲載しました。
- 2017.09.11 『神々の黄昏』公演時のレストランマエストロご予約を承ります。
- 2017.08.24 ブリュンヒルデ役 ペトラ・ラングのインタビューを掲載しました。
- 2017.08.03 インタビュー「 日本人歌手が語る『神々の黄昏』」を掲載しました。
- 2017.07.27 コラム 「『神々の黄昏』 ――過去を振り返り進行していく叙事的物語」を掲載しました。
- 2017.07.20 ヴァルトラウテ役 ヴァルトラウト・マイヤーのインタビューを掲載しました。
- 2017.06.15 『神々の黄昏』特設サイトオープン!
新国立劇場オペラ芸術監督 飯守泰次郎


『神々の黄昏』は、これまでの『ラインの黄金』『ワルキューレ』『ジークフリート』で種が蒔かれて発展・成長してきたすべてを刈り取る物語であり、ひとつの世界が終焉に至るさまを描いている作品です。上演時間も正味で4時間半という未曽有の規模に到達し、巨大な四部作の結末が導き出されます。
冒頭の、3人の運命の女神ノルンの場面からすでに、世界は絶望的であることが感じられます。続く「夜明けとジークフリートのラインの旅」は、コンサートでもよく演奏される場面です。その後の出来事を予感していないジークフリートとブリュンヒルデの二重唱は愛と幸せに溢れ、『神々の黄昏』におけるほとんど唯一の肯定的な音楽です。しかし、ここで二人が離れることが、取り返しのつかない運命への旅立ちとなるのです。
旅立ったジークフリートは、騙されて魔酒を飲み、ブリュンヒルデとの愛を忘れてしまいます。以降、この大作の舞台は、邪悪な陰謀、欲望、策略、欺瞞、反目、裏切り…そして復讐、殺人、破壊、といった否定的な内容で埋めつくされます。憎悪と暴力で世界を支配しようと企てたアルベリヒの息子である、ハーゲンという最も恐るべき人物が登場します。ハーゲンはアルベリヒと違って憎々しいほど落ち着き払い、周囲の誰もが彼に操られて破滅へと向かうのです。
神々の長ヴォータンは、もはや『神々の黄昏』には登場しません。神々の側からの最後の努力は、第1幕でブリュンヒルデの岩山にやってくるヴァルトラウテです。ワルキューレの一人であるヴァルトラウテは、神々の滅亡の不安に駆られ、指環をラインの乙女に返すよう迫りますが、神性を失って愛のみに生きるブリュンヒルデには彼女の懇願が理解できず、物語は世界の終末へと加速していきます。
謀略に陥れられたジークフリートはブリュンヒルデを裏切り、ブリュンヒルデは愛ゆえの盲目の怒りに猛り狂って彼の弱点をハーゲンに教えてしまいます。恐ろしいほどに人間が変わり果て、ついに英雄ジークフリートはハーゲンに殺されてしまいます。これらはみな『ラインの黄金』で蒔かれた種から生じたことなのです。誰かが終止符を打たなければ世界は救われない、というとき、指環をラインの乙女に返して悲劇を終わらせるのは、すべてを悟ったブリュンヒルデの人格と決断です。
『神々の黄昏』におけるドラマの進行の激しさ、悪の力への信仰には、息を呑むばかりです。4時間半にわたる音楽のほとんどすべてが、あらゆる否定的な内容を極限まで描き尽くすことに集中しています。美しく崇高なものを肯定的に表現するワーグナーの音楽は言うまでもなく見事ですが、その一方で彼の音楽は、邪悪なもの、醜いものをも芸術的に表現し、極言すれば美しいとさえ思わせるほどの力をもっています。特に、ワーグナーが造形したハーゲンという登場人物に与えられた音楽は圧倒的な説得力があり、ここまで恐ろしい人物が余裕とユーモアさえ感じさせるように描かれていることに、強い衝撃を受けずにはいられません。
『神々の黄昏』では、これまでの3作品で数多く出てきた示導動機がさらに駆使されて転調し変容し、聴き手は、聴き覚えのあるモティーフから、今までの物語や今後の展開を感じ取って聴くことができます。
ジークフリート殺害から葬送に至る場面は、ワーグナーらしい表現の一つの頂点です。最高の英雄が、いまわの際に『ジークフリート』第3幕のブリュンヒルデとの出会いと愛を思い出します。続く葬送行進曲ではジークフリートの英雄性が表現され、彼の両親ジークムントとジークリンデの『ワルキューレ』における出会いと愛の音楽が回顧されます。私たちの中に壮大な物語全体が蘇る、圧倒的な名場面です。
“火”と“水”による破壊を経て最後に救済を暗示する幕切れは、まさにこの世の過去現在未来のすべてが凝縮されています。そして巨大な四部作の最後は、『ワルキューレ』でジークリンデが歌いあげた“救済の動機”が再び出てきて愛による新しい世界を予感させます。私たちは、そこから何を聴き取るのでしょうか。
楽劇(オペラ)というものが表現しうる内容はここまで幅広く深い、ということを、新国立劇場の3年がかりの『指環』を通して皆様に存分に体験していただきたい、と願っております。
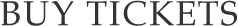
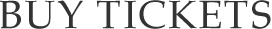 チケットのお申し込み
チケットのお申し込み
 WEBからのお求め
WEBからのお求め
 お電話でのお求め
お電話でのお求め
-
- チケットぴあ
- 0570-02-9999(Pコード321-493)
-
- 東京文化会館TS
- 03-5685-0650
- JTB・近畿日本ツーリスト・日本旅行・東武トップツアーズほか
 グループでのお申し込み
グループでのお申し込み
10名以上でご観劇の場合は
新国立劇場営業部(TEL 03-5352-5745)
までお問い合わせ下さい。