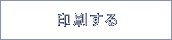- ――マイヤーさんは、世界的なワーグナー歌手の筆頭のおひとりでいらっしゃいますが、ワーグナー作品との出会いはいつ頃ですか? 子どもの頃にはワーグナーを聴いたことがなかった、とインタビューで答えているのを読んだことがあるのですが。
- マイヤー(以下M) 意外かもしれませんが、随分遅い出会いでした。私の故郷であるヴュルツブルクに歌劇場はあったのですが、ワーグナーは上演されていませんでした。というのも、劇場もオーケストラも規模が小さすぎて、ワーグナーが上演できなかったのです。初めてワーグナーのオペラを観たのは1976年です。バイロイトで開催された声楽コンクールで優勝して、その年のバイロイト音楽祭のシェロー演出の「ニーベルングの指環」のチケットをいただきました。コンクール自体はワーグナーやバイロイト音楽祭とは無関係だったのですが、おかげで初めてのワーグナー体験がバイロイト音楽祭のシェローの「指環」という幸運に恵まれました。素晴らしい演出と演奏だったこともあり、瞬く間にワーグナーの虜になりました。真っ暗な空間で『ラインの黄金』の前奏が始まったときの感動は今も鮮明に覚えています。
- ――ご両親は音楽家ですか?
- M いいえ。ごく一般的な音楽愛好家で、ラジオで音楽を聴いていました。もう40年以上も前ですから、今のようにネットやCDで気軽にクラシックが聴ける時代ではありませんでした。両親はワーグナーよりも、ブラームスやシューベルトが好きでした。

- ――確か、マイヤーさんは最初から声楽家を目指していたわけではなかったんですよね?
- M はい。学校の先生になりたくて、大学でフランス語と英語を勉強していました。子どもの頃から外国語に興味があり、早くからさまざまな言語を学んだことは、その後歌手になってからとても役に立っています。フランス語などは発音が本当に難しいですからね。
- ――どのようなきっかけで歌手になろうと決心したのですか?
- M 17歳から声楽のレッスンを受けていて、たまたま師事していた先生が地元ヴュルツブルクの歌劇場の支配人でもあったことから、ある日「うちの劇場のオーディションを受けてみない?」と誘われたのです。何の気なしに受けたら、受かってしまったというわけです(笑)。まだ20歳で、歌手として生きていくといった特別な心構えもなく、「せっかくだし、やってみようかな」といった程度の軽い気持ちで劇場で歌い始めました。ダメだったら大学に戻ればいいと考えていました。堅実な両親は当初、「そんな不安定な職に就かなくても……」と悲観的でしたが、デビューして間もなくマンハイムなどの大きな歌劇場に招聘されるようになった私の活躍ぶりを見て、応援してくれるようになりました。父は私が22歳のときに亡くなりましたが、デビュー2年目で確かなキャリアを歩み始めた娘を見て、安心していました。
- ――ワーグナー役デビューとなった公演は?
- M 最初に契約したのがヴュルツブルクの歌劇場だったので、1976年にデビューしてしばらくはワーグナーとは無縁で、ケルビーノ、ドラベッラ、『ホフマン物語』のニクラウスといったリリックな役を歌っていました。ワーグナーを歌い始めたのは、1978年にマンハイムの歌劇場の契約歌手になってからで、初めて歌ったのが『ラインの黄金』のエルダでした。その後すぐにフリッカとヴァルトラウテも歌うようになりました。今回新国立劇場で歌うヴァルトラウテは1979年から38年間歌い続けている役です。自分のレパートリーのなかで一番長く歌っている役かもしれません。
- ――38年間ですか! そのような難役を長年にわたって第一線で歌い続けるために、どのようなことを留意していますか?
- M 喉を傷める危険のあるオファーは、どんなに魅力的であっても断ってきました。そのために著名な指揮者との関係が悪くなったこともあります。アバドがその一例で、彼は私にエレクトラを歌わせたかったのですが、何度頼まれても断りました。かなり失望したようで、その後、二度と声がかからなくなりました(苦笑)。でも、あのときに役を引き受けていたら、今頃はもう引退していたでしょうね。ショルティのオファーを断ったこともあります。自分の声は、自分で守らないといけません。それからワーグナーを歌い続けるには、確かな発声技術と、ワーグナーばかり歌い続けないように気をつけることが必須です。私はワーグナーばかり歌っているように思われていますが、1シーズン中に歌う回数はそれほど多くないんですよ。喉を大切に使い、オペラでは蔑ろにされやすい言葉や音楽的なディテールを大切にする姿勢を忘れないためにも、昔から歌曲(リート)をよく歌っています。リートの世界にはオペラとは違った魅力があります。

- ――ヴァルトラウテは、ブリュンヒルデのもとにひとりやってきて、指環をラインの乙女たちに戻すよう説得を試みるという役柄です。
- M ワルキューレの名前には全て意味があって、ヴァルトラウテ Waltraute という名前には、「ヴァルシュタット Walstatt(戦場)」、ヴォータンの「フェルトラウテ Vertraute(腹心)」という意味があります。だからほかの姉妹ではなく、彼女がブリュンヒルデに会いにいくことに意味があるのですよ。蛇足ですが、私の名前ヴァルトラウトはフランドル地方の聖人に由来していて、ヴァルトラウテとは無関係です。よく誤解されるので念のために!(笑)
- ――ヴァルトラウテが唯一登場する第1幕第3場での長丁場の「ヴァルトラウテの語り」は、「ブリュンヒルデの自己犠牲」と同じくらい重要な部分かと思います。
- M ヴァルトラウテは、登場してすぐに場面の空気をガラリと変えなくてはいけません。それまで『指環』で起きたこと全てを振り返り、指環が再びライン川に戻るための下準備をするのです。彼女はヴォータンの命令に背く危険を冒してブリュンヒルデに会いに行き、なんとか指環を手放すよう求めますが、断られてしまいます。自分の恋を祝福するために来てくれたのだと勘違いして大喜びするブリュンヒルデと、全く逆の心境のヴァルトラウテ。この姉妹の決定的な温度差をどう表現すべきか、毎回考えています。非常に奥の深い役で、やりがいがあります。
- ――ブリュンヒルデ役のペトラ・ラングさんと共演したことはありますか? 第1幕第3場での彼女との共演について、どのような思いですか?
- M ブリュンヒルデの個性が強ければ強いほど、私が最後に発する彼女への「呪いの言葉」が際立ちます(苦笑)。ペトラ・ラングさんとは『トリスタンとイゾルデ』で共演したことがあります。私がイゾルデ、彼女がブランゲーネを歌いました。『神々の黄昏』を一緒にやるのは初めてですが、どんなブリュンヒルデになるかすごく楽しみです。

- ――ヴァルトラウテはもちろん、クンドリーをはじめとするワーグナーの諸役に、マイヤーさんはどのようなアプローチをしていますか?
- M ワーグナーに限らず、どんな役でも、歌詞が鮮明に客席に伝わるよう常に心掛けています。どんなに声が美しく響いても、歌詞の内容、解釈が客席に届かなくては不十分です。歌詞、音楽、声が一体となってはじめて作品に命が吹き込まれ、感動が生まれるのです。ワーグナー作品ではこれまで17の役柄を歌い、自分の声域に合う役は全てレパートリーに入っていますが、勉強の段階から常にこの三点に注意を払っています。ワーグナーは楽譜に自分の考えを詳細に記しているので、楽譜以外の参考文献はあまり読みません。通常は伴奏ピアニストに協力してもらって、歌に専念しながら役作りをしています。
- ――これまで出演したワーグナー作品のプロダクションで一番心に残っている公演は?
- M 『神々の黄昏』に関していえば、ハリー・クプファーですね。1988年のバイロイト、そしてベルリンでも彼の演出で歌っています。レーンホーフやゲッツ・フリードリヒの演出も印象的でした。新国立劇場もフリードリヒの演出だそうですね。一流の演出家とのコラボレーションではいつも多くのことを学ばせてもらいますが、フリードリヒもそのような演出家で、根っからのオペラ演出家でした。しかし演劇や映画出身の演出家であっても、音楽に対する感性が備わっていれば問題ありません。シェローなどがその良い例です。大変な教養人でした。
- ――これまでに何度も来日していらっしゃいますが、新国立劇場へは今回が初登場となります。
- M 日本には何回も行っていますが、不思議とこれまで新国立劇場と縁がなくて。ですからオファーを受けたときは嬉しかったです。素晴らしい劇場だという話は常々耳にしていますが、実際に中に入ったことはないので、今から興味津々です。
- ――最後にマイヤーさんの再来日を待望する日本のオペラ・ファンにメッセージを。
- M 40年近く歌い続けている大好きなヴァルトラウテを、日本の皆さんに聞いていただけるのを楽しみにしています。
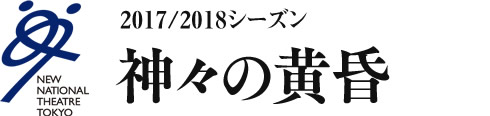
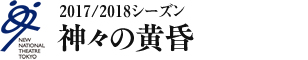
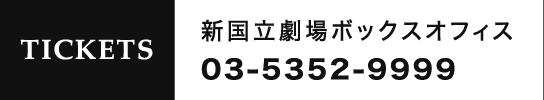
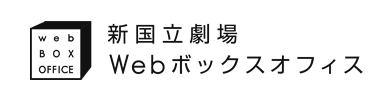




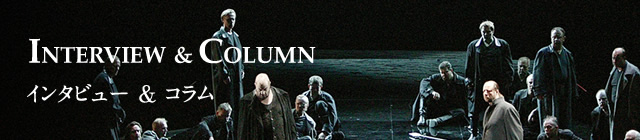


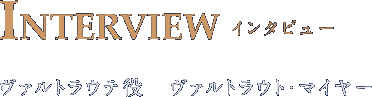
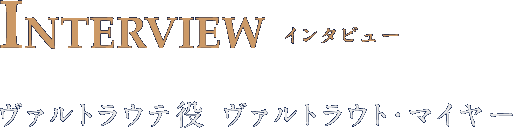
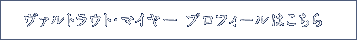
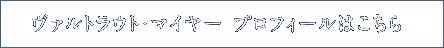


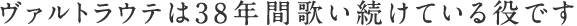
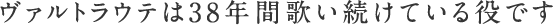
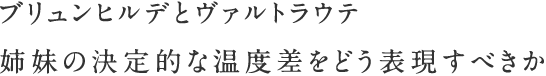
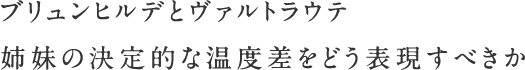
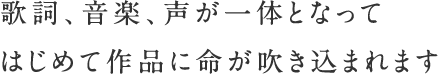
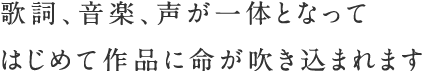
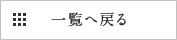
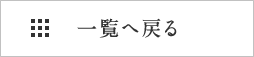
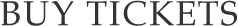
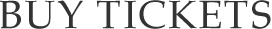
 WEBからのお求め
WEBからのお求め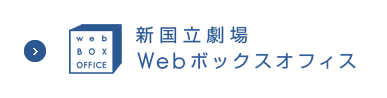
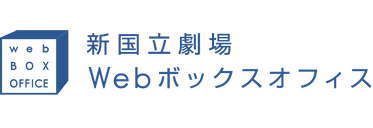






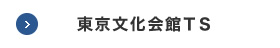
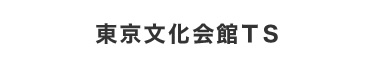
 お電話でのお求め
お電話でのお求め グループでのお申し込み
グループでのお申し込み