現代戯曲研究会
座談会 連続3回掲載その(2)
いま、同時代演劇とは?
小田島恒志 佐藤 康 新野守広 平川大作 鵜山 仁(進行)
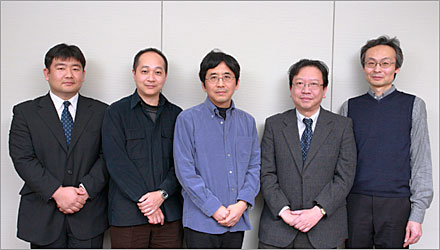
“イン・ユア・フェイス”の役割
<承前>
鵜山●“いま、同時代演劇とは?”という、テーマでドイツ、フランス、イギリス、それぞれの現代演劇の経緯を前回お話いただいています。今回はその2回目です。
新野●前回デーア・ローアーが新しい描き方で社会の問題を扱っていることをお話しましたが、演劇がまだ社会と対応する可能性があるという点は捨てたもんじゃないと思うんです。その可能性の一つとして、シンメルプフェニヒやローアーは、平川さんのお話にあったイギリスの“イン・ユア・フェイス・シアター”と呼ばれている暴力表現、これまでの近代劇を踏み越えてしまうような猥雑な表現や血で血を洗うような表現を使う90年代後半のイギリスの作家たちのスタイルを取り入れながら、独自の世界を切り開いている。イギリスは戯曲や劇作家で考えると非常に豊かな国ですね。戯曲研究会で小田島さんと平川さんに多くの戯曲を訳していただいて、その多様性に目が開かれる思いがしました。ドイツではとてもこうは書けない。ドイツ語圏の劇場は学生革命世代の演出家が主導権を握っているので、若い劇作家は登場しにくいんですね。ただ90年代後半は、ベルリンの劇場がロンドンのロイヤル・コート・シアターと提携して、サラ・ケインに代表されるタブー破りの劇作家たちの作品を上演した。イギリスはこういうインパクトのあるものがあると紹介されたため、ドイツでも若い劇作家が登場するきっかけになった。若い劇作家たちは、イギリスの作家たちに勇気づけられたと言っています。
平川●アレックス・シアーズの『イン・ユア・フェイス・シアター』は90年代に続々登場した新世代の劇作家たちを総括するためにまとめられたジャーナリスティックな書物ですが、“イン・ユア・フェイス”という呼称はある程度流通しているようです。シアーズによれば、“アングリー・ヤングメン”以降のイギリス演劇界において、“イン・ユア・フェイス”をもっとも大きなムーブメントとして位置づけることができるだろうと。
小田島●タブーと言われていた暴力やセックスなど表に出せないものは何なのか。それが、“イン・ユア・フェイス”で、面前で行なわれる。それはどんなに新しいのかというと、暴力に注目すれば、かつて鵜山さんが演出したエドワード・ボンドの『リア』も暴力を描いていて、“イン・ユア・フェイス”に負けていないですよね。性的なタブーでいえば、ジョー・オートンという作家が60年代にすでに出ている。このようなものを描いてきた作品は連綿とあるのに、なぜサラ・ケイン以降特殊なのかというと、これは説明がちょっとややこしい。まず、イプセンからはずっとリアリズムによって社会をリアルに描くだけでなく、こうすべきだというめざしている社会も示されていた。それがアングリー・ヤングメンの時はこうすべきだという答えを提示しないで、ダメだと言うけれど、めざしている方向というか答えがない。答えが見つからないことに怒っている。セックスだとか暴力だとかあらゆる目を背けたくなる出来事を描くのもそうした不満や怒りや表れとも言える。ところが何の必然性も伴わずにそういうものが出てきちゃうのが“イン・ユア・フェイス”以降の特徴です。それを観た観客は嫌悪感こそ覚えるけれども、なぜそうなるんだとか、こうすればいいんだとか、答えの提示に至らない。だからこそ、よけいショックだし、ある意味90年代以降のリアリズムといえるんじゃないでしょうか。サラ・ケインの世界についても、だって現実社会がそうだから、ということですよね。ものすごい暴力が描かれる時に、その劇作家の怒りによって書かれているわけではなく、ごくあたり前のようにそこに暴力があって、昨今の猟奇的な殺人事件などを見ているとまったくその通りだと思う。文脈なく出現する。それを実際に書いているわけです。
新野●シンメルプフェニヒにもデーア・ローアーにも、脈絡のない暴力をどう表現するかという関心が強い。こういう戯曲を書く人が出てきたのは、劇場が新しい世代にバトンタッチされたことの現れでしょう。新自由主義の結果、セーフティーネットが失われてしまったことが誰の目にも明らかになった。事態をなんとかしたいという気持ちを多くの人がもっていると思いますが、新しい世代を中心にこのモチーフを劇場に取り込むことができるんじゃないか。その可能性を見たいのです。
鵜山●日本だと、つかこうへいさんの“ブス”という言葉が決定的なインパクトをもった時代がありましたが、ヨーロッパと日本とはどこがどう違ったのか。“イン・ユア・フェイス・シアター”は言葉の地平を広げたと言っていいんでしょうか。
小田島●サラ・ケインの処女作『Blasted』が登場した時は、「吐き気をもよおすような汚辱の饗宴」と評された。酷評です。そういう反応はもちろんあったということです。それが上演できてしまったことが大きいことだと思います。後に続く作品にとっても。
平川●その背景には検閲の問題もあります。イギリスで検閲が撤廃されたのは1968年で、それまでは誰が観客となるか分からないパブリックな公演に関して宮内長官が厳しく検閲をしていた。1955年に『ゴドーを待ちながら』がイギリスで初演されたときも、検閲を避けるためにクラブ制の劇場で上演されています。検閲が問題にした事柄のひとつは、特定の言葉、いわゆる卑語の使用でした。先のシアーズは、ジョージ・バーナード・ショーが1913年に『ピグマリオン』のなかで“ブラッディー”という言葉を使ったことを例に出しています。そんな猥雑な言葉を使うなんて! と当時はたいへん問題になった。現実世界では自由に使われている言葉を舞台では使ってはいけない、というのは劇作家にとって実に不自由な条件です。イギリスにおいては検閲との闘いが68年まであり、その後もいわゆるFワードの使用をタブーとするような言語的抑圧状況が続いたなかで、90年代に何かが弾けて、どんな言葉でもすべて使ってかまわない状況になった。あるいは劇作家たちの闘いがそうした自由をたぐり寄せた先に、“イン・ユア・フェイス”における劇的想像力の爆発が起こった。サラ・ケインの登場が演劇史的な事件だったわけですが、同時代に登場した若い劇作家たちの背景には90年代にイギリスで生まれた新しい美意識と想像力が共通項として存在した、というのがシアーズの主張です。彼らは“サッチャーの子どもたち”と呼ばれる世代で、東西冷戦が終わってベルリンの壁が壊れてという時代、新野さんが話されたような演劇が現実を変えうるという希望が見えた90年代に青春期を過ごしたことが大きかった。個々の作家には勿論個性の違いはあるが、観客の首根っこをつかまえてショックを与えることで現実を変えたいという志のようなものは共通している。暴力も卑語もそれが現実世界に存在するのであれば、舞台にも存在させる。“イン・ユア・フェイス”は見方によればある種のリアリズム回帰といえなくもない。他方で若い劇作家の登場とその作品を商業的なメリットとして歓迎するイギリスの演劇ビジネス、文化政策が“イン・ユア・フェイス”の生まれる環境を整備したことも大きい。
小田島●検閲については、ずいぶん変わってきたと思います。同性愛はタブーでしたし、自殺すら犯罪とされていたのが、ついこないだの60年代です。鵜山さんが日本の60年代から話し始めたけれども、確かにそこからいろいろなことが解放されていると思います。
