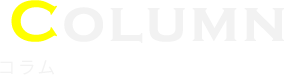『ヘンリー六世』第二部(2009年) 浦井健治 中嶋朋子
第3回 そして『ヘンリー六世』三部作へ・・・
ここまでは、ヘンリー五世以前の世代を描いた英国歴史劇に注目し、第一回では一世代前を描いた『ヘンリー四世』二部作、第二回ではさらに前の世代を描いた『リチャード二世』を取り上げました。今回は次の世代、つまりヘンリー五世の息子の世代を描いた『ヘンリー六世』三部作を取り上げ、『ヘンリー五世』との関わりを考えてみましょう。
「ヘンリーは死んだ、もう二度と生き返ることはない」
(『ヘンリー六世』第一部)
『ヘンリー六世』第一部は、ヘンリー五世の葬列が登場する場面から始まります。ある参列者は「ああ、ヘンリー五世王、/ 彼の名声があまりに高かったため、いのちは短かった」(一幕一場)と口にし、また別の参列者は「ヘンリーは死んだ、もう二度と生き返ることはない」(同)と語ります。これらの台詞は、死せる王を悼む台詞であると同時に、その後を受け継ぐヘンリー六世、そしてイングランドが直面する困難を予告するかのようです。
事実、ヘンリー六世は第三部にて暗殺され、彼を手にかけた人物は次回作にて希代の悪漢たる君主リチャード三世として、その名を轟かせることになります。このように、王国を引き継いだ息子が亡き者とされる『ヘンリー六世』から遡り、父であるヘンリー五世の世代を眺め直すこともできるでしょう。ここで、息子ヘンリー六世の末路が『ヘンリー五世』のエピローグにて端的に語られている点に注目してみましょう。
「だが彼をとりまく多くのものが政権を争うことになり」
(『ヘンリー五世』)
『ヘンリー五世』のエピローグでは再び説明役が登場し、『ヘンリー六世』三部作との歴史的なつながりを強調します:
息子ヘンリー六世は、幼くして父王のあとを継ぎ、
フランス、イギリス両国の王となりました。
だが彼をとりまく多くのものが政権を争うことになり、
ついにフランスを失い、イギリスにも血が流されました。
そのいきさつはすでにこの舞台でごらんにいれております。(エピローグ)
実を言えば、シェイクスピアは『ヘンリー六世』三部作を先に執筆・上演したと考えられていますので、『ヘンリー五世』は『ヘンリー六世』のプリクエル(前日譚)にあたります。「すでにこの舞台でごらんにいれて」いるという台詞を耳にすれば、当時の観客は先に観劇した『ヘンリー六世』三部作を脳裏に思い浮かべたことでしょう。と同時に、歴史的な流れとしては、ヘンリー五世がもたらした治世にも必ず終わりが訪れることを、ましてや次世代においては悲惨な結末が待ち構えていることさえ、観客は『ヘンリー五世』のエピローグに至って再認識させられるのです。それは、ハッピーエンドがいつまでも続くわけではないという透徹した歴史観に、我々観客が不意に遭遇する瞬間なのかもしれません。
最後に:英国歴史劇というダイナミズム
このコラムでは全三回に渡り、『ヘンリー五世』と他の英国歴史劇とのつながりについて、『ヘンリー四世』二部作、『リチャード二世』、『ヘンリー六世』三部作に的を絞りつつ、そのダイナミズムの一端を示してきました。これら関連する英国歴史劇を幅広く読み直すことで、ヘンリー五世という一人の王について、彼が象徴するイングランドという国の、その歴史の一幕について、改めて多面的に眺められるのではないでしょうか。その豊かな可能性に期待を寄せながら、新たな演出で甦る『ヘンリー五世』を新国立劇場で体感しようではありませんか。
※訳文は全て小田島雄志訳、シェイクスピア全集(白水社)に拠る。
- 小泉勇人(こいずみ・ゆうと)
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 - 関西学院大学文学部英文科を卒業後、早稲田大学文学研究科にてシェイクスピア劇を研究、2015年にロンドン大学にて修士号を取得。2017年4月より東京工業大学リベラルアーツ研究教育院・外国語セクションに着任。シェイクスピア映画を中心に研究し、映画を用いた大学英語教育にも関心がある。