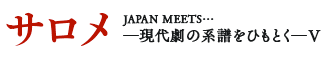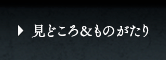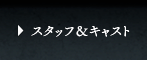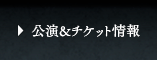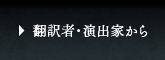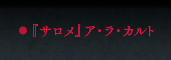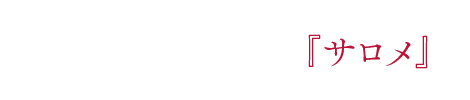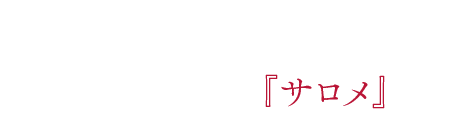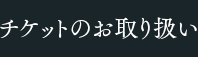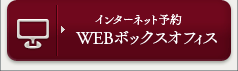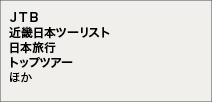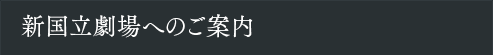今回、新国立劇場の舞台に登場する衣裳は、株式会社ヨウジヤマモトの協力を得て、すべてヨウジヤマモトの衣裳、現代服で行う。宴会のシーンは現代のパーティのように洗練されたお洒落な場面の中で、招待者やサロメの家族、兵士たちの思惑が表現される。とても美しくスタイリッシュな舞台面となるだろう。
また、舞台美術のデザインは中劇場は初めてとなる伊藤雅子。演出・宮本亜門のコンセプトはヨカナーンが閉じ込められている地下牢は絶えず、お客さまから見えていたいとのこと。中劇場の張り出し部分に巨大な地下牢をつくり、そこに水をはり、ヨカナーンが最初から徘徊している姿が見える構造を考えている。その上にアンバランスに建っているテラス。
これまで井戸や地下牢が見えず、声だけ聞こえていたヨカナーンの姿が見える演出が多かったが、上部の宴会の行われるテラスと下部の地下牢、このコントラストの二重構造が作品全体の緊張感を高めている。
『サロメ』とは──
サロメは「ヘロディアの娘」として新約聖書に記述され、「サロメ」という名は登場していない。が、『ユダヤ古代誌』ほかの文献には記述があり、AD14年頃に生まれた実在の女性と考えられている。古代パレスチナの領主ヘロデ・アンティパウスの祝宴での舞踏の褒美として好きなものを与えると言われ、サロメは母ヘロディアの命により「洗礼者ヨハネの斬首」を求めたとされる。
このサロメの伝承をもとにオスカーは戯曲を執筆、1893年にパリで出版され、翌年ロンドンで出版された英語版はビアズレーの挿絵で話題になったが、その背徳性のために彼の生前にはイギリス本国では上演禁止、1896年にようやくパリで初演されている(ちなみに、R.シュトラウスによるオペラ『サロメ』は1905年ドレスデンで初演)。聖書のなかの逸話と『ユダヤ古代記』がサロメの源泉であることから、中世から聖史劇や教会を飾るモザイク画やレリーフなどにサロメは登場していたが、オスカー以後、特にフランスを中心に19世紀になって文学史上で盛んに取り上げられたほか、多くの芸術家たちにさまざまなインスピレーションを与え、絵画、音楽、映画、そして演劇のモチーフになっている。
日本で最初に“サロメ”を演じたのは、松井須磨子という女優である。大正2(1913)年というから今から99年前。須磨子という人は、イプセンの『人形の家』でノラを演じ、大女優の道を歩み、『復活』で“カチューシャ可愛や別れのつらさ~”の出だしで知られる『カチューシャの唄』を歌って大ヒット。その当時を知らなくても、例えば宮本研作の傑作戯曲『美しきものの伝説』を観たことのある人ならピンとくるはず。もっとも劇中に須磨子は登場せず、一緒に暮らした藝術座の主宰者・島村抱月の目で須磨子は語られるのだが。(その代わり、というか、劇中の登場人物はみんなあだ名で呼ばれているが、大杉栄の愛人だった女性新聞記者であり女性解放運動家の神近市子が“サロメ女史”として登場する)
そして須磨子のサロメは、愛する抱月をヨカナーンに見立て独占することで、自分の存在価値を高めようとしたとか。その純粋な、男の運命を変えるファムファタル的な資質は、サロメを演じるにふさわしかったように見える。7年間、演じ、まさに須磨子の当たり役になった。

オスカー・ワイルドは、ギュスターヴ・モローの描いた聖なる娼婦サロメの絵画に啓示を受けた、という説があり、この少女に無邪気で残忍な生命をワイルドは吹き込む。そして、このドラマにのっとってリヒャルト・シュトラウスが傑作オペラを生んだ。『サロメ』がフランス語でパリの出版社から世に出たのは1893年。演劇の初演は1896年、衝撃的な舞台劇としてヨーロッパで広く知られるようになり、シュトラウスがオペラ化の申し出を受けたのが1902年。シュトラウスは大いに乗り気で、足かけ3年、最終的な総譜が完成したのは1905年6月のことで、その年の12月には歴史的なオペラ初演がドレスデンで幕をあけた。結果はドイツ歌劇史上に残る大成功。以来、『ばらの騎士』とともに、シュトラウス作曲のオペラで今日もっともよく上演されるレパートリーになっている。まさに爛熟したヨーロッパの世紀末文化が生み出した、華麗な成果のひとつである。