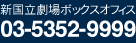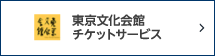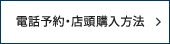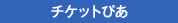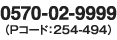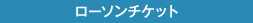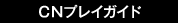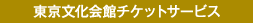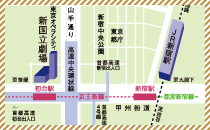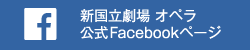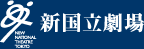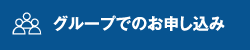
10名以上でご観劇の場合は新国立劇場営業部(TEL 03-5352-5745)までお問い合わせください。
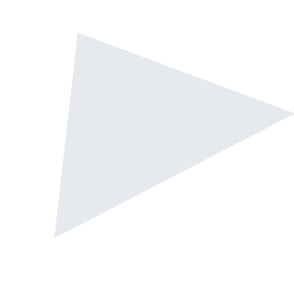


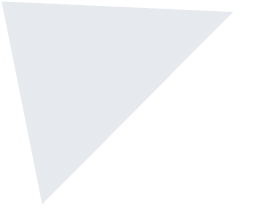
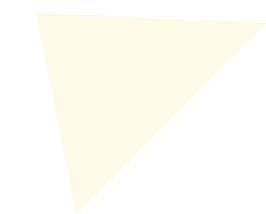

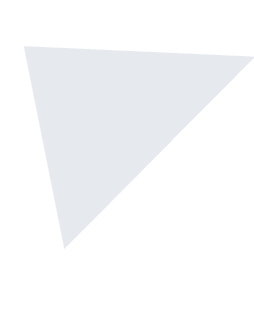


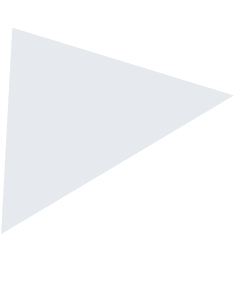
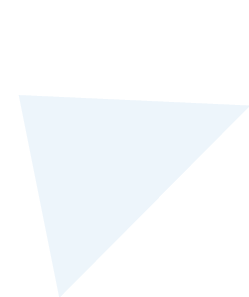
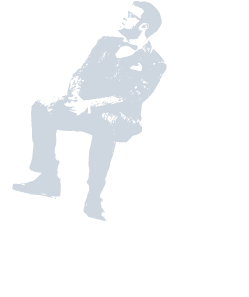
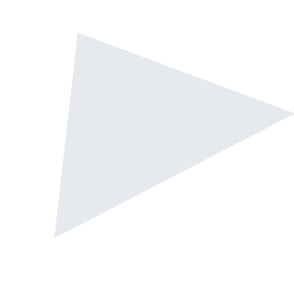


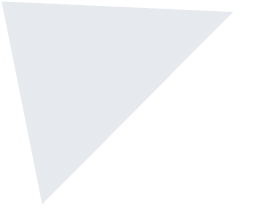
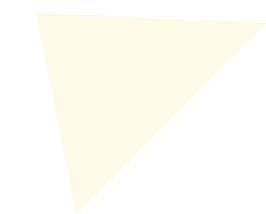

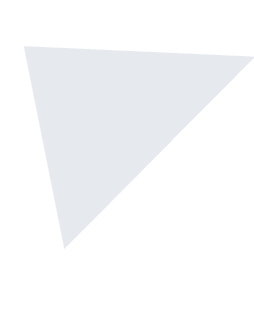


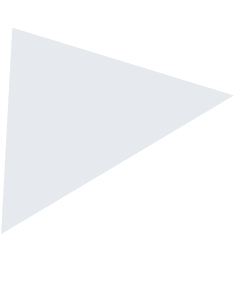
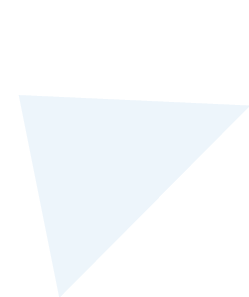
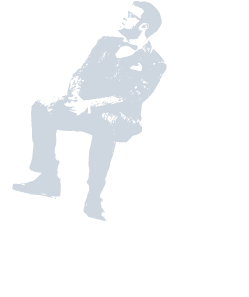
インタビュー&コラム
クリストフ・ロイ演出の『イェヌーファ』
――愛による浄化の物語を越えて
城所孝吉(音楽評論家・ベルリン在住)<ジ・アトレ9月号より>ロイのベルリン・ドイツ・オペラ・デビュー作
 Production: Deutsche Oper Berlin
Production: Deutsche Oper BerlinPhotographer: Monika Rittershaus
ドイツ出身のロイは、現在50代半ば。すでにベテランの域に入りつつある、気鋭の演出家である。1990年代の終わり頃に登場し、まず地方劇場で活躍したが、瞬く間に国際的スターの仲間入りを果たした。これまでロイヤル・オペラ、バイエルン州立歌劇場、ザルツブルク音楽祭などで演出しているが、ベルリン・ドイツ・オペラには、この『イェヌーファ』でデビューしている。そのスタイルは、どちらかというとオーソドックスなもの。もちろん時には、ザルツブルク音楽祭での『影のない女』のように、舞台を50年代のレコード録音スタジオに移す、というようなこともやっている。しかし全体としては、聴衆を驚かし、挑発するタイプではなく、作品自体からアプローチする演出家と呼べる。大歌手たち(エディタ・グルベローヴァや今回コステルニチカを演じるジェニファー・ラーモア)から支持されているのも、そのためだろう。
 Production: Deutsche Oper Berlin
Production: Deutsche Oper BerlinPhotographer: Monika Rittershaus
成長・変化の物語を問い直す演出
 Production: Deutsche Oper Berlin
Production: Deutsche Oper BerlinPhotographer: Monika Rittershaus
しかし、歌手の演技を観ていると、徐々に「普通の『イェヌーファ』と違うのではないか?」と思えてくる。なぜなら、ドラマの核心となる主人公たちの成長・変化が、意識的に避けられているからだ。
ドラマ上で最も重要なのは、イェヌーファ、ラツァ、コステルニチカの3人が、かつての自己を克服し、真の愛に目覚める点だろう。連れ子であるためにブリヤ家の跡継ぎになれず、製粉業もイェヌーファも義弟に譲らざるを得ないラツァは、シュテヴァへの嫉妬からイェヌーファの頬を裂き、彼女が彼と結婚できないようにする。イェヌーファは、ラツァに愛されていると知りながらも、美男で後継ぎのシュテヴァを選び、彼に身を委ねる。コステルニチカは、酒飲みの夫が死んだ後、教会の管理者となって地位を築き、厳格な村のご意見番へとのし上がる(教会の管理者とは、教養と権威のある人、つまり「自分は普通の村人よりも立派だ」と自負する人がなるものである)。
つまり、彼らは必ずしもポジティブな人物ではない。むしろ自己愛に満たされた、エゴイスティックな性格の持ち主である。しかしラツァは、自分の行為が原因でイェヌーファの身持ちが崩れたことを理解し、悔いる。イェヌーファは、瑕ものとなった自分を、それでも愛してくれるラツァの深い心を知る。コステルニチカは、イェヌーファ(=自分)の体面を守りたいというプライドが、殺人の原因となったことを認める。その心の変化、真の愛の認識が、ドラマの終わりで彼らを浄化する。そして我々に、3人がいつか煉獄を脱し、幸福を見つけるだろうと予感させるのである。
これに対してロイ演出は、彼らにこの成長・変化を体験させない。殺人が明らかになった後、コステルニチカは罪を告白するが、依然として青ざめた表情で、逃げ去るように舞台を後にする。イェヌーファは、第2幕幕切れでラツァに「こんな私でも貰ってくれるの?」と言うが、演技には、まだシュテヴァを諦め切れていない様子が滲み出ている。彼女は最終場面では、ラツァに手を差し伸べ、共に歩んでゆく気持ちを示すが、その表情は-ラツァと同様に-こわばったままである。実際ふたりは、音楽が示唆する光ではなく、闇のなかへと消えて行く。まるで彼らの将来が、不幸に包まれているかのようにである。
ロイがこのような結末を提示したのは、どのような意図があってのことなのだろうか。ヤナーチェクが描こうとした浄化のプロセスが、理想主義的に過ぎ、現実の人間の業とかけ離れている、と示したかったのだろうか。しかし、これをどのように感じるかは、観客ひとりひとりの問題とも言えるだろう。それはぜひ、2月の公演をご覧になって確かめてみて欲しい。
 Production: Deutsche Oper Berlin
Production: Deutsche Oper BerlinPhotographer: Monika Rittershaus
オリジナル・キャストによる最高の舞台
ベルリンでの歌手たちは、全員が優れた歌いぶりであった。題名役のミヒャエラ・カウネは、長らくベルリン・ドイツ・オペラの看板歌手だったが、イェヌーファは生涯の当たり役かもしれない。ドラマティックなハイトーンが続くパートを、何の不安もなく歌い、しかも体当たりの演技を見せている。コステルニチカのジェニファー・ラーモアは、かつてのロジーナやチェネレントラとは似ても似つかぬ汚れ役で、文字通り新境地を切り開いた。このところ彼女は、メデアやマクベス夫人(共にロイ演出)まで歌っているが、コステルニチカは、性格女優への転換を誘導した。嬉しいのは、往年の名メゾ、ハンナ・シュヴァルツが老ブリヤを歌うこと。いまだにエレガントな姿、そして豊かな声で、現役であることを実感させてくれるだろう。