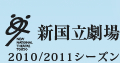対談 水谷八也(翻訳)×宮田慶子(演出)を掲載しました。
2010年 11月 08日
日本の演劇史に大きな影響を与えた海外戯曲を新訳・新演出で上演、私たちの「現在」を見つめる[JAPAN MEETS…]シリーズ。
その第三弾はソーントン・ワイルダーの「わが町」だ。日常生活の些細なできごとや喜怒哀楽を丁寧に描き、その瞬間瞬間を唯一無二のものとして輝かせるこの名作を、今、どう舞台に立体化するか。
演出家・宮田慶子とワイルダー研究者でもある翻訳家・水谷八也が、上演に向けた夢と期待を大いに語る。
進行・文◎鈴木理映子(演劇ライター)
会報誌The Atre10月号掲載
「演劇の力」を知る感動
――[JAPAN MEETS…]シリーズにこの作品を選んだ理由、その魅力はどんなところにあるのでしょう。
宮田 「わが町」は、しっかりした舞台装置が主流だった時代に、何もない空間に舞台を設定し「それでもドラマは成立する」ってことを見せた作品です。そこには「演劇の力」を見直し、取り戻すための問いかけがある。もちろん日本の演劇史にとって重要な作品は今回[JAPAN MEETS…]シリーズで取り上げた4作品以外にもありますが、なかでも観客の皆さんに親しく接していただけるものとなると、やはり「わが町」ははずせなかったですね。セットだけじゃなく、王様もお姫様も登場せず、国と国の争いも、ドロドロの愛憎もない。あたりまえの市井の人の一生を淡々と追っただけなのに、こんなに笑って、泣いて、感動できるんですから。
水谷 ワイルダーの作品は演劇の原点ともいえる力を持っていますからね。近代の演劇は「あなたと私」のような横の関係を主に描くけど、たとえばシェイクスピアの直前までは宗教劇ばかりだったから、「世界と私」「宇宙と私」「神と私」という縦軸を描く芝居が多かった。ワイルダーは近代の「個」をめぐるだけの芝居や上演法に満足していなかったので、結果として、彼の芝居は近代以前の演劇のあり方と重なる部分が多いんです。
宮田 新しい手法なんだけど、古いものの力強さを再認識させますよね。
水谷 そう。またそういう視点や上演法は、岡田利規や前田司郎、柴幸男といった現代の若い演劇人ともどこか共通している気がします。そもそも今の時代って混沌としていて、誰もが共有できる基準がないから、みんな「今、自分たちはどこにいるのか」っていう俯瞰の視点に関心を持つんじゃないでしょうか。ワイルダーはそういう気持ちにも、ストレートに答えてくれますね。
宮田 確かに、この作品のどこに私たちが涙するかというと、それはやっぱり自分の立ち位置を考えさせてくれるからですよね。単なる郷愁じゃなく「今お前はどこにいるんだ」ってことを突きつけられる感動。で、素直にそれを「みんなで考えよう」と思うと、なんだか嬉しくなっちゃうんです。
ワイルダーの頭の中は?
――上演に向けて準備を進めるなかで、改めて発見されたこと、演出に生かしたいことはありますか。
宮田 1幕と2幕では子供が自立していくときの親との葛藤だとか、初めての恋だとかっていう、誰もが思い当たる普通の生活が丁寧に描かれていて、3幕ではそれを死者の立場から眺め、大きな宇宙の中でのわれわれの小さな営み、その愛おしさを分からせてくれる。1、2幕の丁寧さがあるからこその3幕の感動があるという構造はまず踏まえておきたいです。
また今回はマンスリー・プロジェクトで同じワイルダーの「三分間劇場」(*)のリーディングを聞いていただくこともあって、私自身も水谷さんにレクチャーを受けているんですが、そうこうするうちに、ワイルダーの頭の中は想像以上にぐちゃぐちゃだった、ということが分かってきまして……。
水谷 子どものころから夢想癖が強くて、それに手紙魔で、多いときには1日25通も書いていたんですが、言葉が想いについていかないんですね。そんな手紙は字も汚いし、スペリングや文法も無視なんです。お母さんに「あの子は英語が下手で」って言われてた。想像で頭がいっぱいになっちゃってたんでしょうね。
宮田 だから、絵を描くように文字を書いていたんじゃないかって気がしたんですよね。彼の頭の中には天も地もないようなすごくスケールの大きい絵があって、それを写すように戯曲を書いていたんじゃないか。死者ばかりが出てくる「わが町」の3幕も、演劇的な仕掛けという以前に、彼にとっては当たり前の世界だったのかもしれない。となれば、せっかく上演するんですから、今回はそんなワイルダーの本質もふっと感じさせるようにしたいです。
観劇後の「夜の時間」に
――この戯曲の冒頭には「幕なし。舞台装置も一切ない」と書かれています。でもお話を聞いていると、その分やるべきことことは多いようです。
宮田 そうなんです。「ないからこそできること」が「わが町」の凄さでもあって。何もないからこそ、その空間は家の中にも、道端にも、墓場にもなる。
水谷 シェイクスピア劇だってもとはそうだし、能や狂言だって舞台上には何もないですから。でも、この作品、1938年にボストンで試演をしたときに、州知事夫人が途中で席を立って帰っちゃったんですよ。「私たちは劇場のうしろの壁を観にきたわけじゃない」って。
宮田 (笑)。私は、演劇の力は空間を埋める力だとも思っていて。今回は稲本響さんにピアノの生演奏で入っていただくんですけど、それも劇伴音楽じゃなくて、まるで登場人物のように、そこに音が存在してほしいと思ったからなんです。情緒ではなく、風みたいな存在として空間や俳優と対話してほしい。またそこで大変な神経を使って出された音を俳優たちが受け取って、同じような繊細さで言葉を発してくれたら……っていうコラボレーションも夢見ているんです。
水谷 あぁ、イメージが湧いてきた。ほんと、音ひとつ、言葉ひとつが大切に生かされる場面がたくさんあるといいですねぇ。
――見かけも扱っているテーマもシンプルですが、深く豊かな世界を持った作品になりそうです。
水谷 ワイルダーは夜の時間が好きで、他の芝居では夜の時間に哲学者の言葉を語らせてるほどです。「わが町」が星空の下の「おやすみなさい」という言葉で終わるのも、やっぱり思索的な時間を観客と共有したいっていう彼の気持ちの表れだと思う。だからただ「あー泣いちゃった」というんじゃなく、その感動がどこから来てるのか、その質について、家に帰ってからも、夜の時間にじっくり考える、なんてことがあればいいですよね。
宮田 まさしく。今回の[JAPAN MEETS…]で取り上げているのはどれも、そんなふうに考えてほしい戯曲。「わが町」もボディーブローのように利く作品になるはずです。
*ワイルダーの初の戯曲集(1928年)に収録されている16編の戯曲で、いずれも登場人物は3人、上演時間は約3分。2011年1月のマンスリー・プロジェクトの講座(講師:水谷八也)内でその一部を紹介する。