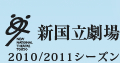小堺一機さんのインタビューを掲載しました。
2010年 12月 06日
アメリカ北部の平凡な町を舞台に人々の生活とその移り変わりを繊細に描くソーントン・ワイルダーの『わが町』。「死」をも踏まえたその切り口は、日常のなんでもない会話やできごとを、切ないほど輝かしい瞬間として舞台によみがえらせる。広い視点と温かみを兼ね備えた語り口で舞台を進行させ、観客を町へと案内するのは舞台監督役の小堺一機。ドラマ性を抑えた演技の難しさに触れつつも、早くも「わが町」への愛をヒシヒシと感じさせるその語り口は、まさにこの舞台と観客をつなぐガイドのそれだった。
インタビュアー◎鈴木理映子(演劇ライター)
会報誌The Atre11月号掲載
 人間としての「経験」が出ちゃう芝居。でもそうじゃないと。
人間としての「経験」が出ちゃう芝居。でもそうじゃないと。
――『わが町』という作品に触れられるのは客席・舞台上を問わず、これが初めてなんですね。
以前からワイルダーさんの「匂い」のようなものは知ってたんですけどね。要するに特別なできごとがあるわけでもなく、まるで日記のような内容で、思い入れがあるかと思うと急にふっと客観的になったりするというような……。シェイクスピアだとかカフカみたいに「優等生じゃないと分からないでしょ」って感じはしないんです。
ただ、実際やるとなると、これがすごく難しい。ドラマティックじゃないからオーバーな演技は絶対できないし、どうしようかと。入学させといてシゴく学校、みたいです(笑)。
―― 一番の課題はどんなところになりそうですか。
この戯曲ってステーキの国の人が書いたとは思えないくらい淡白で、すごく抑制が効いているんですよね。ここでもっと泣かせちゃえばいいのにってところで寸止めしちゃうし、途中で舞台監督が「ここで何年か飛ばします」みたいなことを差し挟んだり。だから演じる方にはアクセルの踏みどころが与えられていないんですよね。車で言うなら100kmで全力疾走したいけどいつも60kmを走ってなきゃいけないみたいな感じがします(笑)。また、なんでもないようなせりふにも、その一文字一文字がまるで立体になっているような奥行きがありますからね。これをどう伝えるかという大変さもあります。
一幕のはじめの方に新聞配達の男の子が出てくるんですが、そこでやっぱり舞台監督が「今の子はすごく優秀で、将来いい大学を出るんだけど、戦争で亡くなってちゃって……」っていうような紹介をするんですね。僕はそこに出てくる「あれだけの教育も全部、消えてしまった」ってせりふが好きで。さりげなくポッと言われるその瞬間に一本の映画が撮れそうな内容が詰まっている。すごく出汁が利いていますよね。テレビドラマ版の舞台監督役のポール・ニューマンさんは、まるでなんにもしてないみたいに淡々とした演技をしていました。だけどそれは演技以前にその人が人間として何を見てどう感じてきたかという経験が出ちゃう方法で、実はとっても難しいんです。でも確かにこのお芝居こそ、そういう経験が出てこなくちゃつまらないとも僕は思います。
――舞台上で演じられる「経験」と演じ手自身の積み重ねてきた経験が一緒になって、さらに本番では、お客様の人生とも出会っていくんですね。
演技も大げさじゃないし、暑くもなく寒くもなく、爆笑じゃないけど笑えるし、号泣じゃないけどちょっとグッとくる芝居というのは、観ていて気持ちいいと思いますよ。登場する町の人たちの年齢幅もあるので、若い人は「あぁそうか、いずれは自分も結婚したり、子どもを持ったりして、死んでいくんだ」と思うでしょうし、僕くらいの年齢より上の人たちは「そうなんだよ、人生ってね。アメリカでも同じだなぁ」なんて思ったりするかもしれない。それと、この舞台は舞台装置がないですから。ないことの自由さも楽しんでいただけると思います。
僕の体験でいうと一人しゃべりで面白かったバカ話をコントにすると色がさめることがあるんです。「この前電車の中で変なおばさんがいて」って話だけを聞くと、毛皮着てるおばさんを想像する人もいれば、もっとお気楽な格好の人を思い浮かべる人もいるんだけど、それを具体的に目に見える役柄にしちゃうと「あれ?」って。でも今回は町の様子からして「向こうが線路で……」と言葉で言うだけですから、想像できる楽しみがある。小道具もほとんどないんですよ。そのぶん役者も裸にされちゃうというか、またしても力量を問われちゃうんですけど。
この町をよく知って、愛して。僕の役目はそこからです。
――舞台監督役は進行を担うこともあり、作家のワイルダーにもっとも近い存在だと言われているようです。
面白い役ですよね。登場人物の一人に変身して店のおじさんの役をやったりもするし。出演者なんだけど、お客様とのあいだにも立つ客観的な人。それも例えば「街を見守るエンジェル」みたいなものとは違うんですよ。「こんにちは」って出てきて「この舞台の制作は新国立劇場、演出は宮田慶子……」なんて言うんです。僕はそれがちょっとおっかなくて。だってこれアメリカの話でしょう。なのに僕はそこで「なんなのこれ?」とかじゃなくて、「あれ、なんか面白いな」って思ってもらわないといけないんですよね。このことを考えるたびに、毎晩辛い気持ちになります(笑)。ただ、ここに限らず、せりふって自分が言うんじゃなく言わせてもらうものですから。例えば手を握るシーンがあったとして、どうして握るかというとそれは、相手の人に握りたくさせてもらっているから。そう思えば気持ちは楽になります。確かに今回は案内役でもあるので「相手」と呼べる人はいない。でもよくよく考えたら舞台全体にせりふを言わせてもらうことはできるんじゃないかな。
――まずは「わが町」を知った上で案内役になるわけですね。
そう。舞台監督はこの町のことをすごくよく知ってて、愛している人なんですから。彼は毎日の生活の「朝のパン、おいしかったな」ってくらいのことがいかに素敵なことかも全部知っていて、同時にみんながそれに気がついていないことも分かってる。でもだからって「分かってないな」って突き放すわけでもなくて「そうなんですよね、こうやって生きていくんです、人ってね」って、なんだか手の中でヒヨコをあっためているような感じでこの世界を見ているんだと思います。その視線がいちばん最後の「おやすみなさい」ってせりふになり、「じゃあ、あとは帰り道やおうちで考えてみてください」っていうふうな空気につながるんですね。僕イソップの「北風と太陽」の話が好きなんですけど、それを思い出しました。風を吹かせて無理やり旅人の服を脱がせようとするんじゃなく、太陽がぽかぽかあたためると自然に脱いでくれるっていう……この本も似てますよね。そんなに主張はしていないように見えて、実はすごく人に影響を与えているんです。