
シェイクスピア大学校
『ヘンリー六世』上演記念 シェイクスピア大学校
6回連続講座
芸術監督:鵜山 仁
監修:小田島雄志 河合祥一郎
V シェイクスピアとジャンヌ・ダルク ―ナショナル・ヒストリーの曙― 佐藤賢一(作家)
2009年11月18日[水]
Topにもどる→
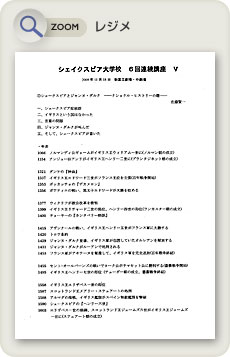 [佐藤賢一氏登場](拍手)
[佐藤賢一氏登場](拍手)
どうも、こんばんは。佐藤賢一といいます。私は、先ほどご紹介いただいたように本業は作家をしております。英文学専攻でも文学専攻でもなく、学生時代は、歴史畑の人間でした。今も、フランス史に材を採りながら、小説を書くようなことをよくしております。
ですから、『ヘンリー六世』のお芝居の流れからしますと、何だか居心地が悪いと言うか、敵地に来ているような緊張感もちょっと覚えてしまうんですけれども(笑)。
何事もスパイスが大事だと言いますか、イギリス専門、文学専門、シェイクスピア専門でないからこそ、ラインアップのなかに変り種が混じるからこそ面白いということもあるのかなと思って、今日はこの講演をお引き受けいたしました。
題は、「シェイクスピアとジャンヌ・ダルク―ナショナル・ヒストリーの曙―」としてお話させていただきます。
『ヘンリー六世』と言いますと、みなさんご存じのように、背景となる歴史は、百年戦争と薔薇戦争ということになります。
百年戦争というのは、中世の末、14世紀から15世紀にかけて、イギリスとフランスの間で戦われた戦争です。薔薇戦争は、その後に続いたイギリスの内乱ということになります。正確にはイギリスではなくてイングランドと言うべきなのかもしれませんが、今回は、あえてなじみの深いイギリスというふうに呼んで話を進めたいと思います。その薔薇戦争は、イギリス王家のお家騒動と言っていいと思います。
そのうちの特に百年戦争をメインに話したいのですが、これは、イギリスとフランス、どちらが最終的に勝ったのか、会場のみなさん、ご存じでしょうか?
西洋史は詳しくない、あるいは興味もないとおっしゃられる方もいるかもしれないのですけれども、試みに世界史の教科書を開いてみますと、一応はフランスの勝ちになっているようです。
ここで、ついでですから、あらましを確認しておきますと、フランドルの羊毛貿易問題、ボルドーのぶどう酒の貿易問題ですね、それから南フランスのアキテーヌ公領という広大な領地の領有問題、さらにフランス王位の継承問題、そういったたくさんの争点がからんで始まった戦争です。長短の休戦を挟みながら、1338年から1453年まで115年間も続いた戦争で、文字通りの百年戦争 英語で言うThe Hundred Years War、フランス語で言うLa Guerre de Cent-Ans。序盤は圧倒的なイギリス優位で進みました。1346年のクレシーの戦い、とりわけ1356年のポワティエの戦いに大勝して快進撃の立役者となったのが、かの有名な“ブラック・プリンス”黒太子エドワードです。そのエドワードの活躍もあって、イギリスが最初はもう圧倒的に勝つんですけれども、この劣勢を一回フランスは逆転して取り返すんですね。14世紀から15世紀の替わり目にあっては一度休戦期を迎えて、これで戦争が終わるかなという感じもありました。ところが15世紀に入って、再びイギリスがフランスに乗り込んできます。それで国土の半ばを占領されてしまい、フランスは国家存亡の危機に追い詰められます。
そこで、現れるオルレアンの攻防というのが起こります。1428年から29年にかけて行われた包囲戦ですね。そこでオルレアンが陥落してしまえばもうフランスに勝ち目はない、イギリスに全部制服されてしまうしかないという、そういう場面に突如現れたのが、救世主、当時の呼び方ではla Pucelle、乙女というような言い方ですね、そういう名前で出てくるんですけれども、つまりはのちの有名人、ジャンヌ・ダルクなわけです。
ジャンヌ・ダルクのおかげで、イギリスを祖国から追い払い、フランスは自分の国を守り輝かしい勝利をおさめるというのが、百年戦争の一般的なオチになっているかと思います。おおざっぱに言いますと、最初は黒太子エドワードでイギリスが勝つ、最後はジャンヌ・ダルクでフランスが勝つ。これが一般的な歴史の捉え方になっているかと思うんです。
私自身、世界史の教科書を読んでもそうですし、またいろいろな書物を読んでも百年戦争はフランスが勝つということになっていますから、それが史実として間違いないんだろうなと長い間思っていました。ところが、これがイギリスでは違うということなんですね。つまり、百年戦争の勝者は、イギリスでは、フランスでなくイギリスだと思われているんです。それが、国民のコンセンサスになっているんですね。もちろん、歴史学者、専門の方は歴史の動きを熟知していますから、そんなことはないとわかっていますが、ところが一般の人々はイギリスが勝ったと思ってしまう。
それはなぜかと言いますと、1990年に『百年戦争』という本を書いたロビー・ネイランズという人がいて、その人の著書から引用しますと、“百年戦争の歴史を紐解こうとすれば、まずもってイギリスの読者は心理的にシェイクスピア症候群と折り合いをつけなければならない”からだそうなんですね。
つまりシェイクスピアというものが、イギリス人の歴史認識にすごく関わっているらしいということがわかってきたわけです。
それは具体的にどういうことかと言いますと、シェイクスピアは、今回の『ヘンリー六世』だけでなく、多くの史劇を残しています。その中でも『リチャード二世』や『ヘンリー四世』『ヘンリー五世』、今回の『ヘンリー六世』、さらにシェイクスピアの作品ではないかといわれたような『エドワード三世』まで合わせると、シェイクスピアの歴史劇だけで百年戦争の経過を追えるぐらいの数があるわけですね。そうしてみますと、イギリスでは、小難しい歴史の教科書よりもシェイクスピアのほうがよほど読まれている。この読まれているシェイクスピアが書いた歴史像というものが、イギリス人の歴史観にも非常に大きな影響を及ぼしている。そう言われるとすごくわかるような気がするんですね。