
![]()



![]()

三浦雅士 Miura Masashi
ベンジャミン・ブリテンの作曲した『パゴダの王子』は20世紀のバレエの歴史において不思議な位置を占めている。すでにジョン・クランコが1957年に、ケネス・マクミランが89年に振付けているわけだが、決定版として繰り返し上演されているわけではない。いわば決定版への途上にある作品なのだ。
クランコとマクミランがともに、英国バレエの創始者とも言うべきニネット・ド・ヴァロワ女史のふところから巣立ったことは広く知られている。むろん、芸術家のことである。和気藹々というわけにはいかなかっただろうが、ド・ヴァロワにとって二人の成功が喜びであったことは疑いない。母親に似た思いだっただろう。二人の上の世代に、アシュトンとチューダーがいて、ド・ヴァロワに対して反抗的だったチューダーがアメリカに渡ってABTの設立にかかわり、結局、アシュトンがド・ヴァロワの、ということはつまりロイヤル・バレエの後継者になったこともよく知られている。
このアシュトンが、1950年代に頭角を現わしてきた若きクランコとマクミランを嫌って、60年代に入るやいなや、クランコをシュツットガルトに、マクミランをベルリンに追いやったと言えば、話を面白くしすぎることになるだろう。だが、そう理解しても必ずしも見当違いでないのは、アシュトンにそんなつもりはまったくなかったにせよ、ロンドンを離れた二人がそこで奮起することになったのは事実だからである。とりわけシュツットガルトでのクランコの活躍は目覚ましく、そこからノイマイヤー、キリアン、フォーサイスらが巣立つことになる。
マクミランはやがてロンドンに戻るわけだが、1973年のクランコの死後、本拠地のシュツットガルトはクランコのミューズだったマルシア・ハイデが守り、ノイマイヤーはハンブルクに、キリアンはハーグに、フォーサイスはフランクフルトにと散って、ヨーロッパの活気あるバレエ団はすべて、いわばド・ヴァロワの子や孫で占められることになった。そういう状況が2、30年ほども続いたのである。あるいはいまも続いていると言っていいかもしれない。ド・ヴァロワ直系のビントレーはもちろんのこと、キリアンのもとに育ったドゥアトも、ノイマイヤーのもとに育ったマイヨーも、大局的には同じ流れのなかにあると見ていいからだ。
ちなみにド・ヴァロワは1898年、アシュトンは1904年、クランコは27年、マクミランは29年生まれで、みな故人。いまなお旺盛な活動を続けているノイマイヤーは42年、我が新国立劇場・舞踊芸術監督のビントレーは57年の生まれである。
クランコの『オネーギン』、マクミランの『マノン』、ノイマイヤーの『椿姫』、いまではこの三つのバレエが、チャイコフスキー、プティパによる往年の三大バレエ『白鳥の湖』『眠れる森の美女』『胡桃割り人形』に代わりつつあるという見方さえ出ているほどだが、ド・ヴァロワにしてみれば喜ばしい限りだろう。これに三人三様の『ロミオとジュリエット』を付け加えれば、20世紀前半のバレエ芸術はディアギレフのロシア・バレエで保ったが、後半はド・ヴァロワのロイヤル・バレエで保ったということになるのである。
だが、そのド・ヴァロワにも叶えられなかった望みがひとつだけあって、それが『パゴダの王子』なのだ。『パゴダの王子』は、イギリスではパーセル以後はじめて登場した大音楽家と言われるブリテンが作曲した全幕物バレエだからである。それがどうしたと言われそうだが、作曲も振付もイギリス人による全幕物バレエが世界中で長く踊られるようになること、つまり『パゴダの王子』が『眠れる森の美女』に取って代わることこそ、ド・ヴァロワの悲願にほかならなかったのだ。途上にある作品では困るのである。
周知のように、クラシックの黄金時代を築いたドイツ、オーストリアには有名なバレエ曲がひとつもない。長年、音楽は芸術だが、舞踊は娯楽であるとして軽蔑してきたからだろう。イサドラ・ダンカンがベートーヴェンの音楽で踊ったとき轟々たる非難が巻き起こったのは有名な話だ。楽聖を汚したというわけである。したがって、振付家はもちろん、バレエ音楽の作曲家も出るわけがなかった。たとえばミンクスはオーストリア出身だがロシアでしか仕事ができなかった。『コッペリア』のドリーブはフランス人、『白鳥の湖』のチャイコフスキーはもちろんロシア人である。20世紀に入ってからもこの傾向は変わらず、ラヴェルもミヨーもフランス人で、ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチはロシア人。ドイツはともかく、イギリスにも作曲家はいないのか。アシュトン、クランコ、マクミランと、振付のほうはイギリス人でどうにかできると思いはじめたド・ヴァロワが、胸中深くそう嘆いていたとしても無理はない。その眼前に登場したのがブリテンにほかならなかったのである。
ブリテンは1913年生まれ。十代の頃から天才少年として注目されていたが、その名が世界中に広まったのは、1945年、オペラ『ピーター・グライムズ』が大成功を収めてからである。ブリテン、弱冠32歳。その後、堰を切ったように『ルクリーシアの凌辱』、『アルバート・へリング』、『ねじの回転』と傑作オペラを次々に書いてゆく。ド・ヴァロワが眼を付けないはずがなかった。
昔、武満徹と話していて、たまたまチャイコフスキーに及んだことがある。当時、知識人たるもの甘たるいチャイコフスキーは馬鹿にすべきという風潮があったのだが、驚いたことに武満さんはその風潮を断固否定し、オーケストレーションについて深く学ぶことがあったとおっしゃった。ブリテンはこのチャイコフスキーに似ている。管と弦と声が見事に溶け合ってじつに多彩な音色を浮かび上がらせるのである。安易な前衛に走ることなく、既成の管弦楽と人の声によって驚くべき革新を成し遂げたことでは、ショスタコーヴィチとブリテンが20世紀の双璧だろう。
そのブリテンを手に入れる手法が、まさにカラボス、いやリラの精なみに、ド・ヴァロワは巧みだった。画家のジョン・パイパーに若きクランコを紹介したのである。パイパーは1903年生まれ。奥さんのマイヴァンウィーは11年生まれ。この二人は南アフリカ出身のクランコを大いに気に入ってイギリスでの父母代わりになるのだが、パイパーは1930年代、詩人のオーデン、イシャウッド、スペンダー、そして音楽家のブリテンらが芸術家サークルを形成し、詩劇運動などを展開していたときの仲間のひとりだったのである。たとえばブリテンの41年のオペラ『ポール・バニヤン』の台本はオーデンである。ド・ヴァロワは大きく迂回してブリテンに接近しているのだ。
ブリテンの53年のオペラ『グロリアナ』の舞台美術を担当したパイパーが、そのバレエ部分の振付をクランコに依頼するようブリテンに示唆するのは、したがって、自然な成り行きだった。のみならず、その後にパイパーが、クランコの背中を押して『パゴダの王子』の作曲をブリテンに依頼するよう仕向けるのもまた自然な成り行きだったと言わなければならない。もちろん舞台美術はパイパーである。ちなみに54年、つまり『パゴダの王子』の3年前、いまも頻繁に上演されるオペラ『ねじの回転』の台本を書いたのはパイパーの妻、マイヴァンウィーその人である。73年の最後のオペラ『ヴェニスに死す』の台本もそうだ。『パゴダの王子』がド・ヴァロワに献呈されているのは、この展開の全体がド・ヴァロワの掌中にあったことを示唆していると言っていい。
こうしてみると、振付活動を始めたばかりの20歳前後のビントレーに、いずれ『パゴダの王子』の振付をしてみてはと囁いたというド・ヴァロワの手腕には感嘆するほかない。とはいえ、ド・ヴァロワの真意としては『パゴダの王子』は、言ってみればブリテンの代名詞にすぎなかっただろう。というのも、クランコの手になる『パゴダの王子』の台本は要素を詰込みすぎて、物語の首筋が、つまりなぜ事件が起こるのかというその肝心の動機さえよく分からないからである。訳の分からない物語に作曲されてしまったのでは、いくら音楽が美しくてもバレエとして成功するはずがない。ドーノワ夫人の童話「緑の蛇」は基本的に冥界下降譚であり、ブリテンはガムランの響きを模して冥界を描き、物語の元型にはよく応えているのだが、クランコのほうはそれに「美女と野獣」や「リア王」の要素まで注ぎ込んで逆に分かりにくくしているのである。クランコ、時に30歳直前。初の全幕物バレエの振付に興奮し有頂天になっていたと言われても仕方がないだろう。上演されなくなった理由だ。
伝記そのほかを参照するかぎり、ブリテンはマクミランには協力的ではない。たとえば曲の削除を許さなかった。マクミランもしたがって大筋ではクランコの物語を踏襲するほかなかったわけだ。マクミランがブリテンに接近するのは70年代で、76年に没するブリテンはすでに体力的に弱っていたからでもあるだろうが、しかしそれではブリテンはクランコには協力的だったのかと言えば必ずしもそうではない。むしろパイパー夫妻に親切だったのだと考えたほうが自然だろう。マクミランはその圏外にあったのである。
アシュトンがマクミランを疎外したように、マクミランはビントレーを疎外した。ビントレーはむしろアシュトンのほうに庇護された。人間関係は錯綜するが、いずれにせよこのような英国バレエの紆余曲折のなかに、ド・ヴァロワはそれでもブリテンの名がしっかりと組み込まれることを望んでいたのである。『パゴダの王子』の名をビントレーの耳に囁いたド・ヴァロワの真意はむしろこの若いコリオグラファーの脳裏にブリテンの名を刻む込むことにあったと言っていい。そのビントレーが日本の新国立劇場バレエの芸術監督に就任し、ほかならぬ『パゴダの王子』を振付けることになったのだから、ド・ヴァロワとしてはおそらく我が意を得た思いでいることだろう。ド・ヴァロワは2001年に102歳で没したが、ブリテンにとって日本がきわめて意義深い国であったことは熟知していたに違いないからである。
『パゴダの王子』はインドネシア旅行を反映してガムランを用いずにガムランの響きを現出させたことで世界を驚かせた。だが、ブリテンの仕事の全体に照らせば、その後の日本旅行のほうがはるかに重要である。ブリテンが1940年、日本の紀元二千六百年式典に依頼されて『シンフォニア・ダ・レクエイム』を作曲し、日本政府と悶着を起こしたことはよく知られている。祝典にレクエイムとは何ごとかというわけだが、事態は日米が開戦するに及んでそれどころではなくなってしまった。そのブリテンが、にもかかわらず第二次大戦後の56年、インドネシア旅行に続いて日本を訪れ、能と歌舞伎に魅了され、自身の音楽活動にその様式を積極的に取り入れることになった。音楽史上の重大事件である。
教会三部作と呼ばれる『カーリュウ・リヴァー(鷸川)』、『燃える炉』、『放蕩息子』がその成果だ。中世音楽を取り入れ、演奏の場をオペラ・ハウスではなく教会に移したのも能舞台の影響だが、『カーリュウ・リヴァー』は能「隅田川」そのものを原作にしている。ブリテンは、能という舞踊劇の骨格が冥界下降譚にあることを見抜き、物語はそのままにして舞台だけを東洋から西洋へと移したのである。古今東西を問わず、すぐれた舞台はすべて死すなわち冥界にかかわっている。思い返せば、『ピーター・グライムズ』も『ねじの回転』も『ヴェニスに死す』も例外ではない。ブリテンは自身の作品の必然的な流れに驚いただろうが、この覚醒こそブリテン晩年のいわゆる「東洋時代」の本質なのだと言っていい。
ブリテンと同じようにビントレーもまた天才である。たとえば『アラジン』には、ソロ、パ・ド・ドゥ、パ・ド・トロワ、パ・ド・カトル、パ・ド・サンク、パ・ド・シスのすべてが盛り込まれている。これはほとんど名人芸であって、こういう芸当は先に名を挙げた振付家の誰もしなかったことである。パの組み合わせと同じように、ビントレーは場面転換や装置によって観客を驚かすことにおいても卓越している。だが、ブリテンが能に見出した生と死のコスモロジー、『オネーギン』『マノン』『椿姫』にも等しく見出せる生と死の垂直な軸への強い関心についてはその限りではないのである。ビントレーはむしろそれを重苦しいものとして避けようとしているとさえ言っていい。名人芸の所以だが、コスモロジカルな軸なしに、見事なパをほとんど無限に紡ぎだす才能をこのコリオグラファーは持っているのである。例外はシュツットガルト・バレエに振付けた『エドワード二世』くらいのものだろう。ディズニー・ランドではないが、楽しい一晩を提供することこそ自身の務めであるとばかりに、ほとんど本能的にバレエを作り上げてしまうようなところがあるのだ。
だが、ド・ヴァロワの囁きに導かれるように、ビントレーはほかならぬ日本でブリテンと向き合うことになった。『パゴダの王子』の物語から枝葉末節を剥ぎ取り、冥界を暗示するに竜宮をもってしたのは、ブリテンの音楽によく応えるものだが、ことはそれだけではすまない。コスモロジーとはそんなものではない。ブリテンが、『パゴダの王子』の後に教会三部作によって日本体験を作品化したように、ビントレーもまたいずれ『パゴダの王子』の後に自身の日本体験を作品化しなければならないだろう。まさにブリテンを手がかりにして。それこそ、ド・ヴァロワが若きビントレーに囁いたことの真意に違いない。ド・ヴァロワの悲願は、イギリス最大の作曲家と最大の振付家が、世界中で末永く上演されることになる全幕物のバレエを作り上げることにほかならなかったのだから。
それが『カーリュウ・リヴァー』すなわち『隅田川』というバレエを作り上げることであるのかどうかは分からない。いずれにせよ、日本滞在の後、何らかの精神的飛躍なしにイギリスに帰ることはビントレーには許されない。このコリオグラファーがいま世界的に熱い視線で見守られなければならない理由である。見守っているのは亡きド・ヴァロワだけではないのだ。
『パゴダの王子』がその精神的飛躍の重要な契機になるだろうことを信じている。
(文芸評論家)
2011年「パゴダの王子」初演時プログラムより
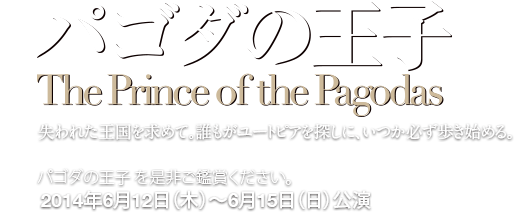
〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目1番1号
TEL : 03-5351-3011(代表)
東京都渋谷区にある新国立劇場は、
京王新線「初台駅」(中央口)から直結!
「新宿駅」から1駅です。