演劇公演関連ニュース
[後編]天狗の羽音~『斬られの仙太』の故郷を訪ねて~

絶賛上演中の『斬られの仙太』。
演劇新シリーズ「人を思うちから」の第一作目となる今作は、尊王攘夷を掲げて戦った水戸天狗党と時代のうねりを描いた、劇作家・三好十郎による超大作だ。
その故郷を巡る旅も後半戦。天狗党決起の場所である筑波山神社と主人公の出身地である真壁町を後にして、一行は水戸市内へ向かう。
目指すのは激戦地となった那珂湊反射炉跡、藩士たちの墓がある回天神社、そして劇中にも登場する那珂川だ。

昼食を終え、演出者・上村聡史さんと仙太役・伊達暁さんはまず、那珂湊反射炉跡へと向かった。
劇中にも激戦地として登場し、主人公である仙太もその合戦に参加したという場所だ。
住宅街を行くと、小高い丘の上に二本の煙突のような影が見えてきた。高熱で鉄を溶かしていたという巨大な炉だ。天狗党の乱の際に破壊されたものを、昭和に入って復元したものだという。それまで日本には青銅製の大砲しかなかったが、江戸時代後期に海外の技術が導入され、異国船に対抗するための鉄製の大砲をここで鋳造するようになったのだと伊達さんが教えてくれた。
作品の背景を調べることは役者にとって当然の作法なのかもしれない。しかし、今作に関する伊達さんの知識の深さにはたびたび驚かされる。こちらの疑問に資料も見ずに答える姿には、今作に対する意気込みが見えるようだ。
なにせ、日本史上でも最大数の人間が粛清されたという事件を扱うのだ。演じる側の重圧も相当だろう。
突然、敷地の看板に目を留めていた上村さんが「そう、そう、そう!」と声を上げた。
そこには、ここが「元治甲子の乱(天狗党の乱)」の戦地となり、多数の戦死者が出たことが記されていた。
「昭和になってから、やっと慰霊碑が建てられたんですね」
熱心に看板を読んでいた上村さんが小さく呟いた。
膨大な犠牲者数にも関わらず、この事件は教科書に載ることもなく歴史の中に埋もれている。
その理由を尋ねると上村さんは、
「中央(幕府)に与えた影響が少なかったからでしょうね」
と答えた。
時代と共に歴史的事実の解釈は変わり、その出来事が持つ意味合いも変わる。しかし、我々はそこに何らかの「答え」を見出して教訓としなければならない。
過去を紐解こうとするかのように、二人は看板の文字に目を走らせていた。

住宅街を抜けた車が、次の目的地を目指して田園の中を走る。
かつて仙太もまた、この景色のどこかで土を耕していたのだろうか。百姓が報われることを切に願った仙太は、その後、望まぬ戦いに参加していくことになる。
旅のテーマのせいか。田園の広がりはのどかでありながらも、不思議な感傷を抱かせた。
回天神社に着くころには午後の陽も弱くなり始めていた。低い鳥居をくぐるとすぐに白壁の蔵があった。鰊(にしん)蔵である。
乱後、捕えられた者たちは五十名ずつに分けられて蔵に幽閉されたのだという。蔵の数は十六に渡ったというから、捕えられた者は八百名近くいたことになる。
蔵内の衛生状況は劣悪で、明治維新により解放されるまでに斬死、病死した者の数は四百人とも五百人とも言われている。
その後、乱後五十年の折に調査されて素性が明らかになったのが、墓の建てられた三百七十一名である。それ以外の者たちは名前も家族も分からないまま、時代の裂け目に埋葬されている。
蔵の壁には血で書かれた絶筆が残されているそうだ。

蔵の横に出ると、墓石たちが凄然と並んでいた。
傾いた陽を浴びて、音もなく立っている。草むらの碑には「水戸殉難志士の墓」と書かれていた。
墓石はどれも簡素な作りで、その多くは長年の風雨のせいで名前も判読できない。その中にいくつか真新しい墓がある。犠牲者の子孫が新調したものだろう。
「読めないね」
墓石を覗き込んでいた伊達さんと上村さんが小さく言う。それでも読み取れる墓はないかと、身をかがめて歩いていく。夕暮れ近い光の中で、墓場は静寂だった。


墓地を抜けた道は那珂川のほとりへと通じていた。そこが旅の終着地点である。
河川敷は幅広く、草木が高く生えていて川面が見通せない。ようやく川原に下りる道を探し当てて土手を下りると、草陰の中に水面が見えてきた。
想像よりもはるかに川幅が大きい。
なみなみとした水が、曇天の下をとめどなく流れている。灰色に映る川水は冷たそうだ。
作中、大志を抱いた人々はこの川を泳いで渡り戦いに挑むのだという。それは並大抵のことではない。当時の人々のひっ迫した覚悟のようなものが窺い知れた。
「これを泳いだのか」
上村さんと伊達さんも川を目にした途端に驚きの声を上げた。
「この戦いを終えれば農民たちが救われると、仙太は信じてるんですよね?」
スタッフの問いかけに伊達さんが、
「信じていなきゃできないですよね」
と、川から目を離さずに答える。その隣で、やはり川を見ていた上村さんが、
「やっぱり、仙太は仲間意識が強いんでしょうね」
と、合点がいったような声で言った。主人公の輪郭を、より鮮明に掴んだのかもしれない。


「お墓を見たときに、百姓の墓がないことに気づきました。時代背景的には当然のことなのかもしれないけど、何とも言えない感情を覚えました。石に名前が刻まれない人がいる、そのことについて考えさせられる旅でした」
川のほとりで旅の感想を尋ねると上村さんは答えた。続けて、
「あとはやっぱり山の大きさですね。ダメ出しで『もっと山を感じたい!』って繰り返すかもしれません」
と、冗談交じりに笑った。真壁町で見た雄大な景色はそれだけ印象的だったのだろう。
対する伊達さんは、
「実際の場所を巡って得たものが、どのように自分の身体に沁み込んでいるのか。それはこれからの稽古で感じたいと思います」
と、旅の行程を思い返すようにゆっくり語った。それから、
「ただ、仙太の信じたものを、間違うことなく届けられたらいいなと思います。仙太は『百姓のために』と、一見すると甘い理想のようなことを言うんですよ。でもそれは現代にも通じる"良心"でもあると思います」
「その"良心"が面白く、かつ輝かしく伝わればと思いますよね」
上村さんが言い添えると、伊達さんは無言で頷いた。
「人間性とか"良心"って、ヒトの世界から少し離れてみて、景色や風景と対峙したときに芽生えるものなんだと思います。心穏やかに世界や社会と対峙していくヒントがそこにあるような。『土』というキーワードを持つ今作を、コロナ禍で苦しむ現代に届けるのは意味があることだと思います」
上村さんが語る横で、伊達さんはちらちらと川面に目をやっていた。仙太の見た景色を焼き付けようとしていたのかもしれない。

こうして『斬られの仙太』の故郷を巡る旅は終わった。
旅の最中、上村さんは常に俯瞰で観察しているようだった。目的地に着いても一歩引いて、その全貌を確認しているように感じた。いつか舞台上に再現するために、その場の全てを見ていたのだろうと思う。
対する伊達さんは場所の中をぐんぐん歩いていた。測量でもするかのように大股で歩き回り、時折立ち止まって、やはり測るかのように自分がさっきまでいた場所を振り返ったりしていた。
もうじきに、今度は舞台上でここを歩く―。
その日のために、もしかしたら本当に測っていたのかもしれない。
あの山の、田園の、川の、物言わぬ墓石たちの息吹を、演出家と役者は自身の中に取り込んだ。違った目線で、しかし同じ目的のために。それは大いなる風となって舞台上から届けられるだろう。
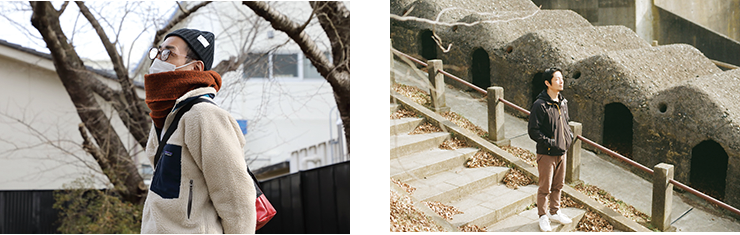

文 フリーライター本田 潤
<前編はこちらから>
- 新国立劇場HOME
- 演劇公演関連ニュース
-
[後編]天狗の羽音~『斬られの仙太』の故郷を訪ねて~