演劇公演関連ニュース
NTL×新国立劇場 コラボ企画 フルレポート公開!

ナショナル・シアター・ライブ『誰もいない国』の再上映に際して、コラボ企画として行われたトークイベントのフルレポートです。
ゲストスピーカーの喜志哲雄さんは、日本におけるピンター研究の第一人者。今回のナショナル・シアター・ライブ『誰もいない国』の映像の日本語訳や11月に行われる新国立劇場演劇公演の翻訳も手掛けています。
書かれた当時のロンドンや、ピンターの文体のことなど、作品の理解を深める楽しいトークとなりました。
(進行:大堀久美子)
大堀 イギリス、ナショナル・シアターでの公演を収録上映している今回の『誰もいない国』。イアン・マッケランとパトリック・スチュワートという、人気、実力ともに長年トップクラスにいる俳優二人が、本当に、バトルのような火花散る演技を見せている作品です。
作者であるハロルド・ピンターは、日本でも上演機会の多い劇作家ですが平らな言葉で言えば、「わかる」ということをなかなか観客に許してくれない劇作家、とも言えそうです。
ピンターの研究家で、翻訳家でもいらっしゃる喜志先生をお迎えし、作品や作者について鑑賞の助けとなるお話をいただきたいと思います。
喜志 ピンターは1930年生まれです。最初は役者だったわけですが、 1950年代に入って劇作を始めた当初は「わからない」という評判が大変多かったようです。
少し理屈を申しますと、いわゆる近代リアリズム劇、これは「わかる」劇なんですね。誰かがある行動をするには、どういう動機があるのかわかる。それから、台詞が語り手の心理なり感情なりを正確に伝える。そういう点でピンターはほとんど革命的なことを起こしました。
しかし、それから50~60年ぐらい経った今では、「わからない」とはあまり誰も言わなくなった。つまり、現実の捉え方、それから言葉の使い方について、ピンターがほとんど1人で革命みたいなことを起こしたのです。
今日上映する『誰もいない国』も、決して古い意味での「わかりやすい」劇ではありません。ですが、それでいて面白い。
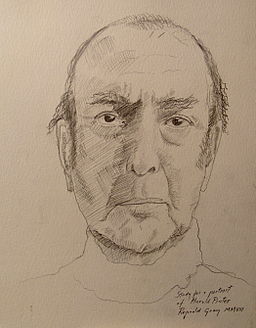
ハロルド・ピンター 肖像画
喜志 ピンターが、あるところで、自分の作品を解説したことがあります。人間は、自分の過去、家族構成、職業なんかについて、全部を印刷した名刺を持ち歩いているわけではない。また、誰かがある行動をとるという場合でも、時によっては、その当事者自身がなぜそれをやったかわからない。むしろこれが普通である、と。
それから、台詞のことをちょっと解説したいと思います。たとえば、"What"つまり「何だって?」という言葉。これは普通、相手の言ったことがよく理解できなかった、あるいは相手の発言がよく聞き取れなかった、そういう意味に解釈するわけですね。ところが、ピンターの戯曲では、ある人物が自分の立場を不利にしないために、自分をいわば守るために時間稼ぎに使われている。
また、ピンターの作品では、登場人物がものすごい長台詞をしゃべる。それは相手に何かを理解させるわけじゃなくって、相手を混乱させるために話している。つまり言葉というものを、意味の伝達手段としてよりも、人間と人間との交渉において一種の武器として使う。そして、こういうことが実際にはあります。別に、ピンターは哲学者ではありませんから、理論的には言いませんけれども、そういう使い方をし始めたのです。
喜志 『誰もいない国』ではハーストという60代の詩人のところへ、パブで会ったスプーナーという、これもやはり60代の詩人らしい男がやってくる。この応酬が実に面白い。決して素直な意見交換ではないんです。必ずしも友好的でもない。その辺はたっぷりご覧ください。終わりがどうなるかってこと、あまり気にしないほうがいいと思うんですね。
大堀 確かにそうですね。日本のお客様は真面目で熱心でいらっしゃるので、見たものに関して、自分なりに着地点がはっきりしないとモヤモヤされる方が多いかもしれません。ことピンターの作品に関しては、1つの帰結ということではなく、受け取ったままの感情でお帰りいただくのが、楽しみ方として正解なのかなという気がします。
 大堀 先生は、非常に若い頃からピンターの作品に惹かれ、翻訳を手掛けていらっしゃいましたが、喜志先生にとってのピンターの魅力は、どういうところにあるのでしょう。
大堀 先生は、非常に若い頃からピンターの作品に惹かれ、翻訳を手掛けていらっしゃいましたが、喜志先生にとってのピンターの魅力は、どういうところにあるのでしょう。
喜志 やはり言葉ですね。ある本に書きましたが、61年に初めてイギリスへ行って、『管理人』を見たんです。こういう言葉というのは聞いたことがなかった。その前年に、私はアメリカで見た、エドワード・オールビーの『動物園物語』にものすごい衝撃を受けたわけですが、ピンターの衝撃はそれよりも大きかった。
『誰もいない国』では、スプーナーという人間がハーストに誘われてやってくる。この2人の関係が途中で微妙に変わるんです。ここが見どころだと思います。
スプーナーはハーストに対して、3通りぐらいの文体でしゃべる。最初は、非常に丁寧な、ややこしい、ラテン語系の語彙がたくさん使われ、複雑な構文になってる。これはわからないでもない。つまり緊張しているんだと思うんですね。初めて会った、誰だかわからない、何されるかわからないという警戒心がある。そこで、なるべく自分は安全な立ち位置を探り探り、卑屈になったり、居丈高になったりする。
それからだんだん親しくなって、普通の会話をするようになる。2幕になって、パトリック・スチュワートが演じるハーストというのが、1幕とはだいぶ様子が変わって出てきます。二人は、40年以上前、おそらく、オックスフォード大学で同級生だったかもしれない。ここは、ものすごくくだけた学生言葉みたいな、短い単語が続く文体でしゃべる。この変化が面白いんです。しかもイアン・マッケランという大名優がその辺りを使い分けています。それから、表情とか、仕草、身振り、つまりテキストを読んだだけではわからない2人の演技を是非ご覧ください。大変面白いんです。
大堀 本当に1幕と2幕では、まるで違う芝居ではないかというほどテイストが変わっていて、それぞれの立ち居振る舞いもどんどん変わっていく。一体この人たちの真意はどこにあるのか、ドラマが複雑で、何層にもなっていくように感じました。
さらには、ちょっと下卑たというか赤裸々な話も出てきて、一体この人達の会話はどこへ行ってしまうんだろうという、かなりスリリングな展開になりますよね。そこがまた、味わいどころというか楽しみどころだと思うのですが。

ハムステッド・ヒース
喜志 この芝居全体に、男性の同性愛、ホモセクシュアリティ、という雰囲気が漂っています。ただ、この4人の登場人物が実際にゲイかどうか、特にハーストの家に、ブリグズという中年男と、フォスターという若い男がいて、彼らがどういう関係か、はっきり書いてありません。なので、非常に親密な関係かもわからないが、しかしそうだという確証はない。
私は、1975年初演の翌年に見たんです。それで、77年に翻訳が出ました。戯曲の中に、ハムステッド・ヒースというロンドンの西北辺りにある公園みたいなところやジャック・ストローズ・カースル、というパブが出てくる。これは19世紀からあったんだそうですが、75年当時は、これは有名なゲイバーだったのだそうです。翻訳が終わってからこれらを知りました。まあ知らないよりはいいですね。
この映像が面白いのは、ライブですから、観客の反応も感じられるところです。私は何度かこの作品を見ていますが、「ハムステッド・ヒースをうろつくかどうか」とか言うと、お客がクスクス笑ったりするんです。ハムステッド・ヒースは、クルージングというんですか、ゲイの人が行きずりの相手を見つけてさまよう、そういう場所なんだそうです。
文体の話に戻りますが、最初のややこしい文体は、どうもそういう(男性同士の)題材について使われているような気がする。それから、2つ目は、男女の結婚生活。それから第3のふざけた文体というのは、不倫など婚外の男女関係。これは多分誰も言ってないと思うので、絶対正しいという自信はありませんが、どうもそうじゃないかなという気がします。その辺りも見どころだと思いますね。
 大堀 この『誰もいない国』が、11月に新国立劇場で上演されることになっております。こちらの戯曲の翻訳も喜志先生が手がけていらっしゃいます。最初に訳されたのはだいぶ前かと思うのですが、今回この舞台のために手を加えられたところはありますか。
大堀 この『誰もいない国』が、11月に新国立劇場で上演されることになっております。こちらの戯曲の翻訳も喜志先生が手がけていらっしゃいます。最初に訳されたのはだいぶ前かと思うのですが、今回この舞台のために手を加えられたところはありますか。
喜志 これは私の持論ですが、出版するための翻訳と上演のための翻訳は別ものであると思っています。つまり、本を読むのと耳で聞くのは違いますから、今では古い言葉や表現なんじゃないかというのも出てきます。
それから、もう全部しゃべってしまいますけども(笑)、私は今回イアン・マッケランが演じているスプーナーをジョン・ギールグッド、それからパトリック・スチュワートがやっているハーストをラルフ・リチャードソンという、当時の大名優が出演している舞台を見ております。これは私の翻訳家としての経験では非常にまれな例なのですが、この舞台が耳に残っていて、それを再現したつもりなんです。だからギールグッドの非常に粘っこい、絡みつくような物言いを再現したつもりなんですね。
ところがちょっとこれは訳し過ぎだったのではないかと、今、反省しております。今回のは寺十吾(じつなし・さとる)さんが演出してくださる。実は今、寺十さんと上演台本を作っていて、明日もまた打合せをします。楽しみにしてください。
 大堀 ハーストとスプーナーを柄本明さんと石倉三郎さんが演じます。存在感と、作品にくさびを打つような演技という意味では、こんなにふさわしいお二人は、今、いらっしゃらないのではないかと思います。
大堀 ハーストとスプーナーを柄本明さんと石倉三郎さんが演じます。存在感と、作品にくさびを打つような演技という意味では、こんなにふさわしいお二人は、今、いらっしゃらないのではないかと思います。
喜志 大変楽しみにしております。俳優の中には古いリアリズムに捕らえられている方もいて、この台詞を語る動機は何なのかとか、ともすると考える。今回のお二人がその辺をどうされるか、それが非常に楽しみですね。ちなみに、これはご覧の方もあると思いますが。石倉さんは5年前ぐらいですかね、もっと前かな、サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』という舞台に出演されました。(※編注:2011年上演)
柄本さんは、私、かなりいろんな作品を見ていましてね。お二人とも古い意味でのリアリズムに捕らえられている俳優さんたちではないので、お二人のやり取りが非常に楽しみです。翻訳者として言うのはどうかと思いますけども、皆さんも期待されていいんじゃないかと思います。
大堀 これまでの上演や作家のイメージにとらわれない舞台が新たに生まれるという意味でも、期待できる作品になるかと思います。一演劇ファンとしてとても楽しみです。喜志先生がくださったヒントとともにご覧いただけば、この作品に「わかる」というアプローチではなく、より「近づいていただける」のではないでしょうか。ありがとうございました。
プロフィール
喜志哲雄(きし・てつお)
京都大学大学院修了。京都大学教授を経て、現在、京都大学名誉教授。専門は英米演劇。著書に、『劇場のシェイクスピア』『英米演劇入門』『喜劇の手法 笑いのしくみを探る』『シェイクスピアのたくらみ』『ミュージカルが<最高>であった頃』『劇作家ハロルド・ピンター』など多数。ほかに、ヤン・コット、ピーター・ブルック、『ハロルド・ピンター全集』など、翻訳も多い。新国立劇場では2012年上演のピンター作『温室』の翻訳を手がける。
- 新国立劇場HOME
- 演劇公演関連ニュース
-
NTL×新国立劇場 コラボ企画 フルレポート公開!