ジョン・ランチベリー
アシュトンはよくイギリスのラジオ番組を聴いていた。初めてプロコフィエフの『シンデレラ』のなかの曲を聴いたのもラジオでだったと、私に語ったことがある。そしてその曲に創作意欲をかきたてられた彼は、1948年に初の全幕バレエ『シンデレラ』(現代イギリスの振付家による初の全幕バレエでもあった)を完成したのだった。物語のロマンティックな性格と、スコアからはっきりと読みとれるように、プロコフィエフの音楽が王子とシンデレラの恋に重点を置いていることにアシュトンは強く引きつけられ、このバレエは霊感に突き動かされるようにすぐに出来上がった。 彼はプロコフィエフの音楽の第3幕に手を入れ、ロシアで上演された初演版では王子が世界中を延々と旅する場面となる部分をカットした。私が思うに、アシュトンはこの部分を“各国の”踊りを挿入することだけが目的の音楽と考えたのだ。 そのためアシュトン版の第3幕は短く、主に物語をハッピーエンドに導く役割を果たしている。それ以外の部分ではアシュトンは原曲の構成を守っており、ところどころで作品を“引き締める”ための短いカットを行なっているのみだ。
1948年にこのバレエが初演されたとき、私は英国王立音楽院を卒業して、初めてプロフェッショナルな契約を結ぼうとしているところだった。その仕事とは、コヴェントガーデンの国立バレエ団とは似ても似つかない、小さなイギリスのバレエ団の音楽監督だった。私が初めてアシュトンの『シンデレラ』にかかわったのは1958年のことで、その頃私はサドラ一ズ・ウェルズにあるロイヤルバレエの “ジュニア”部門で働いていた。 バレエ団の芸術監督二ネット・ド・ ヴァロワが突然、私にコヴェントガーデンで3公演の『シンデレラ』を指揮するようにと言ってきたため、大急ぎでスコアを学ばなくてはならなかった。そして私はこのバレエが好きになり、翌年、コヴェントガーデンのロイヤルバレエの首席指揮者に招かれたのだった。1965年に『シンデレラ』が再演されたとき(そのころには、私は彼に頼まれて何曲ものバレエを編曲していた)、アシュトンは私に善良な妖精(仙女)のソロの音楽 (彼はこの曲を「キリギリスと蝶々」 と呼んでいた) がどうしても気に入らないので、もっといいものを探してくれと言った。そこでプロコフィエフのピアノ曲を検討し、『東の間の幻想』から1曲を選んで、プロコフィエフ自身がこう作っただろうと思えるような管弦楽曲に編曲した。アシュトンはそれを気に入り、今日までその曲が使われ続けている。
プロコフィエフは効果的な管弦楽法をよく知っていた。『シンデレラ』のスコアにはその実例がたくさん見られる。「スル・ポンティチェッロ」(ヴァイオリンの弓で駒く楽器の胴の上で弦を適切な高さに支えている部分)の近くを弾いて、ひっかくような音をたてること)で義理の姉たちの不機嫌を表現し、トロンボーンのどっしりしていて柔らかい低音の和音で父親の悲しみを、ほぼ全音域にわたって穏やかに上昇と下降を繰り返すクラリネットで倦怠感を誘う夏の暑さを表現している。そして王子が到着する場面では、舞台外からのファンファーレとオーケストラの演奏が、異なる調性と拍子で同時に行なわれる。こういった手法のなかで最も効果的なのは、おそらく真夜中を告げる大時計のぞっとさせるような、執拗に続くチクタクという音だろう。そしてユーモア好きのプロコフィエフは、バレエ曲『ロミオとジュリエット』で自作の「古典交響曲」を引用したのと同じように、『シンデレラ』のなかでも自作のオペラ『三つのオレンジへの恋』の曲を使っているのである。
訳・森 類子
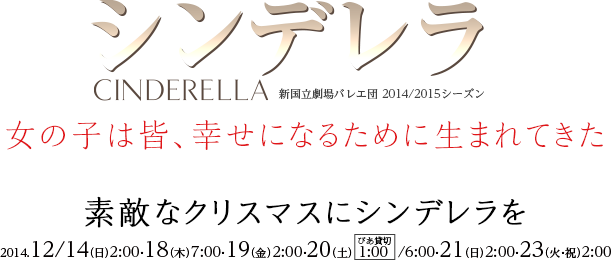
〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目1番1号
TEL : 03-5351-3011(代表)
東京都渋谷区にある新国立劇場は、
京王新線「初台駅」(中央口)から直結!
「新宿駅」から1駅です。