|
|
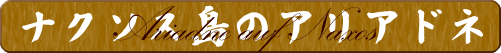 |
R.Strauss:Ariadne auf Naxos
【プロローグ付全1幕】<ドイツ語上演/字幕付>
オペラ劇場 OPERA HOUSE |
| <スタッフ> |
| |
| 台本 |
:H.v.ホフマンスタール |
| 作曲 |
:R.シュトラウス |
| |
|
| 芸術監督 |
:五十嵐喜芳 |
| 指揮 |
:児玉宏 |
| 演出 |
:ハンス=ペーター・レーマン |
| 公演プロデューサー |
:栗林義信/曽我榮子 |
| 演出補 |
:ザビーネ・ゾンターク |
| 美術・衣裳 |
:オラフ・ツォンベック |
| 舞台監督 |
:大澤裕 |
| 副指揮 |
:城谷正博/藤本潤 |
| 演出助手 |
:古川真紀 |
| 管弦楽 |
:東京フィルハーモニー交響楽団 |
| |
|
| 主催 |
:新国立劇場/二期会オペラ振興会 |
|
| <キャスト> |
| |
| 2002年12月 |
12日
(木) |
13日
(金) |
14日
(土) |
15日
(日) |
| 執事長 |
米谷毅彦 |
★ |
★ |
★ |
★ |
| 音楽教師 |
小森輝彦 |
★ |
|
★ |
|
| 黒田博 |
|
★ |
|
★ |
| 作曲家 |
手嶋眞佐子 |
★ |
|
★ |
|
| 白土理香 |
|
★ |
|
★ |
| テノール歌手/バッカス |
ヴォルフガング・ミュッラー=ローレンツ |
★ |
|
★ |
|
| 成田勝美 |
|
★ |
|
★ |
| 士官 |
二階谷悠介 |
★ |
|
★ |
|
| 谷川佳幸 |
|
★ |
|
★ |
| 舞踏教師 |
近藤政伸 |
★ |
|
★ |
|
| 経種廉彦 |
|
★ |
|
★ |
| かつら師 |
志村文彦 |
★ |
|
★ |
|
| 安藤常光 |
|
★ |
|
★ |
| 召使い |
宇野徹哉 |
★ |
|
★ |
|
| 畠山茂 |
|
★ |
|
★ |
| ツェルビネッタ |
シンディア・シーデン* |
★ |
|
★ |
|
| 幸田浩子 |
|
★ |
|
★ |
| プリマドンナ/アリアドネ |
マリアーナ・ツヴェトコヴァ |
★ |
|
★ |
|
| 岩永圭子 |
|
★ |
|
★ |
| ハルレキン |
萩原潤 |
★ |
|
★ |
|
| 北村哲朗 |
|
★ |
|
★ |
| スカラムッチョ |
土師雅人 |
★ |
|
★ |
|
| 望月哲也 |
|
★ |
|
★ |
| トルファルデン |
若林勉 |
★ |
|
★ |
|
| 鹿野由之 |
|
★ |
|
★ |
| ブリゲルラ |
湯川晃 |
★ |
|
★ |
|
| 岡本泰寛 |
|
★ |
|
★ |
| ナヤーデ |
山本美樹 |
★ |
|
★ |
|
| 若槻量子 |
|
★ |
|
★ |
| ドリアーデ |
杉田美紀 |
★ |
|
★ |
|
| 井坂惠 |
|
★ |
|
★ |
| エコー |
森野由み |
★ |
|
★ |
|
| 田島茂代 |
|
★ |
|
★ |
*12日、14日に出演予定のティーナ・シュレンカーは健康上の理由により出演できなくなりました。代わってシンディア・シーデンが出演いたします。詳しくはここをクリックしてください。 |
| <公演日程> |
| |
| 2002年12月 |
12日
(木) |
13日
(金) |
14日
(土) |
15日
(日) |
| 15:00開演 |
|
|
○ |
○ |
| 18:30開演 |
○ |
○ |
|
|
開場は開演の60分前です。
開演45分前から、客席にて当作品の簡単な解説をいたします。 |
| <前売り開始日> |
| |
2002年10月6日(日)10:00〜 |
| <チケット料金> |
| |
| 席種 |
S席 |
A席 |
B席 |
C席 |
D席 |
E席 |
| 料金 |
18,900円 |
15,750円 |
12,600円 |
9,450円 |
6,300円 |
3,150円 |
|
 |
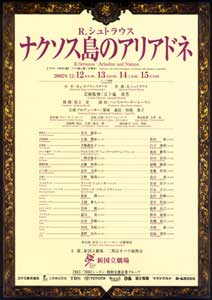 悲劇と喜劇の奇想天外な組み合わせ! 悲劇と喜劇の奇想天外な組み合わせ!
すったもんだの揚句、愛に包まれたハッピーエンドで幕となる
詩人ホフマンスタールとのコラボレーションによる
シュトラウス・オペラの真骨頂「”オペラの”オペラ!」
「アラベッラ」「サロメ」に続くR.シュトラウス・オペラの第三弾。発表される作品が次々とセンセーションを巻き起こすシュトラウスとホフマンスタールの名コンビによる異色オペラ。そんな二人がモリエールの戯曲「町人貴族」の劇中劇という形でこの作品を発表。しかし、上演時間が長すぎたこともあり不評に終ったため、直ちに全面的な改作をほどこし、物語の舞台をウィーンの富豪邸に移してプロローグでオペラに向けての制作準備という舞台裏を描き、続く祝宴の催し物として上演されるオペラは、ギリシア神話を題材にしたオペラ・セリオ。喜劇と悲劇を同時進行させる凝った作品が誕生しました。ツェルビネッタのコロラトゥーラを駆使した技巧の極致といったアリア「偉大な女王様」や、バッカスとアリアドネの二重唱などシュトラウスの音楽の魅力もいっぱい。今回のプロダクションは、ヴィーラント・ワーグナーの弟子といわれるハンス=ペーター・レーマンの演出であり、ドイツ各地のオペラハウスで実績を積んだ実力派、児玉宏が「サロメ」に続いて指揮、シュトラウスの劇音楽を鮮やかに描き出します。
あらすじ
前半のプロローグでは、舞台裏の様子が描かれています。18世紀のウィーン。金持ちの邸宅の祝宴で、新作の悲劇オペラ「ナクソス島のアリアドネ」の上演が予定されている。オペラ終了後に、道化の歌や踊りからなるオペラブッファが上演されるときいて音楽教師は困惑しており、反目するオペラ歌手と喜劇役者の混乱の中、今度は当家の主人の気まぐれで、この悲劇と喜劇をいっしょに上演せよと無理難題を突きつけられる。女優で踊り子のツェルビネッタは、仲間の道化役者にそれを伝えて即興で楽しく盛り上げようということになり、音楽教師は歌手たちをなだめ、結局はやるしかないということに。後半では、「ナクソス島のアリアドネ」が劇中劇として上演されます。ギリシアの孤島、ナクソス島。夫テセウスに捨てられたアリアドネは、嘆き悲しんで死を望んでいる。道化師たちが慰めるが効果がない。ツェルビネッタはアリアを歌って、人生と愛についてきかせ、彼女を慰める。そこにトランペットが響き、バッカスが来たことを告げる。アリアドネはバッカスを死の神だと思い、その身を任せるが、バッカスはアリアドネの美しさに夢中になり、彼女に接吻する。すると、死への憧れが生きる希望へと変わり、新しい愛が生まれる。
|

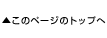
|
|
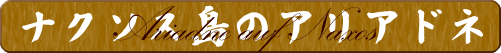

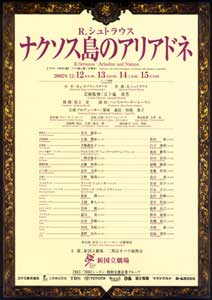 悲劇と喜劇の奇想天外な組み合わせ!
悲劇と喜劇の奇想天外な組み合わせ!