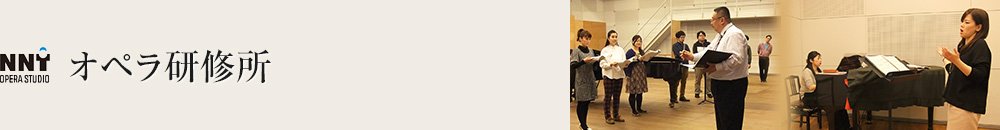オペラ研修所修了生・藤木大地さんの評論記事が掲載されました!
新国立劇場オペラ研修所 第5期修了生の藤木大地さんが、『メデア』へロルド役にて、ウィーン国立歌劇場デビューし、評論記事が掲載されました。
|
|
リンク先:
AMATI http://amati-tokyo.com/news/20160406.html
ウィーン国立歌劇場(英文) https://www.wiener-staatsoper.at/en/
backtrack(英文)https://bachtrack.com/review-reimann-medea-boder-marelli-wiener-staatsoper-april-2017
|
|
以下、評論記事訳
軽んじられたある女の怒り:ウィーン国立歌劇場でのライマンの殺戮の『メデア』
メデアは、著名なドイツ人作曲家のアリベルト・ライマンによって2010年にウィーン国立歌劇場にて初演された。これは、ライマンの8つのオペラのうちで最初に国立歌劇場を魅了した作品であり、それにふさわしくイオアン・ホレンダー(注:元総監督)が個人的に手紙を書いて委嘱したものだった。ライマンは、3つのグリルパルツァー(注:19世紀オーストリアの劇作家)の戯曲から素材を抽出した。『メデア』は先に書かれた2作品(『客人』『アルゴーの人々』)とともに、『金羊毛皮』3部作の一つである。
|
ジョン・アーヴィング(注:現代アメリカの小説家)のファンだけは『ガープの世界』の中で言及されているので聞いたことがあるかもしれないが、グリルパルツァーはドイツ語圏以外ではあまり有名ではない。しかし、彼のオーストリアでの存在意義は看過できないし、彼のいくつかの戯曲はウィーンの劇場のレパートリーの一部である。ライマンがこのようなオーストリアものの脚本を選んだことは、賢い選択である。初演は熱狂を持って迎えられたので、国立歌劇場ではそのシーズンに再演されることとなった。
|
これは裏切りと殺人と自暴自棄の物語である。
|
あらすじ:メデア(Claudia Barainsky)は魔力を持った女性で、イヤソン(Adrian Erod)を手伝って金羊毛皮を盗み出した後、ともにコリントに逃れた。この金羊毛皮は素晴らしい伝説上の宝物で、その所有者に強大な力を与えるが、同時に多くの難題で所有者を悩ますものである。イヤソンは、侍女のゴラ(Monika Bohinec)が冒頭の場面で嘆いているように、もはや妻であるメデアを愛していないが、彼はメデアと子どもたちのため、気乗りしないクレオン王(Norbert Ernst)と娘のクレオサ(Stephanie Houtzeel)の庇護を得る。彼らはメデアの力を信じていない。メデアの新しい環境になじもうとする努力はうまくいかないが、その心情は衣裳家ダグマー・ニーフィントによるメデアの鮮やかな衣裳と赤いドレッドヘアによって覆い隠されている。これに対して、イヤソンと子ども達はすぐにたやすく順応し、輝く白いギリシャの衣裳を身にまとう。神の使者(藤木大地)が到着し、イヤソンの叔父であるペリアスをメデアとイヤソンが殺害したことを糾弾して、彼らの運命を決定づける。これによりメデアは追放されたが、イヤソンはクレオン王により庇護されて残る。彼はクレオサと結婚し、子どものうち一人をメデアに返すことに同意したが、彼らも同行するのを拒否した。メデアは激しい復讐心に突き動かされ、ゴラと少しの魔法の力を借りてクレオサを殺し、また子どもたちも殺害する。イヤソンは追放され、メデアは盗んだ金羊毛皮を返して神々に自らをゆだねるためデルフィに向けて旅立つ。
|
音楽面では、その実直さは重厚な話の筋に沿うものだった。それは角が立って、不協和で、濃密だった。その音楽は幅広い作曲手法によって、オーケストラ的にも声楽的にも究極の音域にまで踏み込んでおり、金属的な特徴のみならず、鞭のような、様々な配列の打楽器的要素が組み合わされたものだった。複雑な譜面を通して巧みにオーケストラを率いた指揮者、ミヒャエル・ボーダーには脱帽である。
|
ライマンはM-E-D-E-Aの5音を作品全体にわたる音楽的テーマとして再構築使用し、登場する6つの役柄それぞれを音楽的に特徴付けた。(メデア役の)クラウディア・バラインスキーはタイトルロールとしての声部を受け持ったが、それは彼女が才気と巧みさをもって習得した発声不可能に近い境界線の声域であり、高いF音まで羽ばたき上がったかと思えば下がり、躍動し、まさに超人としか言い表せないやり方で(ベルカント時代ではない)現代のコロラトゥーラを演じるものである。3幕の中の、より劇的に作曲された場面のいくつかで、さすがにそれは不可能な感じに聞こえたが、ライマンはそのほとんどの場面では巧みに、そこまで彼女をかかわらせないようにしていた。破滅的役柄の女性が、頑健なアルトとしてキャスティングされる代わりに、最高音のテッシトゥーラを持っていることは興味深い。ベルクの『ルル』がぱっと浮かぶように、これには先例がないわけではない。
|
同様に、神の使者を一般的なオペラでのバスバリトンではなく、カウンターテナーの歌手に割り当てたことは革新的な印象だった。藤木大地は多種多様な声の振幅を容易く操る一方、彼の従者たちは銀色の衣をまとい、メデアとイヤソンを傲慢な態度で非難する。シュテファニー・ホウツィールのクレオサは、ベル、チェレスタ、ハープの気まぐれな音で特徴づけられ、彼女のコロラトゥーラはまるでスキップでもするように、その役柄の表層性を強調している。もし誰かがこの舞台で楽しさを感じられたのなら、それは彼女によるものだろう。モニカ・ボイネック(ゴラ)のメゾは厳しいまでに正確で、声の焦点とラインは印象的、またノルベルト・エルンスト(クレオン)のテノールはよく鳴っていて美しかった。アドリアン・エレード(イヤソン)は終始演技に乱れがなく、最初の妻を見限ってより使用価値のあるブロンドの女性を娶るといった無関心な夫を、安定感をもって効果的に表現していた。
|
ただ一点大いに落胆した点は、マルコ・アルトゥーロ・マレッリの装置が工業製品のように広がりに欠けたことである。灰色に縁どられたわびしい風景が舞台を支配し、かご状の立方体が裕福な「ギリシャ人」の集まる一角を示し、それと同様に冷たい金属製の階段がそこへ伸びている。おそらく誰もが、演者は月面に置かれていると考えたことだろう。というのは、メデアが憤怒すると、まるで重力を無視したかのように、また観客のまさかという思いを裏切るかのように、プラスチック製の石が観客に向かって軽く弾んで飛んできたりするからである。
ともかく、想像という以外の何物でもないものから力強い音楽的体験を生み出したすべての人に、また、キュレーションにより豊かになれば、古い慣習ですら革新的になるものだということを思い起こさせてくれたすべての人に、賛辞を贈りたい。