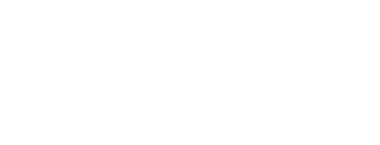- クリスマス・イブのパリ。若くて貧しい芸術家4人が住む屋根裏部屋で詩人ロドルフォが独り仕事をしていると、隣人のお針子ミミがロウソクの火を貰いに現れ、二人はたちまち恋に落ちる。画家マルチェッロも元恋人のムゼッタとよりを戻し、若者達は青春を謳歌する。2月の雪の日、ロドルフォは胸を患うミミを救うために悲痛な別れを決意する。数か月後、ミミが瀕死の状態で屋根裏部屋に運び込まれ、愛するロドルフォの傍らで息を引き取る。
-

原作とオペラで異なる
ミミの人物像ミミの魅力は、等身大のヒロインの魅力であるといえるかもしれません。19世紀はパリという大都会に、地方から出てきた若い女たちが貧しいながら仕事をして、一人暮らしを始めた最初の時代となりました。このオペラの原作は最近、日本で初めて全編の翻訳が出版されていますが(アンリ・ミュルジェ『ラ・ボエーム』辻村永樹訳)、そこでは当時の芸術家の卵たちと、若い女性たちとの自由恋愛がオムニバス形式で描かれています。
プッチーニの『ラ・ボエーム』には、一途なミミと奔放なムゼッタという二人の女性が登場します。ところがミュルジェの原作を読むと、彼女らは二人とも気まぐれな所があり、恋の相手も一人だけではなかったことが書かれています。ミミが病弱で、一途な性格の女性であるという設定は、原作のミミと、フランシーヌという別の挿話の主人公とのミックスによりプッチーニと台本作家たちが作り上げたものでした。
プッチーニは、ミミとムゼッタの違いを音楽で見事に描き分けました。第一幕は屋根裏部屋で出会ったミミとロドルフォが、互いの自己紹介をするアリアを歌います。第二幕の主人公はムゼッタです。クリスマス・イブのラテン地区で、ムゼッタは自分の魅力を披露するアリア「私が街を歩くと」で人々を虜にし、元恋人のマルチェッロとよりを戻します。そして第三幕はミミが中心となり、雪の中での二重唱、叙情的な美をたたえたアリア、そしてカップル二組の愛と別れを描く四重唱が聴きどころです。第四幕は屋根裏部屋に戻ってきたミミの死で終わりを告げます。『ラ・ボエーム』はまさに、歌と音楽で描かれた青春群像なのです。

- 【作曲】ジャコモ・プッチーニ/1893~95年
- 【原作】アンリ・ミュルジェ『ボヘミアンの生活』
- 【台本】ジュゼッペ・ジャコーザ、ルイージ・イッリカ(イタリア語)
- 【初演】1896年2月1日/トリノ/王立劇場
- 【制作】新国立劇場 2003年
- 【構成】4幕/約2時間
- 【演出】粟國 淳
- 【美術】パスクアーレ・グロッシ
- 【衣裳】アレッサンドロ・チャンマルーギ
- 【照明】笠原 俊幸