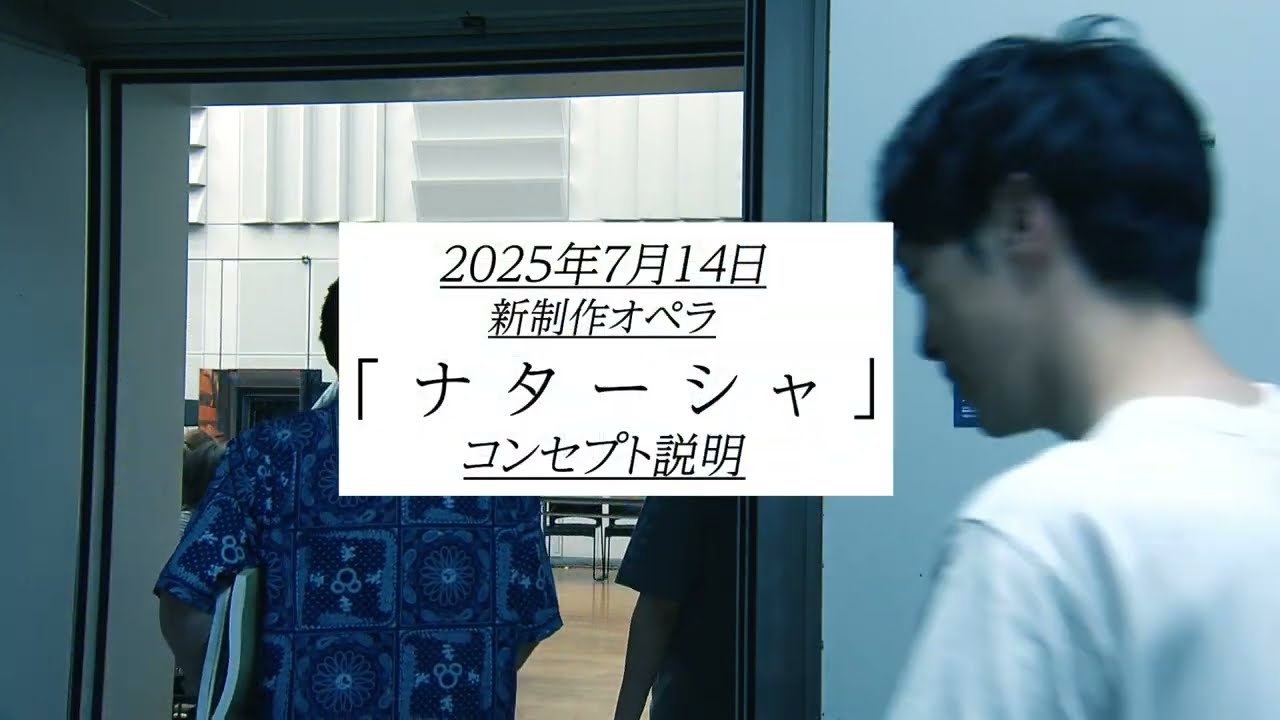オペラ公演関連ニュース
オペラ『ナターシャ』リハーサル開始!顔合わせ・演出コンセプト説明会レポート
7月14日、いよいよ新国立劇場創作委嘱作品『ナターシャ』のリハーサルが始まりました。
新国立劇場リハーサル室には、『ナターシャ』を作曲した細川俊夫、この作品を指揮する大野和士オペラ芸術監督、演出家のクリスティアン・レートをはじめ続々と来日したクリエイティブ・スタッフ、電子音響の有馬純寿、キャストとダンサー・助演、新国立劇場合唱団が一堂に会し、台本の多和田葉子もベルリンからリモートで参加して、顔合わせが行われました。
顔合わせにはナターシャ役:イルゼ・エーレンス、アラト役:山下裕賀、メフィストの孫役:クリスティアン・ミードル、ポップ歌手:森谷真理・冨平安希子のほか、ビジネスマン役:タン・ジュンボ、ティモシー・ハリス、ダンサー・助演、新国立劇場合唱団が参加。演出・美術を担当するクリスティアン・レート、スタッフからは美術:ダニエル・ウンガー、衣裳:マッティ・ウルリッチ、映像:クレメンス・ヴァルター、振付:キャサリン・ガラッソ、そして電子音響を担当する有馬純寿が紹介され、顔合わせに続いて演出・音響のコンセプト説明がありました。
細川俊夫さん、多和田葉子さんと大野和士芸術監督のあいさつと、演出・音響のコンセプト説明の概要をお伝えします。
【多和田葉子あいさつ】

「今までずっとひとりでポツポツとリブレットを書いていたんですけれど、長い孤独な時間が細川さんのおかげで音になり、その音がこんなにたくさんの方々から流れ出してくるんだなということを実感しながら映像を見ております。東京の会場の顔合わせの映像がパソコンの中に小さく映っているんですけれども、非常に大きなものとして感じております。大変楽しみにしております。」
【大野和士芸術監督あいさつ】

「待ちに待ったプロダクションという期待の声が沢山届いています。皆さんにお力をお借りして、素晴らしい舞台になるよう私も全力を尽くして参りたいと思います。まず、細川俊夫さんに大きな拍手をお願いいたします。
新国立劇場で上演した『松風』と比べても大規模な、ソリストと合唱の皆さんの出演する新作『ナターシャ』が、いよいよ世界初演を迎えます。この作品は私たちの力を示す機会となるでしょう。
多和田さんと細川さんは一緒に小さなアンサンブルのための音楽劇を創られていますが、このように大勢の力で上演する大規模作品というのは、お二人にとっても初めていうことです。この上演を作者のお二人へ、私たちが差し上げたいという風に思っています。
『ナターシャ』は劇場いっぱいに広がる音とアンサンブル、そしてめくるめく、輝いていくオーケストレーションが聴きどころの一つです。歌手の歌がこう流れてくると、雨が降るように、ひとりずつ、ポツ、ポツ、ポツ、ポツポツ...と別れて、本当に雨が降ってくるような音の中を皆さんが歌うというようなところもあります。それから3人が小気味よく連携を取りながらアンサンブルが運ぶようなところもあって、三次元的に出て来る声とオーケストラのアンサンブルが昇華している作品だと思っています。楽しんでいきましょう。」
【細川俊夫あいさつ】
【演出家のクリスティアン・レートからの演出コンセプト説明】

「この素晴らしい作品を今日まで準備し導いて下さったコラボレーターの皆さんに心から感謝を申し上げます。さあ皆さん、地獄への旅へ出発しましょう。
この物語は、ナターシャとアラトという少女と少年が、どことも分からない地の海辺で出会うところから始まります。彼らの問題は、お互い言葉が通じないことです。言葉が通じない中で、どうやってふたりがコミュニケーションをとっていくのか、このグローバルな世界で人が何を頼りにお互いを知っていくのかということが、この作品の中で語られています。
そして『メフィストの孫』という者が現れて、ふたりをいろいろな『地獄』に、人間によって環境も人間性も破壊された世界に連れて行くわけです。ナターシャとアラトはもともと、破壊された世界のトラウマを抱えています。人間というものが攻撃者であり、そして被害者でもあるという世界が描かれています。」

「アラトとナターシャは、言語の壁が立ちふさがりながらも、いろんな世界を試していく中で、惹かれあっていきます。それを邪魔するのが、メフィストの孫という役です。彼はゲーテの『ファウスト』の悪魔を名乗ってはいるけれど、彼が見せる世界は、悪魔が破壊したのではなく、人間が破壊している地獄です。私たちが今生きているこの世界そのものがまさに地獄だ、ということが描かれていきます。そして、失われた人間性、失われた環境をどうやって取り戻していくのか、それには何が必要なのかということが問われていきます。
メフィストの孫による地獄めぐりの旅は、一つのテストなのです。二人の若者が通過していく中で、自分たちのアイデンティティ、自分たちは何者なのかということに直面し、そしてトラウマに対峙し、そこから愛というものを知っていく。これは新しい世代の若者たちがこの世の中がどういうものか知っていく道筋でもあります。
例えばオペラ『魔笛』で、タミーノとパミーナが試練を受けながら、自分たちが本当に目指していく未来はどういうものかということを知る、そんなものと共通しています。私たちの世界がより良いものになることを探していく、そういう地獄めぐりです。」

「7つの地獄を次々に具現化してスピーディーに見せていくというのは、私たち演出、デザイナーチームにとって大変大きな挑戦でした。そこで、次々にイメージが移っていく夢の世界のように、そして映画のように、シーンを止めずに、地獄という想像上の世界を作っていける方法を模索しました。アラトとナターシャの目を通した世界を具体化するという姿勢で考えています。
この地獄は自分たちの中に起こっているもの、自分たちの中にあるものとも言えます。舞台全体がタイムトンネルのような形になっていて、手前から奥の方に向かっていくというダイナミズムがあります。そして、この地獄はどんどん旅をしていくにつれて、深いところ、深いところに入っていくということで、この地獄を俯瞰しているような世界を、プロジェクションの映像の力も借りて表現していきたいと考えています。
ナターシャとアラトの先には、私たちが望む世界が待っています。これが今回作っていく世界です。」
電子音響の有馬純寿による音響面のコンセプト説明

「細川さんと打ち合わせをして立てたコンセプトが二つあります。ひとつは、単に効果音のようなものではなく、スコアの中の1パートとして書かれている音響、音楽の一部として作る音響があります。もうひとつは、音響による空間を客席側に作るということです。
ひとつめの音楽の一部としての音響ですが、今回の素材のほとんどは、自然音を収録しています。これから歌手の皆さんや、朗読をする皆さんのご協力で言葉を録音していくんですが、それを単純にコラージュしていくだけではなく、電子音楽の手法を使って時間を伸ばしたり、音の高さを調整したり、様々な加工をして、音響として成り立つものとして使っていきます。
もうひとつは、客席側に劇場のご協力を得て、20 数チャンネルのスピーカーを3フロアに前後左右を取り巻くように設置し、いわゆるサラウンドの音響を設置します。5.1サラウンドというような普通のサラウンドは正面ですけれど、前後左右、上下3階層を使って、上から下に落ちてくる、下から上、といった条件も含めて、劇場そのものをひとつの音響空間にすることをコンセプトに、作業を進めております。
作品とも連動することですが、なるべく多くの、日本だけではないマテリアルを使いたいということで、今回、日本国内の音素材だけではなく、ニューヨークや、ドイツ、アイスランド、中国、世界各地の音を知人の協力を得て集めておりまして、今、目下編集中という状況になります。そういう意味でも作品のコンセプトに沿ったサウンド作りを目指しています。」
今日と向き合うオペラ『ナターシャ』は、8月11日(月・祝)に世界初演を迎えます。どうぞご期待ください。
(写真:堀田力丸)
- 新国立劇場HOME
- オペラ公演関連ニュース
-
オペラ『ナターシャ』リハーサル開始!顔合わせ・演出コンセプト説明会レポート