- 『神々の黄昏』は、リヒャルト・ワーグナーがオペラ作家としてのキャリアの半分余りを費やして完成させた大作だ。彼が最初に台本の下書きをしたためたのは1848年、まだドレスデン宮廷歌劇場の楽長職にあるときだった。それは英雄歌劇(ヘルデンオーパー)「ジークフリートの死」と名づけられた単独作品だったが、物語の前史を書き加えるうちに構想は膨らみ、ドイツの英雄叙事詩、北欧神話、ギリシャ悲劇の要素が換骨奪胎されて序夜と3日間の舞台祝祭劇(ビューネンフェストシュピール)「ニーベルングの指環」となった。そしてその最後を飾るのが本作『神々の黄昏』であり、その構成は全体のそれに似て序劇と全3幕からなる。
しかしワーグナーは、革命運動に加担した罪で国外への逃亡を余儀なくされ、ようやく第一作の作曲に取りかかったのは1853年、スイスのチューリヒにおいてであった。だが、自身の芸術上の理念を実現するために奔走した彼の人生は波乱に満ちたもので、最終作の作曲に取りかかるまでにはさらに16年の歳月を要した。当時ワーグナーは、すでにドイツの国民的作曲家とみなされており、バイエルン国王の援助を受けて「指環」完全上演のプロジェクトの実現も現実味を帯びはじめていた。1874年11月21日、ようやく『神々の黄昏』の総譜の最終頁が書き終えられたが、これは本格的な上演準備へ向けての新たなスタートでもあった。1875年には事前練習が行われ、彼はみずから出演歌手たちを指導した。その後もワーグナーは、作曲家として楽譜に最後まで微修正を加え、演出家としては舞台装置・美術の専門家たちと細部の詰めを行い、そしてプロジェクトの総監督としてあらゆる細事に忙殺された。そうしてついに、1876年8月13日に開幕した祝祭において「指環」は完全上演され、その最終日、8月17日が『神々の黄昏』の世界初演の日となったのである。
 Production:Finnish National Opera
Production:Finnish National OperaPhotographer:©Karen Stuke
 Production:Finnish National Opera
Production:Finnish National OperaPhotographer:©Karen Stuke
- 『神々の黄昏』は、常に過去の出来事を振り返りながら進行してゆく叙事的な物語である。幕が開くと、過去・現在・未来をつかさどる3人のノルンがこれまでの出来事を振り返り、オーケストラもまた、そこで語られる場面の音楽を回想する。前三作にあらわれたさまざまな素材――息の長いメロディから断片的なモティーフにいたるまで――の自由な加工、変形、結合によって紡ぎ出されるのが『神々の黄昏』の音楽の特徴であり、それを奏でるオーケストラは、物語の内容を登場人物たち以上に雄弁に語る。とりわけ、オーケストラがもてる表現力のすべてを発揮して音響的絵画を描く場面転換の音楽は、その描写力の豊かさと全オーケストラによって構築される響きの伽藍によって聴く者を陶酔へと誘う。
その一方で歌手たちには、美しいアリアを歌うことではなく朗誦風に語ることが要求される。だがそれは、ただの語りというよりも「劇的語り」と呼んだ方がよい。というのも、歌唱パートは感情の動きに応じて、テノールやソプラノといった声域をまったく顧みないほどに音域が拡大しているからだ。とりわけ感情の高まりが並外れた音の跳躍となってあらわれるのは、四部作のなかでも本作に特徴的な現象である。高音域からの急激な落下や超低音での息を潜めた語りには、流麗なアリアを聴くのとはまた別の醍醐味があり、まさにそこに、ワーグナー歌唱の本質があるのだ。
- 『神々の黄昏』の物語は前史の理解を前提しているため、複雑であることは否めない。しかし、筋の中心にいるのは英雄ジークフリートと、彼の所有する指環を奪還しようと画策するハーゲンの2人である。
- [序劇] 岩山の頂に暮らしたブリュンヒルデとジークフリートであったが、英雄は妻のもとを離れて人間の世界へと旅立つ。
- [第1幕] ライン川を旅する彼が出会ったのが、周辺を治めるギービヒ家の当主グンターとその妹グートルーネ、そして彼と異父兄弟のハーゲンであった。ニーベルング族のアルベリヒを父に持つハーゲンは、本来父の所有物でありながら主神ヴォータンに強奪され、紆余曲折を経てジークフリートの手に渡った「指環」を奪還する使命を負わされている。このニーベルングの息子はいま、その使命を果たすべく目の前にあらわれたジークフリートに忘却の薬をもって妻ブリュンヒルデの記憶を消去し、独り身の女グートルーネを娶らせ、グンターと義兄弟の契りを結ばせる。さらにハーゲンは、グンターの地位と名誉に適うとしてブリュンヒルデの名を挙げ、「恐れを知らぬ英雄」しかたどり着けない岩山の頂に住まうこの女を、グンターの姿に変装したジークフリートに手に入れさせるよう仕向けた。
- [第2幕] 岩山から誘拐されたブリュンヒルデは、グンターに連れられてギービヒ家に迎えられるが、そこで彼女が目にしたのは、見知らぬ女に寄り添うジークフリートであり、その手には、誘拐の折に剥奪された指環があった。怒りに震える英雄の正妻は、裏切り者として夫を告発するが、祝福ムードだった家臣たちには状況が飲み込めない。唯一人すべての状況を把握するハーゲンは、裏切られた妻に夫への復讐を耳打ちし、公然と名誉を傷つけられたグンターにも、義兄弟へ制裁を加えることを提案する。かくして「ジークフリートの死」を合言葉に、ハーゲンの指環奪還計画は最終段階を迎えることになる。
- [第3幕] 騒動の翌朝、グンター、ハーゲン、そしてギービヒの家臣たちとともに狩りに出かけたジークフリートは、川縁で休息をとる折に記憶を取り戻す薬をもられる。ハーゲンにそそのかされるままに養父ミーメや、大蛇ファフナーとの戦いのことを語るうち、彼は岩山の頂に眠るブリュンヒルデとの出会いにまで言及してしまう。裏切りの罪を公然と認めることとなってしまった英雄の背中に、ハーゲンは制裁の槍を突き立て、英雄の殺害計画がここに成就する。
ジークフリートの亡骸が館に到着すると、夫の帰りを待っていたグートルーネは絶望し、兄弟に説明を求めるグンターもまたハーゲンの手にかかる。一切の邪魔者を排除し、いよいよジークフリートの手に輝く指環にハーゲンが手を伸ばすと、亡骸の腕がすっと高く上がり、すべてを理解したブリュンヒルデがあらわれる。彼女は一同に事の顛末を語り、館の前に薪を高く積み上げるよう命じて火を放ち、英雄の亡骸を火葬し、彼女もまた愛馬とともに燃え盛る炎のなかに飛び込む。炎は天高く昇り、天上の神々の世界へと到達してすべてを焼き尽くす。地上ではライン川の水が溢れて灰を飲み込み、その波間にあらわれたラインの乙女たちの手に指環を見たハーゲンは「指環から離れろ!」と叫んで水に飛び込み、姿を消す。彼の計画は文字通り水泡に帰し、神々の世界は滅び、英雄もその妻も消え、呪われた指環はラインの川へと還って浄化されたいま、残されたのは人間の世界なのであった……。

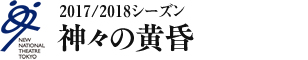

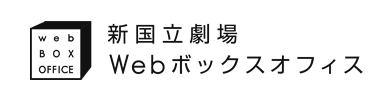







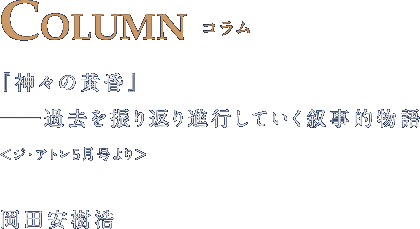
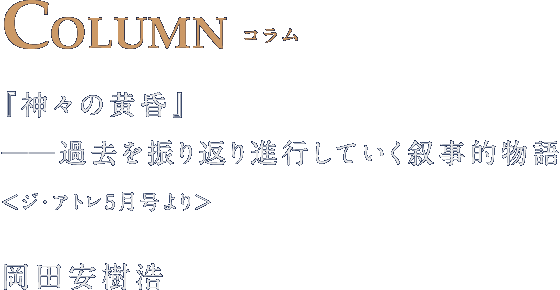


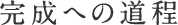
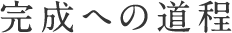


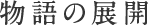

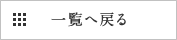
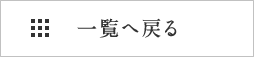
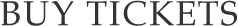
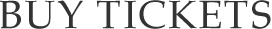
 WEBからのお求め
WEBからのお求め







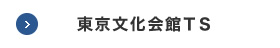
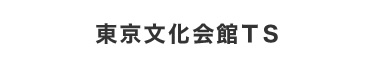
 お電話でのお求め
お電話でのお求め グループでのお申し込み
グループでのお申し込み