現代戯曲研究会
座談会 連続3回掲載その(3)
いま、同時代演劇とは?
小田島恒志 佐藤 康 新野守広 平川大作 鵜山 仁(進行)
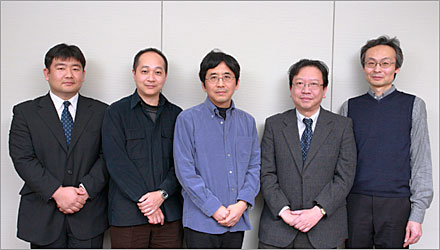
物語への回帰も
<承前>
小田島●今回のシリーズ第3弾『タトゥー』にもそうですが、サラ・ケインに代表される“イン・ユア・フェイス”以降の人たちには詩的な表現が出てきます。必ずしも美しくはないんですが、セリフを文章で言わないのが多くなっていますね。ベケットの影響もあるかもしれませんが、セリフは文で表すものではないという雰囲気すらある。日常会話がそうだからといえるかもしれないけど、単語がぽつっと出てくることの連続。
といって、イギリスの演劇について言うと、そればかりではない。いわゆる大御所作家たちも健在で、すばらしい作品を書きまくっています。アラン・ベネットもトム・ストッパードも、かつて前衛的だった人たちが今では文学的な骨太のものを書いています。サラ・ケインと同世代の暴力満載だった作家たちがむしろおとなしくなってきているかもしれません。が、おとなしくてもインパクトのある作品を書こうとしているようにも見える。相変わらず言葉遣いは激しいし。で、実際、観客はどうかというと、やっぱりそういうものなのだと素直に受け入れられる世代と、“ブラッディー”という言葉をいまだに受け入れられないイギリス人がいます。シリーズ第2弾『シュート・ザ・クロウ』のオーウェン・マカファーティーが書いているのは人情的ないい話ですが、労働者の会話なのでFワード(F**K)満載なわけです。劇評ではいい話として評価されつつ、最後にひと言、あなたがFワードに抵抗がなければ観ることを勧めると書かれている。ちなみに、サラ・ケインは当初イギリスで酷評され、ドイツ、フランスで評価されてからイギリスで認められました。
佐藤●人間が言葉を使ってコミュニケーションするという前提そのものが壊されたということのほうがはるかにスキャンダラスだと思います。人間を登場人物として出すためには、その人の語っている言葉やその人が置かれている状況が真実のものとして誰かに伝えられるという前提があるわけですよね。無意識の発見とか、人間の人格なんて環境で作られちゃうんだとか、すべて実体が構造物のなかの網の目に引っかかるだけなんだという主体と言語の関係の逆転が、構造主義時代にあって、従来のように近代的主体というものをもった登場人物が出てくるドラマを書くことに何の意味があるんだろうかと。
小田島●構造主義以前も、ベケットからそうだということですか?
佐藤●地続きになっていると思います。
鵜山●全体像として俯瞰されたのは、もう少し後かもしれません。コミュニズムも含め、強権権を生成しているドグマをどう脱構築するか。
佐藤●言葉を語っていることそのものが、権力の側にいるんだという意識ですよね。フランスの場合、アフリカに植民地が多くあって、アフリカでの演劇がどういうものかを考えるとわかりやすいんですが、演劇を行なうこと自体が支配者の言語で支配者の真似をするということでしかない。ところがアフリカの土俗的な習俗、お祭りのようなものも演劇だとヨーロッパが発見してしまう相互的な視線の交錯がポスト・コロニアリズム以降のヨーロッパと植民地の不思議な関係です。演劇とは、他者の言語を使って他者の真似をすることだ。植民地だけがそうなんじゃなくて、実は近代ヨーロッパがすでにそうなんだという発見があるような気がします。
鵜山●感情移入と異化効果、キャラクターの一元的な心理から出たり入ったりする手法……。
佐藤●異化の階段を一つ上がった異化ですよね。言語そのものに対して異化的な関係であろうという。
鵜山●しかし、じゃあ一体どういう主体がそういう関係を作り出しているのかが問題になってくる。それは、果たして本当に世界を広げているのかどうか。
新野●脱構築の話は、ドイツだとハイナー・ミュラーやエルフリーデ・イェリネクになりますが、これには明確な相手がいます。ハイナー・ミュラーは社会主義リアリズムに対抗するために脱構築を試みて、『ハムレットマシーン』を書いた。イェリネクは男性社会に対する明確なアンチテーゼとして散文形式の難解な戯曲を書く。明確な相手があって出てきた脱構築ですが、空回りし始めたと思われる状況が90年代に訪れた。皆ついていけないわけです。そこでドイツの観客は物語に回帰する道を求めるようになった。ローアーがブレヒトの叙事的手法を取り入れる劇作家として評価されるようになったのは、こういう背景があるからです。『昔の女』のシンメルプフェニヒのように、メディア社会で変容した感覚を描く作家も高い評価を受けるようになった。ところで日本では、たとえばケラリーノ・サンドロヴィッチがメディアのなかで変化した身体感覚を描きますが、彼の世界では誰もが揺れている。一方ドイツの作家の世界には、揺れない主体がどこかにある。ドイツはコンビニのない社会です。日本のように資本を野放しにしない。そういうことも関係しているのかもしれない。逆にいえば、ドイツはケラや松尾スズキのような作家が出にくい社会です。
佐藤●それは観客がみな同質であるという前提がないからですよね。日本は、観客がみな同質であるという前提で作家が書いている。ドイツもフランスも観客は同質な人たちではありません。メディアに寄りかかる書き方はできない。日本で“幸せ”を表象するためには、お父さんが「ただいま」と言って帰ってきて背広を脱いで、家族が鍋を囲んでいればいい。そのような表象で“幸せ”は表現できるけど、フランスでそれが自動的にそうはならない。それを自覚しなければ作品が書けない社会です。日本はそのハードルが低すぎる。
新野●“サッチャーの子どもたち”と平川さんがおっしゃっていましたが、サラ・ケインは日本では同時代的に紹介されませんでしたね。“イン・ユア・フェイス・シアター”の作家では、マーティン・マクドナーが長塚圭史演出で大きく紹介されましたが、“イン・ユア・フェイス”を生んだイギリスの社会的背景が伝わったかどうか疑問です。逆に今、不況でセーフティーネットがないのがわかってきたこの時点でなら、イギリス社会と似通ったところが見えるかもしれない。だとすると、ここでサラ・ケインを登場させた社会的背景を振り返るのは、日本の演劇にとっても意味のあることだと思います。
平川●やはり階級の違いが大きいかと。“イン・ユア・フェイス・シアター”の登場人物は階級的に下の人たちです。淫らで突拍子もなく、暴力的で過激亜登場人物を前に、観客は「こんな人間いないだろう」とつぶやく。しかし、作家たちによればそうした人間像こそ日常で、演劇を文化的な消費の対象とする観客とは社会を捉える認識の視点が違う。先ほど観客は同質でないという話がありましたが、日本でも階級とはいかないまでも階層の違いが出ていますね。
佐藤●いまの日本の若い人たちの演劇を支えている感性は、フリーターと引きこもりですからね。この両方を兼ねないといまの演劇はわからない。
